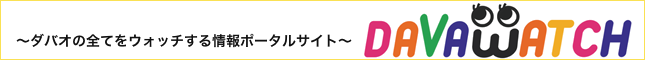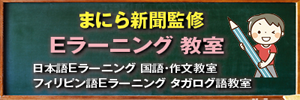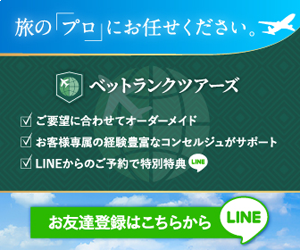ハロハロ
今年3月に生誕百周年を迎えた映画界の巨匠、黒澤明の映画祭が世界各地で催され、ここフィリピンでも秋口に首都圏の3市で主な作品が上映された。黒澤の遺伝子を受け継いだと言われる米国のジョージ・ルーカスをはじめ「黒澤チルドレン」も各地で活躍している。その黒澤に生前、一度だけインタビューしたことがある。30分足らずだったが、どうしても忘れることができない。多弁なはずの巨匠がインタビューの間、ほぼ、だんまりを決め込んだからである。1970年代初め、日本映画の衰退が言われた頃のことだ。
◇
当時、黒澤は新作がヒットせず制作資金も底をついていた。とはいえ、巨匠にインタビューの約束をとりつけるのは骨が折れ、映画担当の先輩記者の口利きがあって、やっと3カ月後に30分の約束がとれた。それも異例なことに午前零時半から東京・赤坂の民放局前の喫茶店奥の一室を指定された。あとから考えれば、その民放局での録画収録の後で複数のインタビュー申し込みにまとめて応じる、との段取りだったようだ。ところが、約束の日が近づいてきた頃、ある週刊誌が大見出しで「黒澤自殺未遂」を報じた。当然、約束はキャンセルされると勝手に思い込んでいたら、秘書が「予定どおり会う」と言う。
◇
約束の時間にやや遅れて現れた黒澤は、片手を挙げる仕草で質問を促した。実のあるインタビューをするには、まず相手と打ち解けた雰囲気を作るのが先。下手な冗談を言ったが、巨匠はにこりともしない。本題に入った。木で鼻をくくったような返答ばかりで取り付く島もない。どうしたものか。とっさに「自殺未遂」報道の話題をぶつけ巨匠を怒らせる手が浮かんだ。が、紹介の労をとってくれた先輩記者の顔が浮かんで踏み込めなかった。「あの話はするな」と、念を押されていたからだ。それにしても、だんまりを決め込むくらいなら、なぜインタビューに応じたのだろうか? その後しばらくして、黒澤の作品は息を吹き返した。比で初の上映というふれ込みの催しには行けなかったが、繰り返し上映される巨匠回顧フィルムを見るたびに、あの時の光景が浮かんでくる。 (邦)