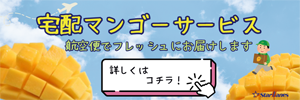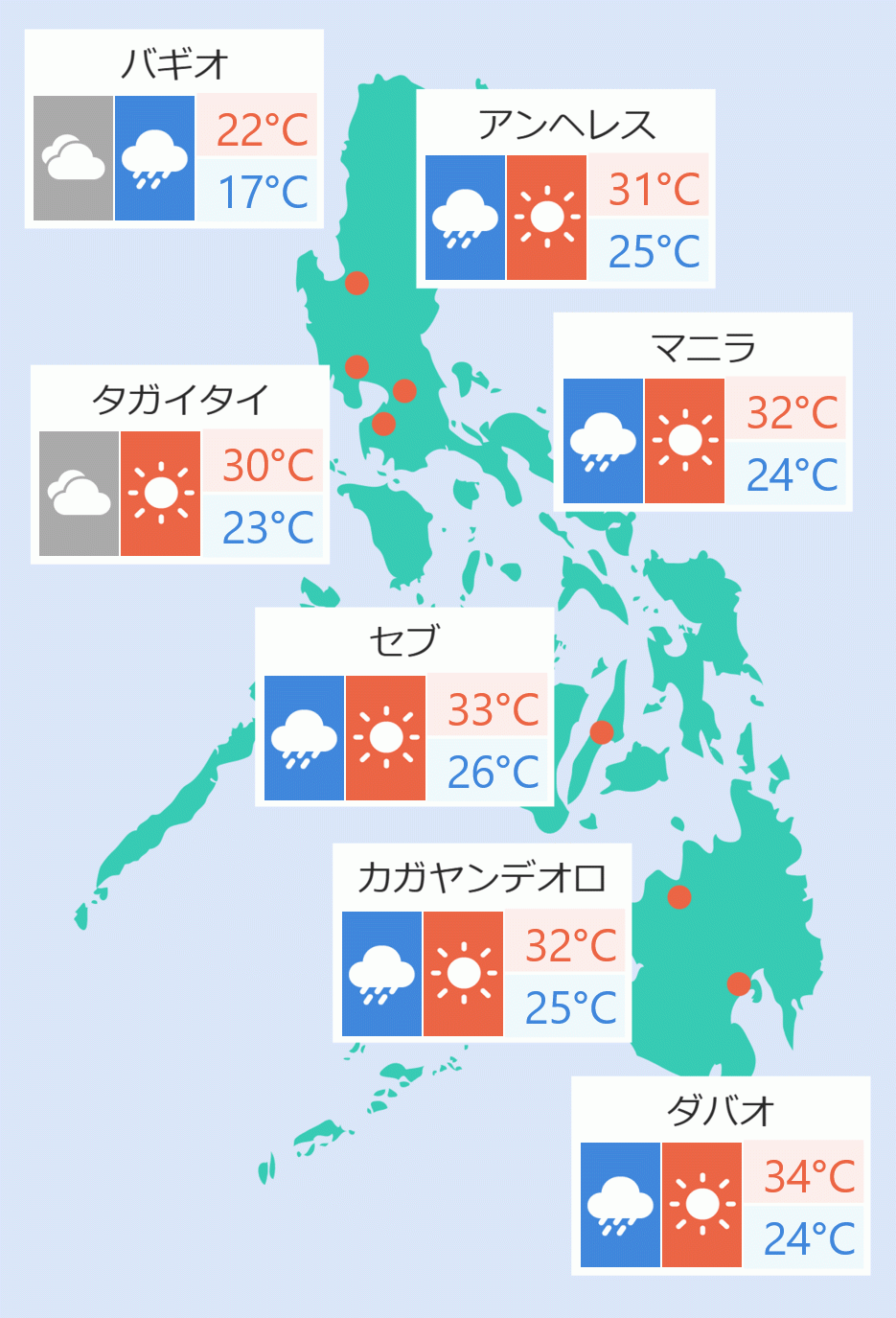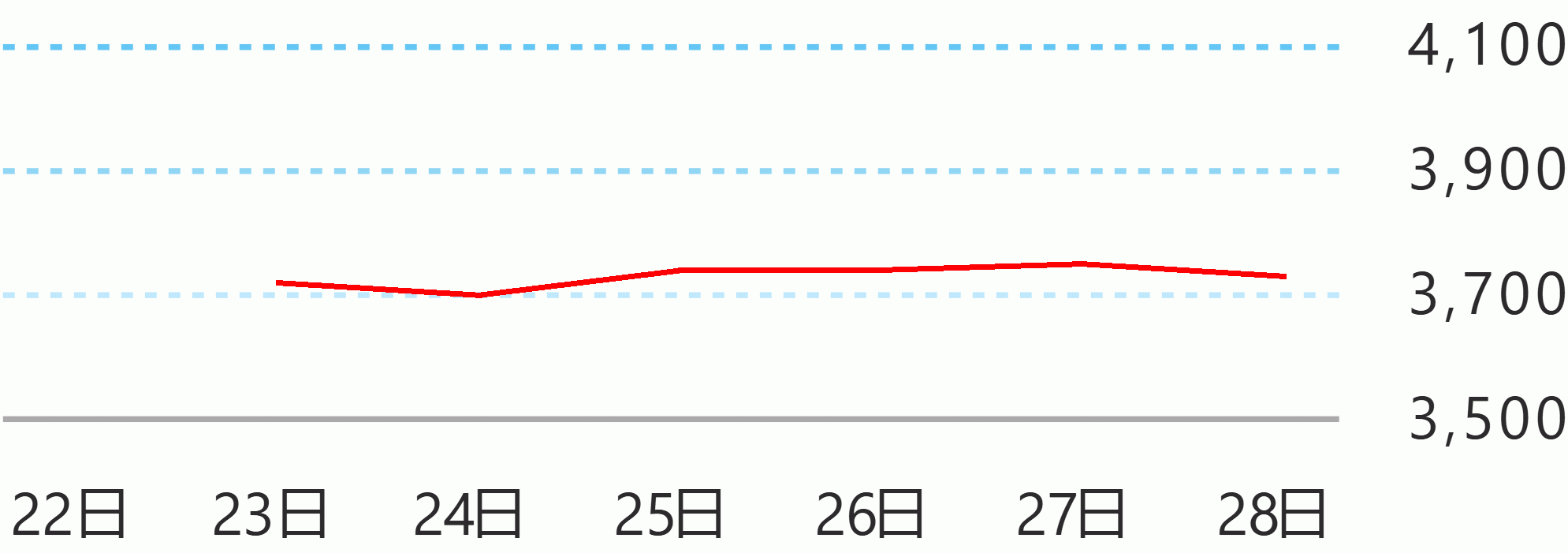第1回 ・ ヒップホップを通じて山梨とマニラをつなぐ

国境の垣根が低くなる中で、人々の生き方や価値観の多様化が進む。日本政府がフィリピン人への興行ビザ発給を制限した2005年以降、両国関係の中核だった「恋愛交流」の機会は減った。しかし、若い世代を中心に、アートやポップカルチャーなど、新しい交流を切り開く動きが出てきた。両国を結ぶ芸術や文化の担い手を通して、その芽生えを探った。
山梨県笛吹市(旧一宮町)を拠点に活動するラップグループ「stillichimiya」(スティルイチミヤ)は、現在の日本のヒップホップシーンで最も勢いのある集団の一つだ。甲府市を舞台に、地方都市の現状を描き、フランスの「ナント三大大陸映画祭」でグランプリに輝いた映画「サウダーヂ」(10年、富田克也監督)にも出演し、話題になった。
グループの楽曲プロデューサーを担当するYOUNG Gさん(30)は、おそらく初めてフィリピンのヒップホップコミュニティーと交流を持った日本人アーティストだ。
政府系外郭団体「国際交流基金」の助成事業でもある「ラップ・イン・トンド」の一環として2011年5月、Gさんと「おみゆきCHANNEL」の名でユニットを組むBIG BENさんの2人は、約2週間の日程でマニラ市トンド、ミンダナオ地方ダバオ市の現地の若者たち向けのワークショップを行うためにフィリピンへ飛んだ。
「マニラへ向かう機内で、なぜ今回自分たちが選ばれたのかを考えた。山梨という地方で活動する自分たちの東京に対する姿勢と、マニラの中でトンドが置かれた位置には、共通点があるかもしれない。だからこそ、自分たちにしかできないことがあるはず」と強い縁を感じたという。
1970年代にニューヨークのスラム街に住む黒人たちが生み出したヒップホップは、打ち込みのビートに言葉を載せる「敷居」の低い音楽だ。社会への不満を歌う反骨心を持ったアーティストが多く、近年ではフィリピンでも、特にトンドなど貧困地域の若者の表現手段として盛り上がりを見せている。
Gさんたちをマニラで迎えたのは、トンド出身の元ギャングメンバーで構成される「Tondo Tribe」のラッパー、シルバート・マヌエルさん(26)。
「トンドはギャングがたむろする危険なスラム街というイメージよりは、子どもたちが多い活気にあふれた場所でした。みな感情むき出しに、よく笑い、よく怒る。見るからに生活は大変そうなのに、彼らはそれをあまり表に出さない。陽気で前向きなのは、生来の気性なんでしょうね。真夏の暑い時期でしたが、シルバートと行った看板もない地元の店で食べたハロハロ(フィリピン風かき氷)が美味しかった」と頬をゆるめる。
ワークショップは計10日間、マニラ市エルミタの子ども美術館「ムセオ・パンバータ」、ダバオ市のミンダナオ国際大学で開かれた。マニラではトンドから約15人、ダバオでは約10人、ラッパーや楽曲制作を目指す若者たちが集まった。
「機材が不足しているので、ラッパーたちはわれ先にと録音する。音楽に対しては日本人よりもハングリー。楽曲制作ではインターネット上の無料音源を使う手法を中心に教えました。向こうではキーボードを使わずに、マウスだけで作る『マニマニ』という独自の制作手法があることを知って驚きました。モノがないなら、自分たちで生み出してやろうというのが、ヒップホップの面白さ。彼らの貪欲な姿勢には刺激を受けました」。
Gさんは帰国後、計6曲のフィリピン語ラップを含むアジア7カ国から選曲したアルバム「PAN ASIA」を発表、日本であまり知られないアジア発のヒップホップに陽を当てた。
「フィリピンで初めて、日本以外のアジアのヒップホップを知り、その魅力に気づきました。今回できたこの縁を、今後どう形にしていくか。マニラとダバオで作った音源もリリースしたいし、もっと共同制作もしたい。フィリピンのヒップホップを、山梨で活動する自分たちがつなぐ図式も面白い」と意欲的だ
山梨とフィリピン、そして、日本とアジア。元々「僻地」で生まれたヒップホップだからこそ、今後Gさんたちが仕掛ける「化学反応」の行方が楽しみだ。(野口弘宜、つづく)
※スティルイチミヤ公式HPはこちら
(2013.1.2)


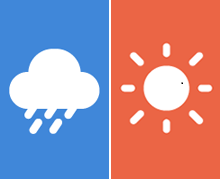


 English
English