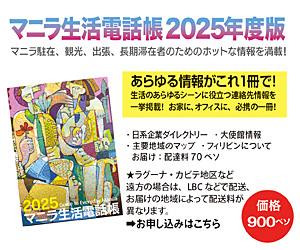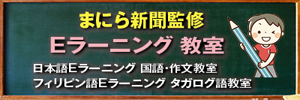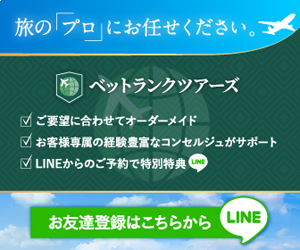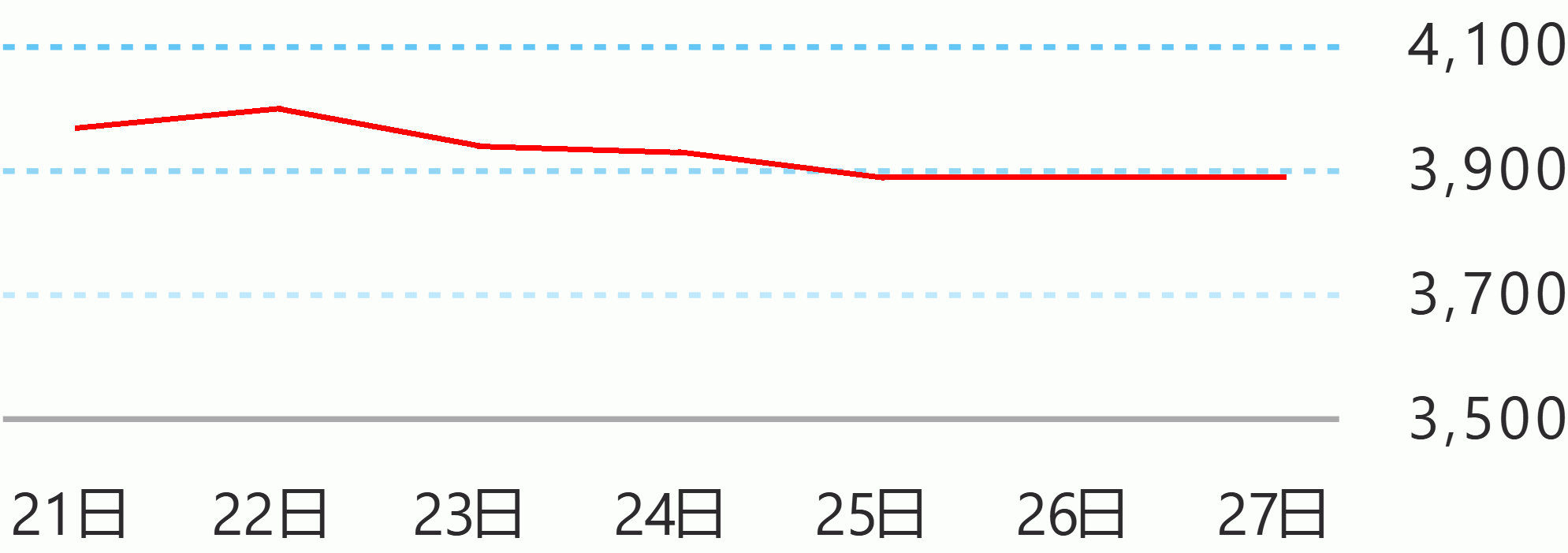多くの民間人犠牲者を出したマニラ市街戦の開戦日から80年を迎えた3日、戦時中に日本軍による聖職者虐殺事件があったアダムソン大学のビンセント校舎で、マニラ市による追悼式典が開催された。
式典には同市のラクナ市長、比国軍のラリダ参謀副総長、比国家歴史委員会のアレバロ理事、退役軍人協会のエスクエラ副代表のほか、米国のカールソン大使、カナダのハートマン大使、ニュージーランドのマッキントッシュ大使、スペインのウトライ大使、オーストラリアのコレット臨時代理大使、英国のホワイト臨時代理大使、日本の松田賢一次席公使、メキシコのロメオ総領事ら各国の代表が出席。ラクナ市長とアダムソン大のピラリオ学長は、80年前の事件を振り返り、今日の自由のために犠牲となった全ての人々を追悼した。
▽遺体を水路に投棄
アダムソン大のピラリオ学長は、80年前に同大で発生した虐殺事件を説明。「1944年6月、ここに住んでいた聖職者たちは、占拠した日本軍を歓迎し、食料などの貯蔵場所として施設を提供した。しかし7カ月後、かれらは拘束され1945年2月9日にすぐ近くのバレテ水路まで連行され、そこで殺害されて遺体は20日間放置された。犠牲者には6人の司祭、修道士4人、神学生2人、聖具保管係、爆撃から避難していた中国人庭師が含まれていた」と述べた。 その上でピラリオ学長は、比独立の父ホセ・リサール博士の著書「ノリメタンヘレ(我に触れるな)」の中の一節を紹介。「私は祖国に輝く夜明けの光を見ることなく死す。それを見るあなたは、私の代わりに迎えよ。そして夜の間に死した者たちを忘れるな」という言葉を引用し、「解放と自由の回復を祝うとき、犠牲となった人々を思い出す。かれらこそ、自由を祝うこの日を実現させたのだ」と強調した。
ラクナ市長は、「ここで虐殺が発生した翌日には、同じ部隊が(同市にあったドイツ人居住者の社交場)「ジャーマンクラブ」に避難していた数百人の比人、ドイツ人、インド人の命を奪っている」とし、日本軍による虐殺は当時の同盟国のドイツ人居住者にも及んでいたことを説明した。 その上で「われわれが勝ち取った自由は、自らの意思で戦った人たちだけでなく、恐ろしい銃弾の雨の中命を落とした女性・女性、乳幼児のかけがえのない血の代償だ。この悲劇が決して忘れ去られないよう約束する」とした上で、「かれらの血の一滴一滴は愛国心の種だ。われわれの国が偉大になるためには、国民が英雄たちに感謝し、平和と進歩を実現させることが必要だ」と強調した。
▽荒廃したマニラの記録
アダムソン大ビンセント校舎では3日から14日にかけ、同大と米国国立公文書館に残されたマニラ市街戦の写真の展示が行われる。展示される写真の中には、日本軍捕虜が戦後のマニラ市の大規模瓦礫撤去に動員される様子や、倒壊した旧立法府議事堂、マニラ軍事法廷にかけられる山下奉文陸軍大将、マニラ市街戦の最中にパシッグ川を挟んで銃を構える比米軍兵士などの写真が展示される。
45年2月3日から3月3日まで続いたマニラ市街戦では、日米両軍の砲撃や戦闘に巻き込まれ、民間人10万人が犠牲になったとされる。レニングラード市街戦などに匹敵する殺りくと破壊が行われ、その惨状は「マニラの死」と言われた。(竹下友章)





 English
English