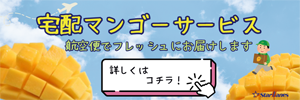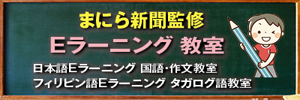マルコス大統領が大戦中の状況になぞらえ「比は地域の平和を守る戦いの最前線にいる」(2月の豪州議会演説)と表現するほどエスカレートする比中の南シナ海管轄権争い。中国海警局船による放水砲発射事件、レーザー照射事件、比中巡視船同士の衝突事件など、中国による圧力が近年特に強まる中で、2016年の南シナ海仲裁裁判所判断に沿った南シナ海の海洋権益を主張するため最前線に立っているのがフィリピン沿岸警備隊(PCG)だ。そんなPCGに対し日本政府は、PCG最大船となっている97メートル級巡視船(多目的船)2隻の供与を行うなど、協力を加速化させる。そんな中、在比日本国大使館に身を置きながら、日本のPCG協力を担当してきたのが、海上保安庁から出向している米沢夏希一等書記官だ。3年の任期でPCGへの貢献を高く評価され、4月の海保帰任を前にPCG職員向けの勲功章を受章した米沢氏。そんな同氏にPCGの南シナ海問題への対応や日本の協力のありかたについて話を聞いた。 (聞き手は竹下友章)
―着任したのはいつか。
2021年の3月はじめ。海上保安官による任期3年の大使館出向制度ができて、私が4代目だ。まだ引き継ぎ作業中だった同年3月末に起こったのが、ウィットサン礁(比名フリアン・フェリペ礁)に、中国のいわゆる「海上民兵船」が220隻蝟集(いしゅう)した事件だった。中国船は、その後も同じような規模で、西フィリピン海(南シナ海で比が国際法に則り権利を主張する海域)に展開し続けている。
海保からの出向とはいえ、大使館では外務事務官(一等書記官)の身分で務めている。大使館での業務は海洋安全保障関係全般。例えば、22年には97メートル級巡視船2隻の引き渡し、昨年はミンドロ島の油流出事故への対応、初の比日米海上保安機関の合同訓練、日本の首相として初となる岸田総理のPCG本庁訪問などに携わってきた。
―南シナ海問題への比の対応をどう評価する。
昨年から比政府が採用している「トランスペアレンシー戦略」は、武力紛争に発展させないよう、軍艦ではなくPCGの巡視船を前面に立てながら、西フィリピン海で何が起こっているかについての情報公開を進め、問題の透明性を高めることにより、国内世論・国際社会の双方から支持を獲得することを目的とした戦略だ。空撮映像なども含め公開し、西フィリピン海の透明化を進める比政府の取り組みによって、多くの国家が「中国の行動はここまでになっていたのか」と知り、比への支持を次々表明している。一時的にPCG職員の視力を奪ったと報告されたレーザー照射や、比船を損傷させるだけの至近距離からの放水など、中国から比への「ハラスメント」は深刻化しており、それだけセカンド・トーマス礁(比名アユギン礁)への補給任務など比側のオペレーションの負担は重くなっている。しかし、高まる国際社会・国内世論からの支持を力に、PCGは中国からの強まる圧力に屈していない。
昨年10月のPCG創設記念式典では、8月にセカンド・トーマス礁の補給活動中に中国海警船から放水を受けたPCG44メートル級巡視船(日本供与)の乗組員が表彰されていた。さらに、その44メートル級巡視船も式典のためにマニラに寄港し、マルコス大統領が自ら船に乗って職員を激励した。これは士気を上げる目的だったと思うが、同時に現政権の姿勢が表れていたと思う。
現場レベルでのPCGのアセット増強は急務だ。巡視船は自国の海域に存在しなくてはならないものであり、それなしでは何もできないからだ。しかし、比には日本のように24時間365日配備を維持できるほどの船がない。マルコス政権も、スカボロー礁へのパトロール頻度を強化するよう指示するなど、プレゼンス強化に取り組んでいる。日本は、44メートル級巡視船10隻、97メートル級巡視船2隻と巡視船の供与などのPCGへの協力を進めてきた。
西フィリピン海問題では、中国海軍が後ろに控えながら、海警船と民兵船がフォーメーションを組んでいる。特に、妨害の末の巡視船同士の衝突は衝撃的な展開だった。そういう意味で、PCGは世界の海洋安全保障の最前線に立っているといえる。その最前線に身を置き、危険と隣合わせにもかかわらず、PCG職員の士気は極めて高い。そうしたPCG職員には心から敬意が湧いてくるし、われわれは最前線の経験を学ばせてもらっている立場だと思っている。
―新たな協力分野は。
今後重要となる協力分野は、巡視船の追加供与に加えて、海洋状況把握(MDA)分野だ。海保では一定の巡視船に衛星通信システムを搭載しており、現場の状況をリアルタイムで本庁と共有し、必要があれば本庁から指示を出せる体制を整えている。この仕組みを日本の支援によりPCG巡視船等に導入することが昨年8月に決まった。導入されれば、PCGのMDA能力が飛躍的に向上することになる。これが日本によるPCGのMDA支援一丁目一番地になると思う。
―今後PCGにはどのような協力が必要か。
ハード・ソフト両面の協力の継続が必要だ。モノだけを供与する協力は他国も行っているが、供与された船をどのようにメンテナンスし、どのように運用計画を作るかということを、手取り足取りで継続して伝え、ノウハウの伝承を行うことが重要だ。こうした能力向上支援は、国際協力機構(JICA)に海上保安庁から出向し、PCG内で勤務する小野寺寛晃専門家が現在担当している。
こうした協力の一層の加速化も既に始まっている。キャパビル専門部隊である海上保安庁モバイル・コーポレーション・チームを、JICAと協力してフィリピンに派遣し、継続的な支援を続けている。97メートル級巡視船を引き渡して以降、年数回の頻度だったのが、現在は倍増以上のペースになっている。
また、22年以降、米国沿岸警備隊(USCG)と共同でPCGへの能力向上支援を始めた。日米CGによるPCG支援によって、日米間でも双方のやり方、得意分野を知り、学び合うことができるようになっている。
ソフト協力の重要部分は人材育成だ。トランスペアレンシー戦略を主唱するPCGのジェイ・タリエラ准将(西フィリピン海問題担当報道官)は、海上保安大学校・政策研究大学院大学が共同で行う海上保安政策プログラム(MSP)の第一期生として日本で修士号を取った人物。私は彼の同期生で、MSPで「同じ釜の飯を食った仲間」だ。こうしたMSPの修了生がPCGの重要ポストに就き始めており、比はMSPが最も成功した国といってもいいかもしれない。MSPのネットワークのおかげで、フィリピンでの活動は有意義なものになった。顔の見える関係は、協力を揺るぎないものにしてくれる。
また、MSP以外でも救難防災研修などのJICA事業で、毎年PCG職員を日本に招へいしている。「私はJICAで何年に日本に行っていたんですよ」という職員がPCG内にたくさん育っている。これも長年にわたる先駆者達の努力のおかげだ。
―日本の協力の特徴は。
長い協力の歴史と信頼関係に基づいた比に寄り添う協力というのが日本の特徴だと思う。JICAに出向している小野寺専門家はPCG本庁にオフィスを持っているが、PCGに出勤する外国の駐在官は他にいない。また、現場への入り込みも深い。それが表れたのが、昨年2月末の貨物船沈没事故に伴い発生したミンドロ島沖の油流出事故への緊急支援だ。
忘れもしない去年のマニラ日本人会主催盆踊り大会の日、越川前大使から電話がかかってきた。「ミンドロ島における油事故に国際緊急援助隊(JDR)を派遣するよう調整せよ」との指示だった。その時、屋台に並んでいるところだったが、並びながら方々に電話・メールにより調整した。自分が起案者であるため、最後まで自分も参加するということで進め、大使館もそれを認めてくれた。本事故のために最初にフィリピンに駆けつけた国が日本となった。
日本は二瓶大輔在比大公使が団長、私が団長補佐として、海上保安庁機動防除隊およびJICAとともに現場に赴いた。他国にはないコミットメントの強さだった。
日常的にPCGと付き合いのある海保アタッシェが現場に行くことは、相手方とのコミュニケーションで大きな違いを生む。本国から来たPCGにとってよく知らない人だけでなく、駐在する私が同行することで、PCGとのやり取りもスムーズになり、船に乗せてもらう調整も容易になる。
われわれは、日本から持ってきた資器材を供与するだけでなく、PCG職員と一緒に現場を視察し、同じ船に乗り、同じ油にまみれて、資器材の使い方や油回収のノウハウを共有した。例えば、油処理剤の混合比について、PCGと海保のやり方を実際に比較して効果を実演するなど、本当にもう現場レベルの協力だった。こういった一緒に汗をかく協力というのは、他国にはない。PCGが比運輸省傘下に入った1998年以降、30年近い協力の歴史に裏打ちされた、比日の強い信頼関係の証だと思う。
―今月、帰任を前にPCG職員向けの勲功章を受章している。
日本ではとても考えられないが、ガバンPCG長官からPCG職員対象の褒章をいただけた。一緒に働く仲間として認めてもらえたと感じて本当にうれしかった。97メートル級巡視船の引き渡しを含め様々な協力に携わり、現場でも共に汗をかいて思い入れも強かっただけに、3年務めてきて本当に良かったと思った。比での学びを本庁に持ち帰り、今後も比日の海上保安協力に貢献できればと思う。
◇
よねざわ・なつき 平成14年海上保安大学校入学。大型巡視船首席航海士、巡視艇船長および海上保安庁本庁勤務(総務部、警備救難部)を経て、令和3年3月外務省出向。令和3年3月から在フィリピン日本国大使館外務事務官(一等書記官)として勤務。


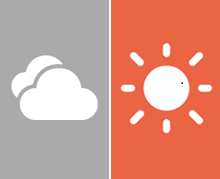


 English
English