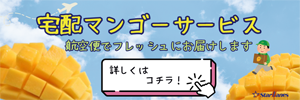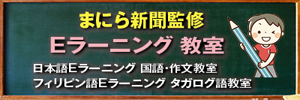第2回 ・ 「救えた命があったはず」と自身の無力と町、政府の無策を責める気持ち消えず

「もっと多くの命を救えたはず」。被災から約1カ月後の12月初旬、パポース・ランタホさん(49)は自問を続けていた。バランガイ(最小行政区)の議長として、行政機構の末端に携わりながら、幼なじみや隣人らを救えなかった自身の無力と町、政府の無策を責めたい気持ちは、なかなか消えない。
古里、ビサヤ地方レイテ州パロ町サンフアキン・バランガイは、レイテ湾沿いの一角にある。隣接する州都タクロバン市と同様、高さ5メートルを超える高潮に飲まれ、同町全体の死者・行方不明者約1381人の2割強に相当する約300人が犠牲になった。
被災初日の11月8日午後。がれきの山を乗り越えながら、数キロ離れた町役場にたどり着いた。町内会的バランガイのレベルでは何ともならない状況下、町の支援を求めるためだった。しかし、壊滅的被害を受けた町役場に町長らの姿はなく、居合わせた職員からは「重機を動かす燃料がない。分けてほしい」と逆に助けを求められた。
手ぶらで戻ったバランガイで待っていたのは、水・食料を求める生存者だった。「水をくれ」と迫られても、手元には何もない。飢えと渇きで絶望のふちに立たされた当時を「いつまで耐えればいいのか分からない。そんな状態で、私たちは4日間、飢え続けた。被災5日後になって、海外の民間団体からコメや水が届いた。腹が膨れるようにとおかゆにして分け合った」と振り返る議長。
そして、「救ってくれたのは海外の民間団体だった。われわれの政府は……」と続けようとしたところで感極まり、言葉が途切れた。やり場のない憤りが涙になって、ほおを流れた。
いつ終わるとも知れない遺体収容と行方不明者の捜索活動も、生き残ったバランガイ関係者と住民有志で行わざるを得なかった。がれきの山に埋まったり、木に引っ掛かった遺体を人力で収容した。がれきの向こう側から生存者の声が聞こえることもあったが、足場がなく助けに行けない。その上空を、国軍ヘリが時折舞った。
被災5日目には、死後間もない男性の遺体を収容した。負傷して動けなくなり、がれきの山で息を引き取ったとみられた。「遺体を何十も収容していると、死後何日ぐらいたっているか分かるようになった。あの男性の遺体はまだ新しかった。恐らく、被災から4日間程度は生きていたと思う」と議長。それだけに、あの時、頭上を飛び去ったヘリのことが「助けてくれなかった」と忘れられない。
300人に上る犠牲者の多くは、バランガイ中心部にあるカトリック教会前広場に運ばれた。公共墓地と墓地へ通じる道ががれきに埋まり、使えなかったためだった。埋葬は「せめて身元確認を」と可能な限り引き延ばしたが、被災3日後には傷みが激しくなり、神父の了承を取った上で広場での集団埋葬を始めた。
「埋める場所がなく、仕方なかった。教会の敷地内に埋葬されることで、救われるよう願っている。できるだけ早い時期に(広場一角を)慰霊公園として整備し、犠牲者の名前を刻んだ慰霊碑を建てたい」。そう話すと、ランタホさんは埋葬者の名前や収容場所を書き込んだ帳面にじっと目を落とした。12月初旬までに埋葬された210体のうち、身元が分かったのは175人だけ。残り35体は、性別と推定年齢だけが記されていた。(酒井善彦、続く)
(2014.1.3)


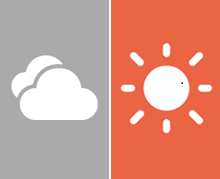


 English
English