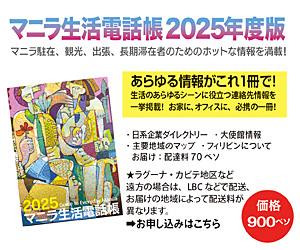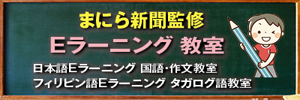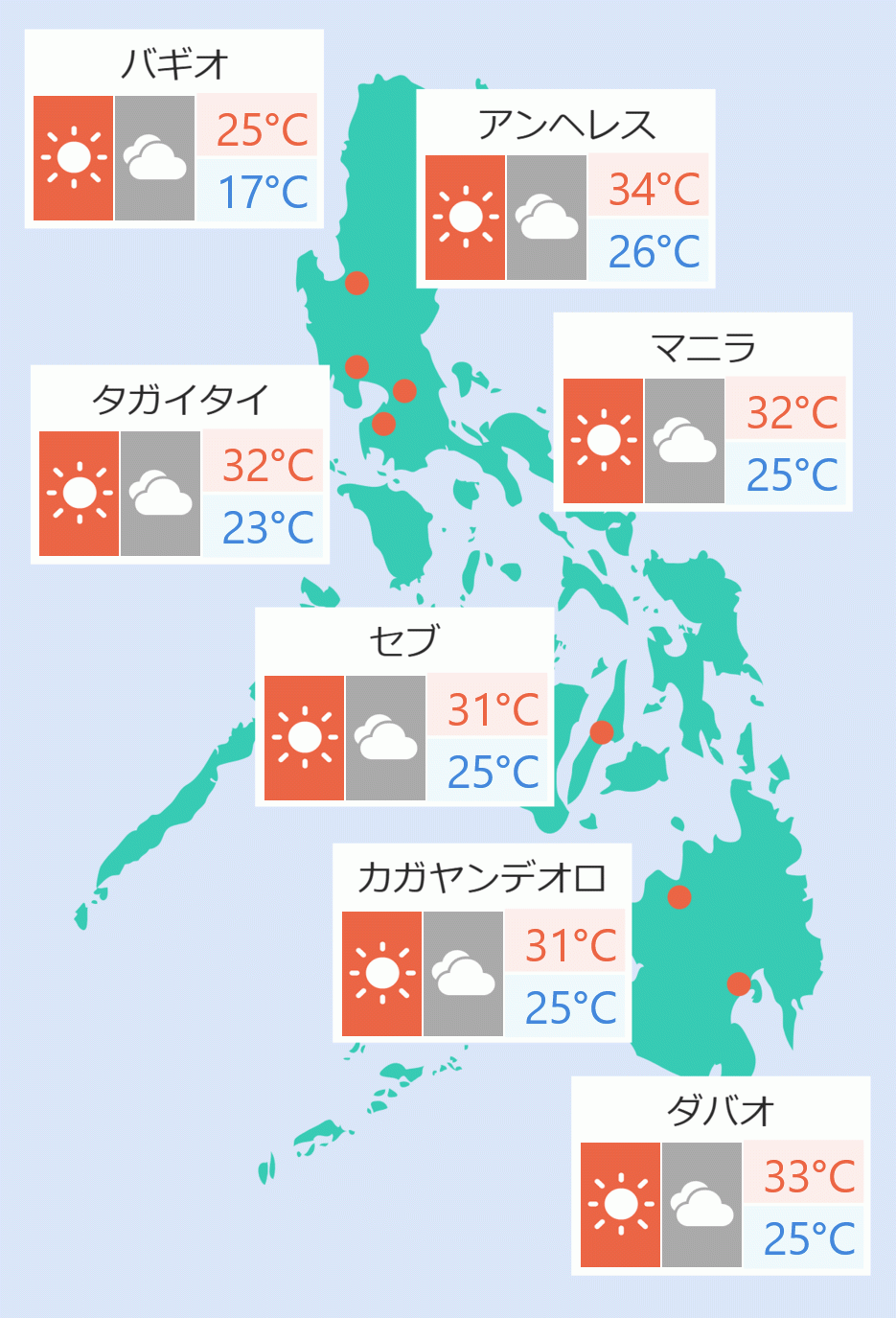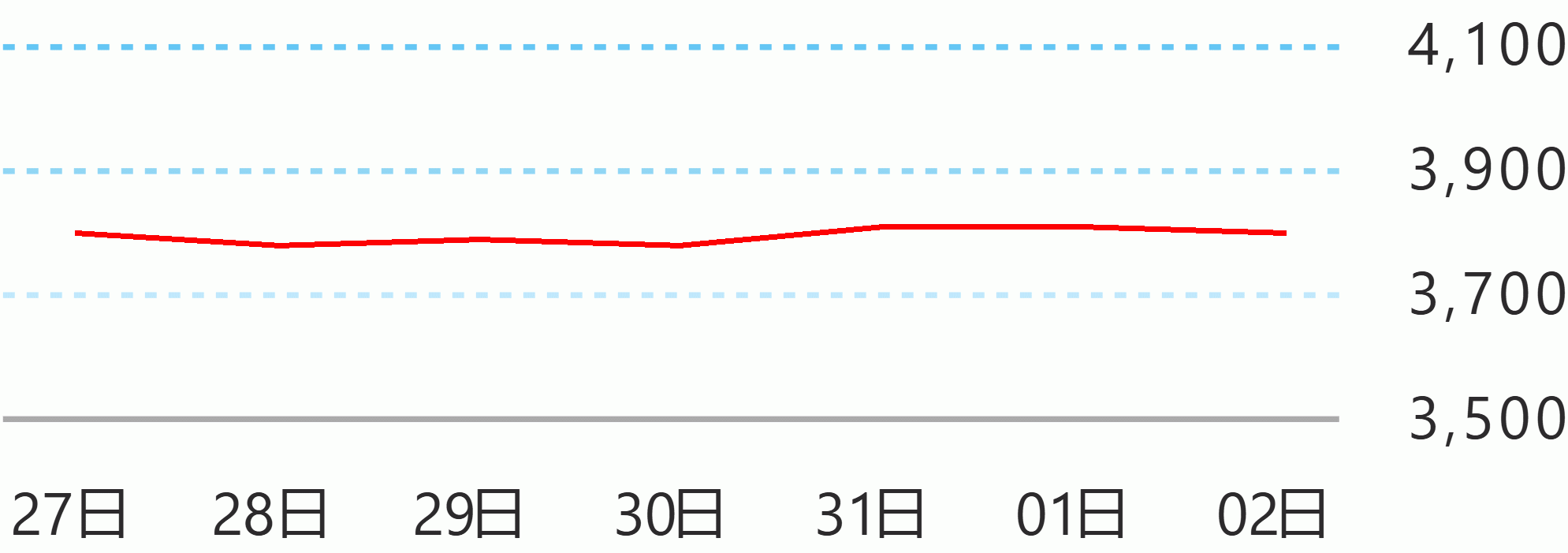人気漫画「東京リベンジャーズ」の実写化シリーズなどに出演する若手俳優・堀家一希(ほりけ・かずき)さん(26)が、初の主演作品「世界は僕らに気づかない」(2023年、飯塚花笑監督)が2月からの日本映画祭(国際交流基金)の目玉の一つとして上映されるのに合わせ、舞台あいさつのためフィリピンを訪問した。
同作品で先月、第37回高崎映画祭「最優秀新進俳優賞」の受賞が決定するなど、いま波に乗る堀家さん。同作品では、ゲイで在日フィリピン人2世、さらに母子家庭に育った高校生という、多重のマイノリティーの主人公を迫力の演技で演じきった。「あえて悪役に描いた」(飯塚監督)という主人公・純悟を熱演したことで、本作の英題は「Angry Son(怒る息子)」となった。そんな堀家さんが、上映を前にまにら新聞の単独インタビューに応じた。(聞き手は竹下友章)
―俳優になったのはいつから。
いつから俳優になれたかというのは難しくて、高校1年から3年間、実家のある岡山から大阪まで毎週演技のレッスンに通っていた。片道2時間半で2400円。交通費はずっと貯めていたお小遣いから出していた。クラスにこういう生徒は他におらず、当時は僕の方も皆に言うのはなんだか恥ずかしく黙っていた。必要最低限の人にだけ伝えて、友達には黙っていた。
―多重マイノリティーという難しい役作りをどう行ったか。
コロナ禍で撮影が1年延期されたこともあり、その期間を使って飯塚監督に自分のことを話して、役作りに生かせる部分を探った。
監督と話していたのが、根本は「母と子との物語」だということ。まずそこを作ろうと。自分と両親との関係を監督にいっぱい聞いてもらって映画に使える部分を探った。例えば僕の父は仕事人間で、ほとんど家にいない。運動会などの行事に、父に来てほしかったのに来てくれなかったりといった思い出をたどって監督に共有した。
また、いまになって父のことをとやかくいうのも良くないと思うが、当時の僕としては、父の自分に対する接し方に、一種の「精神的暴力」のようなものを感じていた。肉体的なものではないのだが、「俺が飯を食えって言ったら食え」というように、有無を言わせない、強要するような圧を、子どものころの自分は感じていた。反抗することさえ怖くて、言うことを聞くしかなかった。本当はお腹がいっぱいで今食べたくないのに「嫌だ」と言ったら怒られる。そういう子どもの頃の思い出を見つめ直して、監督に話すと、監督も「そこは(映画に)使えるね」と教えてくれた。
そうした話し合いを通じて、監督にも脚本を僕に寄せて調整していただけた。劇中のとあるシーンで、いつもは比人母のレイラ(ガウ)と怒鳴り合っている主人公・純悟が、「辛かったとき、そばにいてほしかった、助けてほしかった」と涙する場面がある。これは、自分の話を脚本に反映してもらったのかなと思っている。このシーンには監督も自分も思い入れが強く、取り直しを行って納得行く演技をした。
―ゲイの役になりきるために何をしたか。
撮影が始まる直前に、恋人・優助役の篠原雅史さんとデートをしてほしいと監督に頼まれた。イオンでのデートで、監督は僕らの邪魔にならないように遠巻きに見ているだけ。ただ2人で、アドリブでデートした。最初は2人で関係性を探り合いながらだったが、あるタイミングで手をつないだ。その時、今でもはっきり覚えているが、通りすがりの男性2人に笑われた。通り過ぎたら後ろからも笑い声がして。今でもその情景を思い起こして話すと、胸が痛む。
あと、プリクラを撮ろうとすると、「男二人ではダメ」という表示があったりした。こういうことは、男同士でデートするまで気づけなかった。この経験から芽生えたものが、糧となった。
―人を愛することにセクシュアリティーは関係ないと思うが、これまでの自身の恋愛経験も生かしたか。
それもある。以前取材でLGBTQ(性的少数者)関連の質問を受けたときは、LGBTQの当事者を傷つける表現になって世に出てしまわないか心配であまり踏み込めなかった。でも今、あえて言うなら、愛する相手が男なのか女なのかというだけの話だと最初から思っていた。難しいことではない。
例えば、もし、異性カップルがおかしいという世界にいたらと想像すると、こっち(異性愛者側)がおかしいと扱われることになる。そうしたことを想像すると、相手を愛するという根本はセクシュアリティー関係なく全く同じだと思う。ただ、少数者は世間から白い目で見られるから、色々な辛さや屈折を抱えることになる。
―初の主役を務め、俳優としての成長を実感したか。
実は手応えはあるが、「はいそうです」と言いたくないという気持ちが強い。飯塚監督は監督だけでなく、演技の勉強をしてきた人だから、監督の理解に助けられた。ただ、普通のテレビドラマや映画の監督は、演技メソッド、演技の文法というものを認知していない方が多い。監督と2人でできたことを、これからは1人でやらないといけない。今は、成長の充実より、そういう緊張感が強い。





 English
English