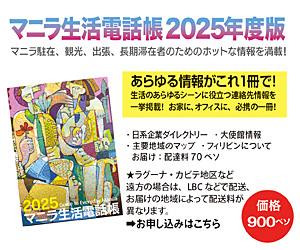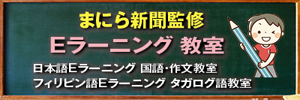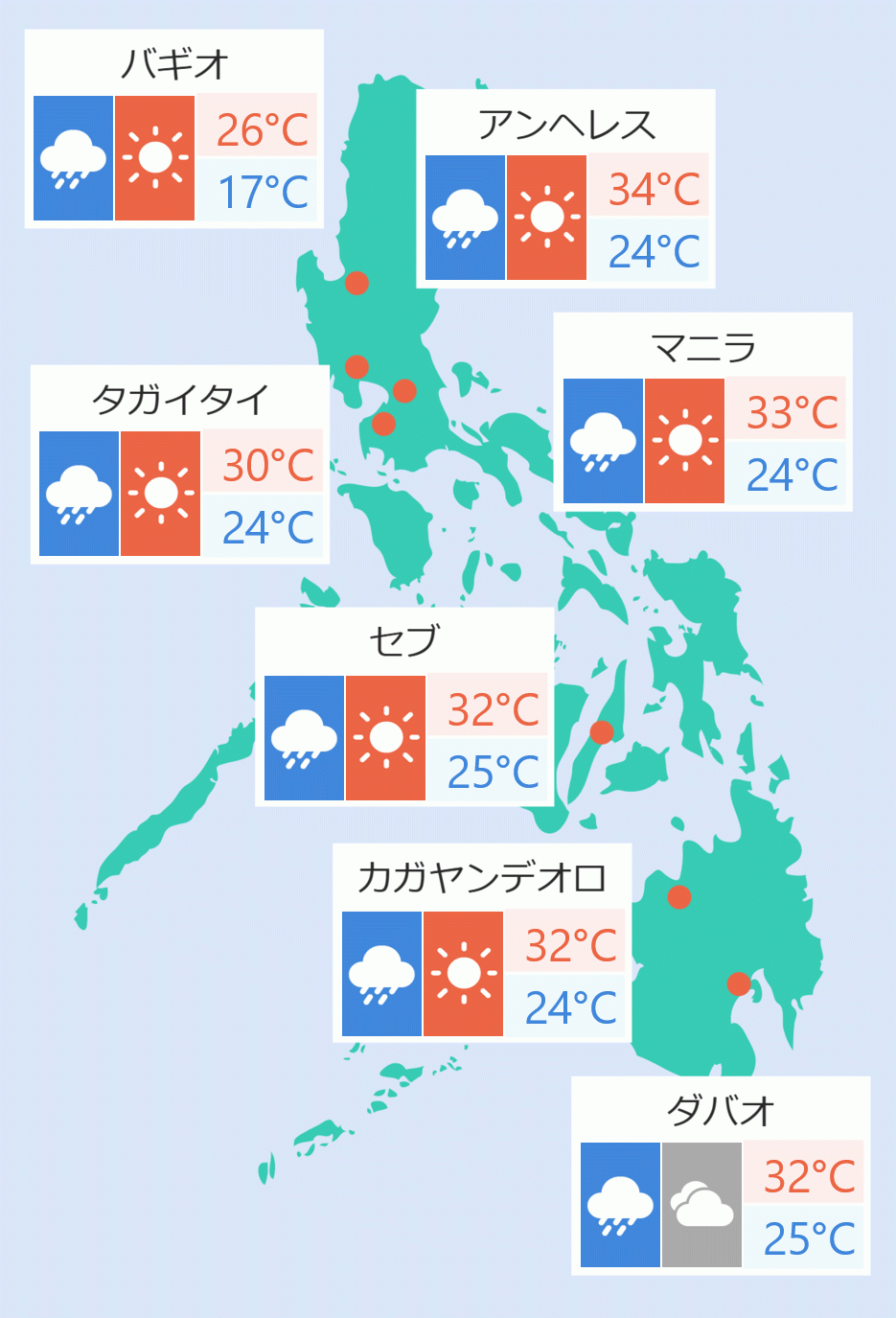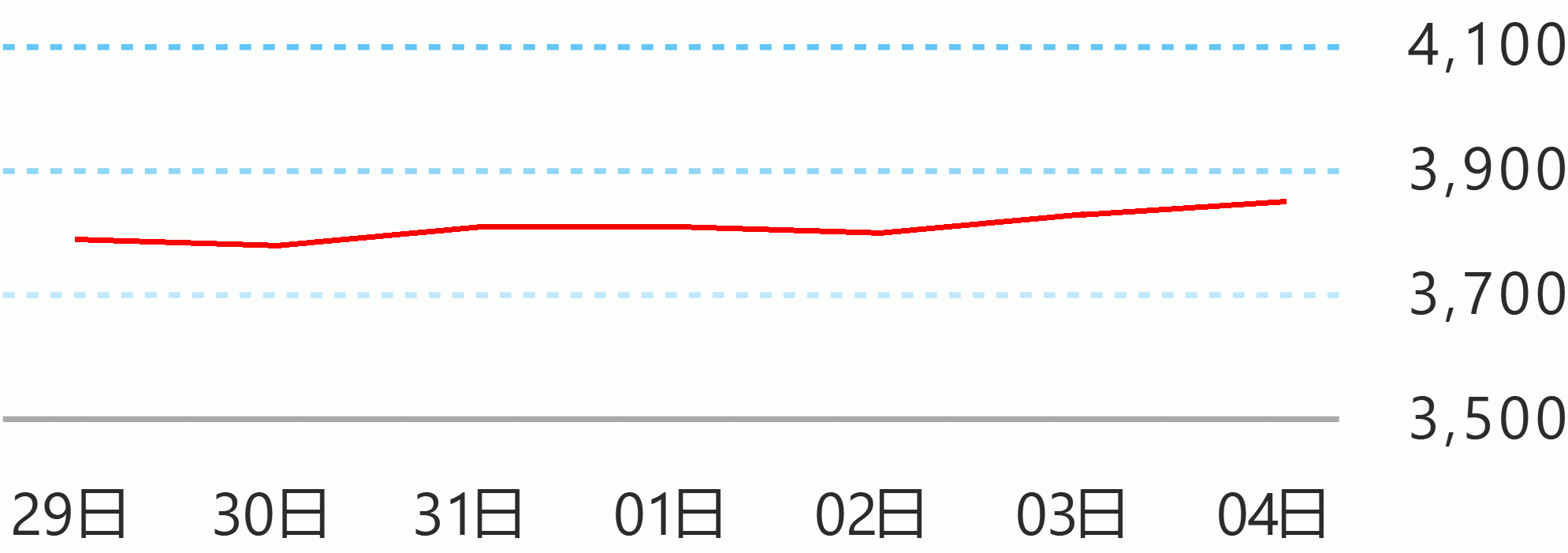長年、撮影監督として活動しながら、比でNPO法人や自身の劇場を作り、芸能プロダクション経営も行うなど実業家としての顔も持つ瓜生敏彦氏。その監督デビュー作である長編ドキュメンタリー映画「YIELD」(2018年)のファイナルエディション(最終版)「子どもの瞳をみつめて」が、3月15日に東京神田のアテネ・フランセ文化センターで、29日には新宿ケイズシネマにて日本公開が開始された。瓜生氏に同作品に込めた思いなどを聞いた。(聞き手は岡田薫)
―フィリピンとの関わりは
1995年まではドキュメンタリーを撮影し、社会の悲惨さや矛盾を伝えてきた。その間、多くの活動家や政治家とかを見て、訴えることを信じていた。それが1995年の11月27日にスモーキーマウンテンで警察官に撃たれたことで変化が出てきた。いわば一度死んでしまったようなもの。生きているうちに何人か助けられるではないかと考えるようになり、2001年に「クリエイティブ・イメージ・ファウンデーション」を設立。子どもたちのために無料の学校を作った。
―なぜドキュメンタリー
ドキュメンタリーというと、いわゆる社会問題の追及が一般的で、文字でもできる分野だ。しかし、いくら饒舌に話しても言葉では伝えられない、映像は映像で表現したいという思いが若い時からあった。とてもいい絵が撮れても編集でカットされたり、映像で伝えられるのにナレーションを被せたり。カメラマンとディレクター、編集との間の確執とでもいうのか、そんな欲求不満を抱えてきた。
ドラマには設計図があるが、ドキュメンタリーはジャズに近い。何が起きるか分からない中で、直感でカメラを左右に振っていく。昔からナレーションやインタビューなしで伝える作品を作りたいと思っていた。
―比での手応えは
「YIELD」が2018年にフィリピン映画芸術科学アカデミー賞をもらった際、審査員のレベルが高くて感動した。
審査委員長がヘビースモーカーで、授賞式会場の駐車場の隅で劇映画10本中の1本に彼が推してくれたことを知った。他の審査員の反対にも「この映画には他の映画にはないパワーがある」と。理解してもらえて嬉しかった。
―タイトルはどう決めた
ファイナルエディションでも、あまり変わってはいない。YIELDは「フィロソフィカルな作品にしたい」と言っていたビクター・タガロ(共同監督)が付けた題で、日本語タイトルは配給会社に付けてもらった。「子どもの瞳の奥を見つめて」との案も出したが、これに決まった。
―映画の作業期間は
撮影に8年。編集に数年かかった。何十時間も撮った内容を編集していくのだけれど、タガロがまとめられず、比で一番有名な若手の女性エディターに、半年ぐらい編集に携わってもらった。彼女はフィリピン大出身で、どちらかというと西欧の価値観に仕上がってしまい、そうした「価値観」を崩していくだけでも精いっぱいのようだった。結局タガロに「お前しかいない」と。彼はよく辞めずに、ぼくの意思を理解して残ってくれたと思う。
―映画の見方は
ぼくの家は専業農家だったから親父やおふくろに付いてよく畑に行った。畑で遊んだりもするし、農家であれば当たり前に麦踏みをして、父親の後ろ姿を見て育った。行きたくなければ畑に行かなければいい。「強制労働」や「児童労働」といったネガティブなイメージとは違う。
つまり、自身の価値観や知識、生き方全部がかかわってくる。100人が見て100人が違った感じ方をすれば良い。金持ちでも貧乏人でも、どのような職業であっても、子どもの時分からの体験と、現在の生活、思想をもって子どもたちの映像と比較しながら感じてもらう。ドキュメンタリーというより劇映画を見る感覚かもしれない。
タルコフスキーが好きだったから。それで、しかも素人の俳優でタルコフスキー的な世界、つまりヨーロッパやソ連から亡命した監督による表現世界をドキュメンタリーでもやってみたかった。
―見る人に望むこと
日本の映画監督に見てもらった際、ワンカットごとに「これはなんなのか」と質問してくる。例えば「貧しいのになぜテレビや冷蔵庫があるのか」というような。先入観なく見ないと細かいところに入り込んでしまう。
あと日本のニュースを見ると、子どもを殺したなど家族間の殺人や、自殺者が年に3万〜4万人、生きる価値が見いだせず死を選ぶ人もいる。そういう人たちにも見てほしい。幸福はお金ではない。1ペソを持っていなくても、家族や子ども、そういった幸せの価値観は大切だと考えている。ある財閥の息子にこの映画を見せた際、40歳近い大人が泣いていた。「ミスター瓜生、劇場でハンカチかティッシュを配らないとだめだよ」と。金持ちの息子にもハートがあったと分かった。
× × ×
TOSHIHIKO URYU 1958年、千葉県三里塚に生まれる。映画専門学校を中退後、実家が三里塚闘争を撮影する小川伸介監督らの拠点だったことから小川プロに所属。小林正樹監督「東京裁判」の撮影助手を経て、撮影監督として多数の映画やテレビ番組の製作に参加。1995年にスモーキーマウンテンで、NHKドキュメンタリー「フィリピン、スモーキーマウンテンが消える日」の撮影中、警察から銃撃され瀕死の重症を負う。四ノ宮浩監督の3部作「忘れられた子供たち/スカベンジャー」(1995年)、「神の子たち」(2001年)に撮影参加。14年にはマカティ市に劇場を建設し、定期的に子どもたちに歌やダンス、楽器演奏等のワークショップを行うなどしている


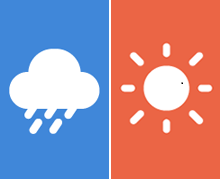


 English
English