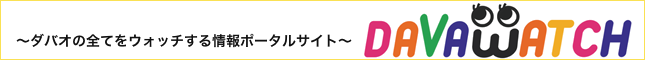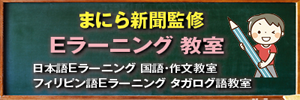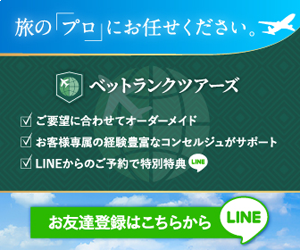ハロハロ
日本へ一時帰国するたびに、気になる単行本や雑誌を2、3冊買ってくる。今回はノンフィクション作家沢木耕太郎の『キャパの十字架』、文芸誌「すばる」(2月号)など3冊。「すばる」に掲載された友人の作家辺見庸の最新小説「青い花」(50ページ)は改行なしで、3・11大震災後の暗い心象風景を延々と綴っており、その難解さに往生した。沢木耕太郎の『キャパの十字架』は傑作である。2月に初版が出てから、売れ行きがすこぶる好調なのも納得できる。
◇
ロバート・キャパがスペイン内戦初期の1936年9月に撮影したとされる「崩れ落ちる兵士」は翌37年7月に写真誌「ライフ」に掲載されると、大反響を呼び、ピカソの「ゲルニカ」と並ぶスペイン内戦のイコンとなった。ところが、共和国軍の民兵が銃弾を受け、後ろにのけぞり倒れようとする瞬間をとったとされるこの写真については、贋作説、やらせ説が繰り返し蒸し返されてきた。
◇
沢木本の一番のすごさは何だろうか。日本、スペイン、フランス、米国で徹底した取材を重ね、写真の撮影現場を特定した上で、撮影者が実はキャパではなく、同行取材していた恋人のゲルダ・タローであったと立証している点にある、と思う。アンダルシア地方エスペホ町に3度足を運び、キャパとゲルダが使用していた2種類の古いドイツ製カメラで現場写真を撮り、その詳細な比較から、ゲルダのカメラでしか「崩れ落ちる兵士」は撮れないと証明した。兵士は実戦で撃たれたのではなく、訓練中に誤って転んだだけ、との結論も出している。つまり、世紀の傑作は偶然の産物だったというのだ。その取材へのこだわりに、頭が下がる。(竹)