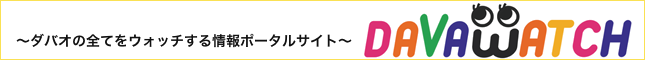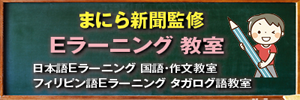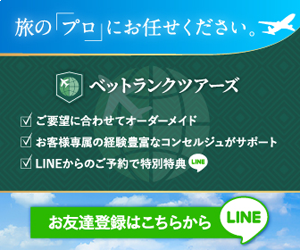戦後60年 慰霊碑巡礼第2部レイテ編
そして、誰もいなくなる?

州都タクロバン市の南は、旧日本軍飛行場跡があるブラウエン町だ。この地にある慰霊所の管理人は日本と手紙のやりとりを続けて来た。しかし、元兵士や遺族の高齢化とともに届く手紙の数も年々減っている。
地元の住民は飛行場跡を「ランディング(着陸地)」と呼んでいる。田と草むらが広がる平地が今も開けている。あぜ道を歩いていた少年二人に日本軍慰霊所の場所を聞くと、近くの小さな集落に連れて行った。
集落の中心には人だかりがあり、のぞくと豚を解体していた。すぐ横のニッパハウスの奥が祭壇になっている。石造の釈迦立像が一体。背後に第二六師団と米軍第十一空挺師団と書かれた彼我両軍戦没者を慰霊する木製の十字架二本が立っている。その両脇には計百十一本の卒塔婆が横木に打ち付けられ、柵のようだ。
慰霊所の管理人を名乗る女性が現れた。バランガイ職員を務めるエルリンダ・アマットさん(50)は父親から引き継いだ二代目だという。
慰霊の祭壇は一九六〇年代後半、第二六師団戦没者慰霊所として造られた。以降、七〇年、八〇年代には師団所属の旧将兵や戦没者遺族が足繁く訪れた。帰国すると、アマット一家に現金小切手や古着、紙などを送ってきたという。
その慰霊訪問者の数は九〇年代に入るとめっきり減った。戦後五十周年だった一九九五年だけが例外で、今はほとんどだれも来ない。
「ただ、物やお金だけじゃないんです。手紙の交換が始まり、ずっと続いたんです」とエルリンダさん。家にいったん戻ると手紙の束を持ってきた。
慰霊訪問の後、お世話になったという礼状一通だけの人が多いが、その中の数人とは「クリスマスカードや年賀状という形で定期的な手紙の交換が始まりました」と、エルリンダさんは振り返った。
文面を見ると、「元気ですか」「慰霊所を管理して頂き、ありがとうございます」という趣旨の英語が短く書かれている。単純な文面でも、手紙を出すことで訪問の代わりにしようとする心の動きがこもっている。
しかし、今は大分減った。「皆さん高齢なので、突然手紙が来なくなりますよ」。
残された遺族から逝去の知らせはほとんどない。「手紙が来なくなるのは寂しいですよ。あの人も亡くなったのかと思うと・・」エルリンダさんは悲しそうな顔になった。
高齢化は、元日本兵や遺族ばかりではない。慰霊の記念構造物を守る管理人も年老いていく。
ビリヤバ町バリテ・バランガイ(最小行政区)の小高い丘に立つ白い塔。一九九五年に元抗日ゲリラの比人と日本軍帰還兵の友情で建立されたといわれる日比合同戦没者慰霊塔だ。
慰霊塔入口の扉に錠が下りていて立ち往生していると、麦わら帽子の老女が歩いてきた。慰霊碑の管理人、ロレタ・バレンテ(67)さんだった。
「近所に住む元抗日ゲリラに頼まれて」管理人になった。管理人手当は昔は月千ペソだったが、今は八百ペソだという。
塔が立つ広場までひどく急な階段を登ると、木造の小屋があった。壁に写真や日本語の新聞記事の切り抜きが六枚の額にビニールをかけて掛かっている。慰霊塔建立の縁起を教える資料だった。ビリヤバ町の簡易水道事業の経緯も写真付きで説明してあった。慰霊塔と一緒に水場の建設も支援したのだろう。
小屋の横に蛇口の付いた水道栓があった。「昨年七月ごろから、水が出ないんです」とロレタさん。「付近の集落で盗水してしまうからだ」と愚痴った。
「水がないから、敷地内の草花の手入れは大変。雨も降らないし。階段を上がるだけでも大変なのに水を持って上がる時は重労働です」とこぼし続ける。
「八百ペソでは安すぎる」と言う老齢のロレタさんがやめたら、管理人の代わりはいなくなりそうだ。 (藤岡順吉、おわり)