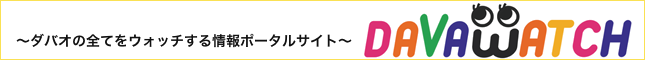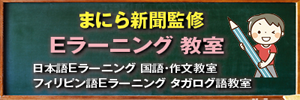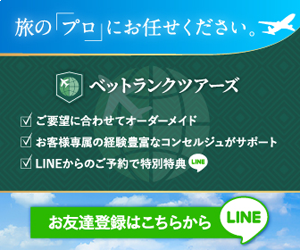戦後60年 慰霊碑巡礼第2部レイテ編
沖縄女性、遺骨収集の半生

沖縄からレイテ島へ。太平洋戦争の最激戦地に生まれ、最激戦地に嫁いだ秀子・仲村・オカンポさん(74)。自分も戦争の被害者なのに、侵略された比国民のうらみを一身に浴びた。
戦後、米国占領下の沖縄は貧しかった。秀子さんは米海軍基地で働いていて、トラック運転手をしていたセリソ・オカンポさんと恋に落ちて、結婚した。一九五一年に夫の郷里、北レイテ州ブラウエン町にやってきてから五十四年になる。
沖縄はレイテ島と同様、ひどい戦火の洗礼を受けた。しかし、秀子さんの生まれ故郷、沖縄本島北部の大宜味村は南部・那覇周辺のような苛烈な戦いを経験しなかった。秀子さんは村に米兵が一度現れたことを記憶しているだけだ。
それだけに日本軍がフィリピンに侵攻し、レイテ島が激戦地だったことを知らずに育った。実は、太平洋戦争中、ブラウエン町には日本軍の飛行場があり、多くの日本人将兵が駐留していた。米軍が上陸すると、日本軍はこの町から山奥へと敗走していった。
「こちらに来たばかりのころは帰りたくて、帰りたくて。五十年も住むことになるとは思ってもいませんでした」。秀子さんは人生を振り返る。
戦後五、六年たってもブラウエン町には反日感情が強く残っていた。まだ講和条約も結ばれていないころだ。秀子さんが引っ越してきたばかりのこと。「外を歩くと厳しい形相をした人々が詰め寄ってきた」という。
暴力を振るわれることはなかったが、激しい口調でののしられた。夫の通訳で「お前は日本人だな。家族を日本人に殺されたんだぞ。どうしてくれる!」と言われたとわかった。一度や二度ではない。
若妻の秀子さんにとって寝耳に水だった。夫の通訳がぴんとのみ込めない。敗戦国からはるばる、夫に連れられて南の島に来ただけなのに。「日本の軍隊がこんな所で悪いことをしたとは想像もつかなかった」と言う。住民の怒りが伝わり、胸が痛んだ。
セリソさんからブラウエン町で戦争中、何があったのかを聞かされて、気が転倒するほど驚いた。日本軍が侵攻して来ると、住民たちは山奥へ逃げ込まざるを得なかったという。まるで沖縄と一緒だった。来たことを後悔した。言葉はわからず、頼るは夫だけで、ひしひしと孤独を感じた。
日本人であることへの「世間」の風当たりが怖く、秀子さんの心はすっかり萎縮してしまった。来比してから四年の間、まともに外出せず、家に閉じこもった。
しかし、帰ろうにも帰れない。憂鬱な時間は続いたが、夫を介して少しずつ知り合いができ、友人付き合いも広がってブラウエンの住人となっていった。厳しい仕打ちをされた半面、あったかな気持ちで接してくれる隣人が支えになってくれたという。どうにかフィリピンの主婦になった。
一九七一年、厚生省(現厚生労働省)が秀子さんにレイテ島での遺骨収集を依頼した。レイテ島に住む数少ない日本人だったからだ。秀子さんは一生懸命、戦闘の情報を集め、悲劇の同胞たちの形見を探した。秀子さんが関係した収拾作業で集めた遺骨の数は約四万体に及ぶという。
遺骨収拾を始めたことで日本とのつながりがよみがえった。慰霊碑が次々に建立され、訪問者が増えた。慰霊碑訪問者のガイドの仕事を始めた。
慰霊事業団体とのつながりが縁で、来比二十五年後、の一九七六年、初めて日本に帰った。東京など日本各地を案内された後、ふるさと沖縄に帰った。
帰りたくてしょうがなかった故国だったが、旅行の間にレイテに帰る日が待ち遠しくなっている自分を見つけた。毎日、カレンダーの日付を数えていたのだ。「いつの間にか、フィリピンの方が心が落ち着くようになったんですね」。三十七年間、日本からの旅行者のガイドを続けてきたが、足が悪くなったため昨年七月、引退した。
九六年に夫が他界して、まもなく十年。夫が営んでいた理髪店と小さな雑貨店を引き継いでいる。二人の娘は日本に渡り、息子が近くに住む。(藤岡順吉、続く)