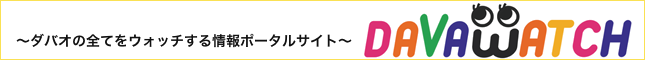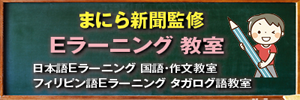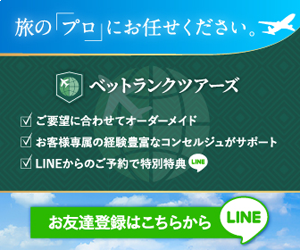移民1世紀 第3部・新2世の闇と未来
「辱められない比人に」

「日本人にはどうして心がない。子供もいるのに。死んだ本人もかわいそうでしょう?」。一年前の深夜。エドサ通り沿いにある葬儀場。三日前に急死したある日本人男性(50)の内縁の妻、リサさん(24)‖仮名、ルソン島ヌエバエシハ州カバナトゥアン市出身‖は低く、強い声でそう言うと、親類の胸で眠り続ける長男タロウ君(4)‖仮名‖に視線を落とした。
一週間は続くフィリピン式の葬儀。最後の別れを惜しむように、毎日二十時間近く、ひつぎの横で過ごしてきたリサさん。ほとんど寝ていないのか、涙が枯れ果てたのか、大きな目は真っ赤に充血していた。
男性の死は突然やって来た。ヌエバエシハ州の実家に帰っていたリサさんの携帯電話に男性から文字メールが一つ、入った。「おはよう。いってきます」。「いつもは『グッドモーニング』だけなのに・・」。ちょっと変な予感がした。すぐ電話をしようとしたが、携帯カードの度数が不足していた。
三十分後、死を伝える電話が携帯電話に入った。心筋梗塞(こうそく)だった。
タロウ君を連れ、首都圏の自宅へ駆け付けると、男性の務める日系企業の比人従業員が入口で待っていた。
「男性の遺体は見せられない。日本から本当の家族が来るから」と従業員。さらに「自宅にある物はすべて会社の所有物。何も持ち出せない。日本人の本妻が部屋を見たいと言っているから、近くのアパートへ移ってほしい」とも言われた。
「比人なら夫を亡くしたばかりの女にこんなことは言わない。会社の日本人が言わせている」。直感したリサさんは言い返した。「ランガム・マン・アコ・サ・ティギン・ニンニョ。マサキット・ディン・パグ・クマガット(あなたたちにとって私はアリみたいなものかもしれない。だけどかまれると痛いわよ)。侮辱するなら弁護士を雇って死ぬまで闘ってやる。そう(会社の)日本人たちに言いなさい」。結局、火葬までの六日間、自宅と葬儀場を毎日往復し続けた。
遺体がだびに付される日。リサさんはミサの直前に思いもよらない言葉を耳にする。日本からやってきた男性の娘(13)が母親(本妻)にかけた一言。「あの人たち(リサさんとタロウ君)はいいよね。お父さんと長く一緒にいられて・・」。会社の仕打ちに怒りの収めようもなかったリサさんだったが、この時ばかりは涙が止まらなかった。
葬儀が終わり、タロウ君と実家へ帰ろうとした時、比人従業員が分厚い封筒と男性の死亡証明書のコピーを差し出した。「遺体は見せられない」と言った、あの従業員だった。会社の比人従業員約八十人から寄せられた、約一万四千ペソ分の小額紙幣がぎっしり詰まっていた。「悪く思わないで下さい。死亡証明書を渡したことは(会社の)日本人には黙っていてほしい」と従業員。リサさんは、正妻がすべて持ち帰った男性の遺灰の代わりに、封筒と一枚のコピーを握りしめ生まれ故郷へ帰っていった。
リサさんと男性の人生が重なった歳月は約八年間。エンターテイナーとして日本へ初めて出稼ぎに行った一九九四年五月から二〇〇二年八月まで。男性の比赴任を契機に始まった同居生活は六年近くに及び、二十歳で一人息子のタロウ君を生んだ。
十五・二十三歳という女性として輝きを増す時を男性とともに刻んだリサさんは言う。「(軍人だった)父が目の前で射殺された十一歳の時から今まで、いろいろなことがありすぎた。まだ二十四歳なのにおばあさんになったような気持ち。だけど、タロウは人に辱められることのない立派な比人に私が育てて見せる」
葬儀から半年が過ぎようとしていた二〇〇三年二月。彼女は再び日本の出稼ぎ先へ向かった。(つづく)