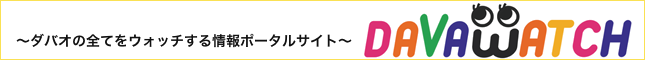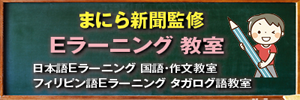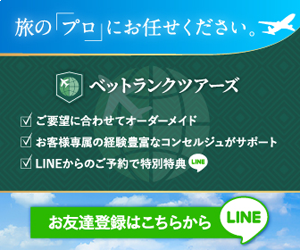移民1世紀 第2部・ダバオで生きる
残留孤児「私は一体誰」

ダバオ市内に住むその「日本人女性」は自分の本名、正確な年齢を知らない。育ての親のフィリピン人が戦後付けてくれた名前は「レテシア・アギラ」という。年齢は拾われた時に七、八歳ぐらいに見えたことから起算して「六十六歳」にしている。髪の毛は既に大半が白く、六十歳は恐らく超えているだろう。
名、年は思い出せないが、母が日本人だったことは覚えている。そして、その母の顔と妹二人を失った場面も鮮明に覚えている。
「ある日、母が『戦争は終わった。逃げなければ』と言って私と姉、妹を連れて家を飛び出しました。川の手前で(少数民族の)バゴボの男たちに出会い、母はボロ(長刀)で首を切られて倒れました。私たち姉妹三人も木で頭をたたかれ気を失いました。数日間、気を失っていたのでしょうか。目を覚ました時、母の遺体にはもうウジ虫がわいていました。姉妹の生死は今も分かりません」
木で頭をたたかれたためか、変わり果てた母の姿を見た衝撃のためか、アギラさんはこの日より以前の記憶をほとんど喪失。「家は農園の近くにあったように思います。家の中には写真が飾ってあったような・・。なぜはっきり思い出せないのかと自分を責めながら生きてきました」
父のことは「戦前になくなっていたのでしょうか。まったく覚えていません。私の姿格好を見てもらえば分かると思うのですが、恐らく日本人だった」と言う。
戦前、日本人女性は日本人の夫から呼び寄せられる形でダバオへ渡った。母親が日本人だった場合、父親も日本人の可能性が極めて高い。しかし、両親の名前、出身地さえ分からない状況では確かめようもない。
孤児となったアギラさんの運命はこの後も流転する。別のバゴボの一家にいったん拾われた後、日本人狩りを続ける比人兵に引き渡された。そのまま日本人収容所に連行されるはずだったが、たまたま重度の皮膚病を患っていたために軍の病院へ。ここで養父となる比人軍医、コンドラド・アギラさん=一九九三年に七十八歳で死亡=に出会うことになる。
軍医の二女、ベリア・アギラ・サレナスさん(55)は言う。「同僚には『ハポネサ(日本人女性)を養女にするのか』と陰口をたたかれていたようですが、身寄りのない子供を放っておけなかったのでしょう」
養女とはいうものの、実態は住み込みの子守兼メードで、サレナスさんら戦後に生まれた軍医の実子六人の世話をした。現在もサレナスさん宅の通いメードを続け、掃除・洗濯からサレナスさんの義母(89)の世話をしている。
自宅のある場所は、サレナスさん宅のある高級住宅街から歩いて十五分ほどの貧困者居住区。一万五千ペソで「居住権」を買い取った違法占拠住宅のバラックに住んでいる。四百三十万ペソで買い手を探しているというサレナスさんの邸宅とは文字通り「天と地」の開きがある。
「日本人として生まれたのは神様の意思。神様がこのまま放っておくことはないと信じています」。自分と同様の境遇に置かれた中国残留孤児約二千百人が日本政府の支援で集団帰国、うち約六百七十人の身元が判明したことも知らないまま、「自分は一体誰なのか」と自問し続けるアギラさん。中国の残留孤児、そして古里ダバオを再訪し自らの原点を確かめる日本国内の戦争孤児とは対照的に、歴史の闇から抜け出せないままだ。 (つづく)