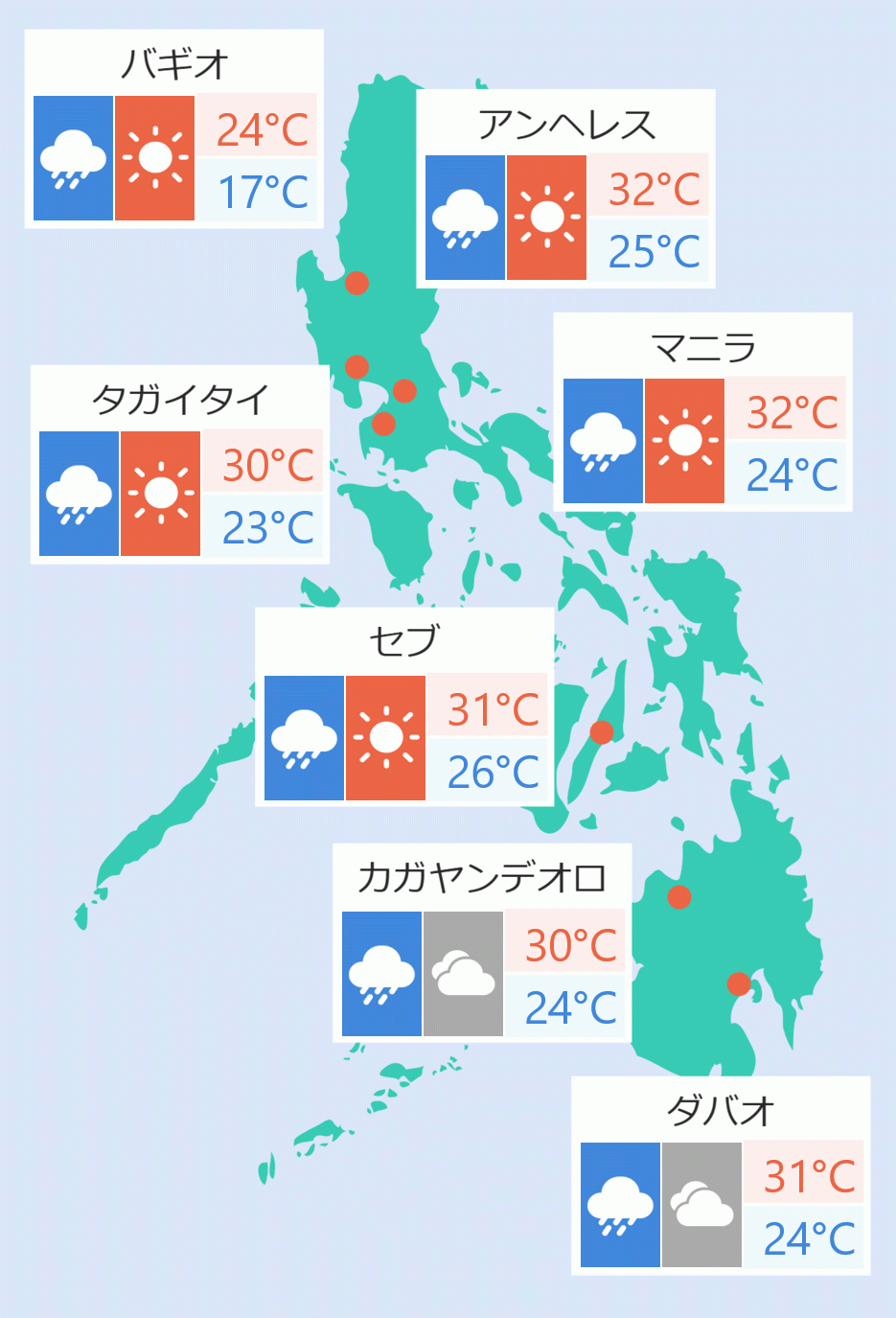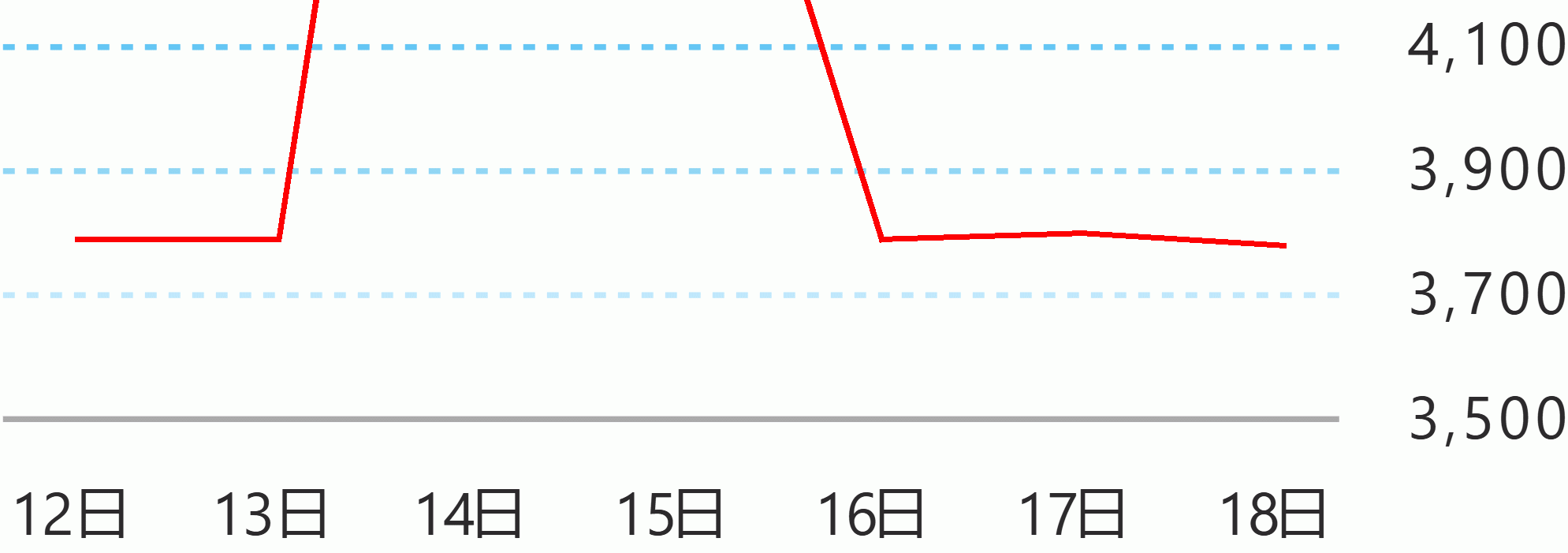庭の日陰に植えた茗荷(みょうが)の根茎から花穂がのぞいていた。周りの土をそっと取り除くと中に淡い紅色をした茗荷の子。八月八日朝のことだった。「マキリンのふもとなら、ひょっとして採れるかも……」。そんな淡い夢が一年ちょっとで正夢に。その夜、自家製の逸品をキュウリの酢の物にあしらった。「茗荷」は「芽香」(めか)が転じたものという。
・
晩春に顔を出す新芽は「茗荷竹」と呼ばれて春、花穂は「茗荷の子」で夏、そして花穂が育って咲き出す淡黄色の花は「茗荷の花」で秋と、それぞれが日本の季節感を表す季語。和英辞典の訳も「Japanese ginger」。薬味によし、酢の物によしで、いかにも日本の香りだと思い込んでいた茗荷。意外なことに熱帯アジアが原産地だという(岩波国語辞典)。
・
わが家のビッグニュースをセブ島に居住する植物研究家の知人に伝えると、早速「おめでとう」のメールが届き、数日後、「拙宅の茗荷の様子を調べたら、三個花つきで顔を出していました。今晩、冷やしめんの薬味にして香りを楽しみます」の第二信。東アジア原産のアジサイがほぼ年中、花をつけ、地元原産の茗荷が庭で採れる。日本とフィリピンの距離が以前よりもまた縮まった。(濱)


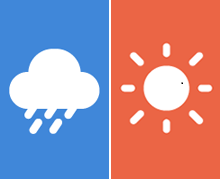


 English
English