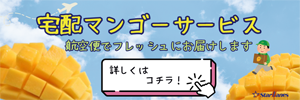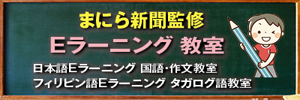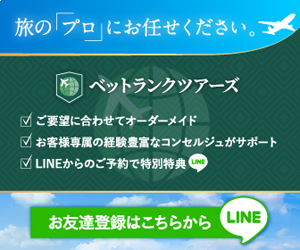現在も約1700万人の国民が貧困線未満の「絶対的貧困者」として生活しているフィリピン。比経済の宿痾(しゅくあ)であり、今なお最大の開発課題であるこの問題に、草の根レベルで取り組む比日の人々がいる。
バタアン州ディナルピハン町の道端にある素朴な作業所は、貧困世帯の母親たちで活気づいていた。壁には「繁栄した国家に向けた変革」との標語を掲げた垂れ幕。そこは、「児童とコミュニティ変革のための同盟(ACCT)」の事業所だ。同団体は、社会福祉開発省中部ルソン地域局長だったアデリーナ・アポストルさんが、退職後の2016年に立ち上げた。近所の貧困家庭の母親たちを集めハンドメイド雑貨を制作・販売し、家計の助けにする。小規模でも、自分たちにできることを広げていく。草の根「エンパワーメント」の取り組みだ。
▽アクションとの出会い
しかしその取り組みも、コロナ禍で大きな困難に直面する。強力な防疫規制の中で、商品が売れなくなる事態に直面した。そこに協力の手を伸ばしたのが、日本人が立ち上げたNPO法人「アクション」だ。オロンガポ市を拠点に1994年に設立され、貧困家庭や施設で暮らす子どもたちの自立を長年支援してきた同団体。アポストルさんは社会福祉開発省職員時代から同法人と縁があった。
アクションは、コロナ禍であることを逆手にとって、布マスクなどの布製品の制作をACCTに依頼して買い取り、販売した。布は近くの市場から廃棄予定の切れ端を無償で提供してもらい、再利用するという環境持続可能性にも配慮した事業として始めた。
「ところが、結局アクションの活動内部の需要にとどまっていた。アクションは社会福祉の専門家が多いが、マーケティングのプロがいないため、事業の天井が見えていた」と語るのはアクション本部で調整員をする山本浩平さん。「そこで、JICA(国際協力機構)の海外協力隊で、ビジネス経験のある人材に来てもらえないか相談した」。
▽厳しさと創造性
草の根の取り組みが直面した、小さな「開発課題」。この解決のために派遣されたのは、JRのグループ企業で5年間、駅やお土産開発に携わってきた前川未歩隊員(29)だ。昔から関心を寄せていたという協力隊の活動に、会社を退職して飛び込んだ。そんな前川さんが生計向上活動にもたらしたのは、「厳しさ」と「創造性」だ。
「最初は販路開拓の仕事を想定していたが、来てみたら商品開発から始めないといけないと分かった」と前川隊員。フィリピンらしさと端切れ布の唯一無二性を生かしたポーチや小銭入れなど、自分で商品をデザインし、試作品を作成し、ハンドプリンティングの一種、シルクスクリーンの型も一から作った。それを元に母親たちからデザインアイデアを出してもらい、フィリピンの感性を取り入れながら共に作り上げた。
「今まではアクションの買い取り。こっちが買い取ったらこれで終わりになっていて、その先のお客さんのことまで考えられてなかった。そこで一回品質管理のセミナーをお母さんたち相手に開いて、『商品を売るってこういうことだよ』ということとか、『もうちょっと品質を上げないと売れないよ』ということを伝えさせていただいた」(前川隊員)。
現在の販路は市やフェアなどへの出展だ。「ローカル向け市場だと低価格で販売される大量生産品に負けてしまうことが分かった」という前川隊員。そこで考えたマーケティング戦略は、品質管理とブランディングによって高付加価値化し、「ハンドメイド」や「サステイナブル」といった特徴に価値を見出す外国人客やフィリピンの高所得者層をターゲットにすることだ。
今は、SMメガモールで開かれるフェアなど、首都圏を中心に様々なイベントに出展しながら、顧客の反応を探っている最中。「ただ、イベントは出店料もかかるし、1回1回限りのこと。お母さんたちに必要なのは、適正な水準の安定した収入」と前川隊員。2年の派遣期間中に達成したいことは、安定的な販売先の確保だ。
▽ものづくりの喜び
「マム・ミホ(前川隊員)は品質に厳格。少しのズレも許さない。でもそれが良かった。求めに応えようとして、腕を上げられた」と語るのは、前川隊員の助言・指導の下で裁縫作業を行う母親の一人、レイチェル・アンドラーデさん(49)だ。
「彼女は私のクリエイティビティー(創造性)を表に出してくれた」と語りながら、自分でデザイン・制作した作品を見せてくれたレイチェルさん。その自信に満ちた目は、より高いハードルを超えるやりがいと、自分達の作った商品を世に出す「ものづくり」の喜びを物語っていた。4人の子のうちまだ2人が未成年というレイチェルさんは、夫に先立たれ、決して生活は楽ではない。そうした中で、この活動への参加は生計向上の着実な一歩となっている。「今でも生活は苦しいけれど、前よりは収入が上がった。とても助かっている」とレイチェルさんは語った。
こうした草の根の取り組みを通じて大切なものを獲得したのは、母親たちだけでなく、前川隊員も同様だ。「フィリピンに来てみて、家族や地域の助け合いであったりとか、多くのことを私の方も学ばせてもらっている」と語る前川隊員。2年の協力隊員期間を踏まえ、見据える将来のステージついては、「私は東北出身なんですが、今すごく過疎化している。いずれは学びを日本に持ち帰って、自分の故郷や地方の活性化に取り組みたい」と希望を語った。(竹下友章)


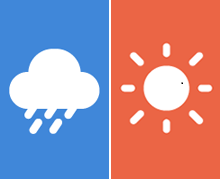


 English
English