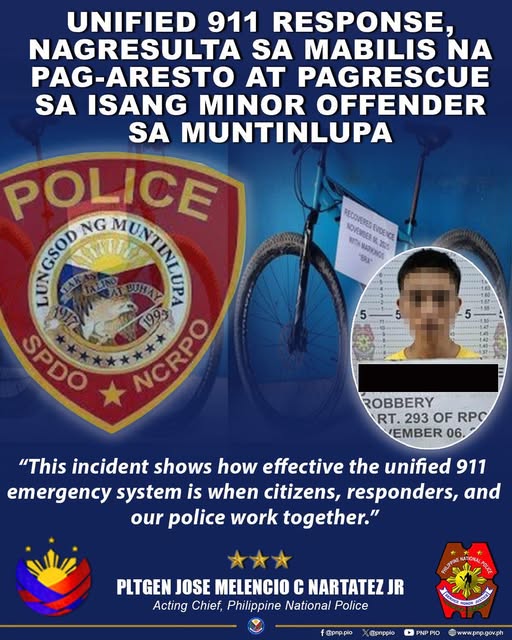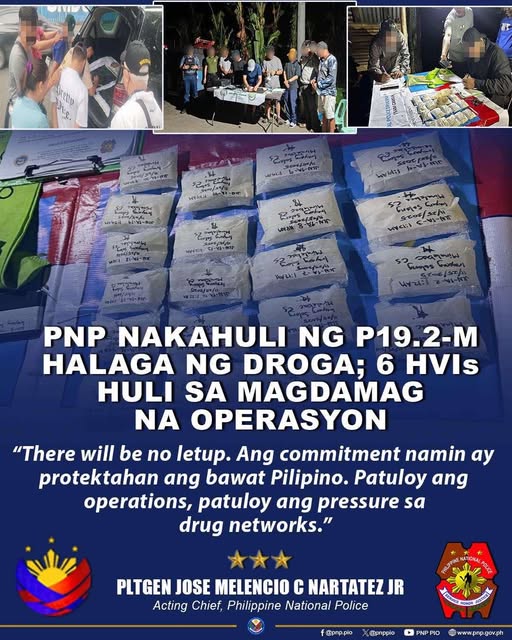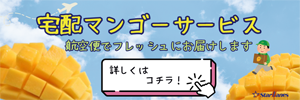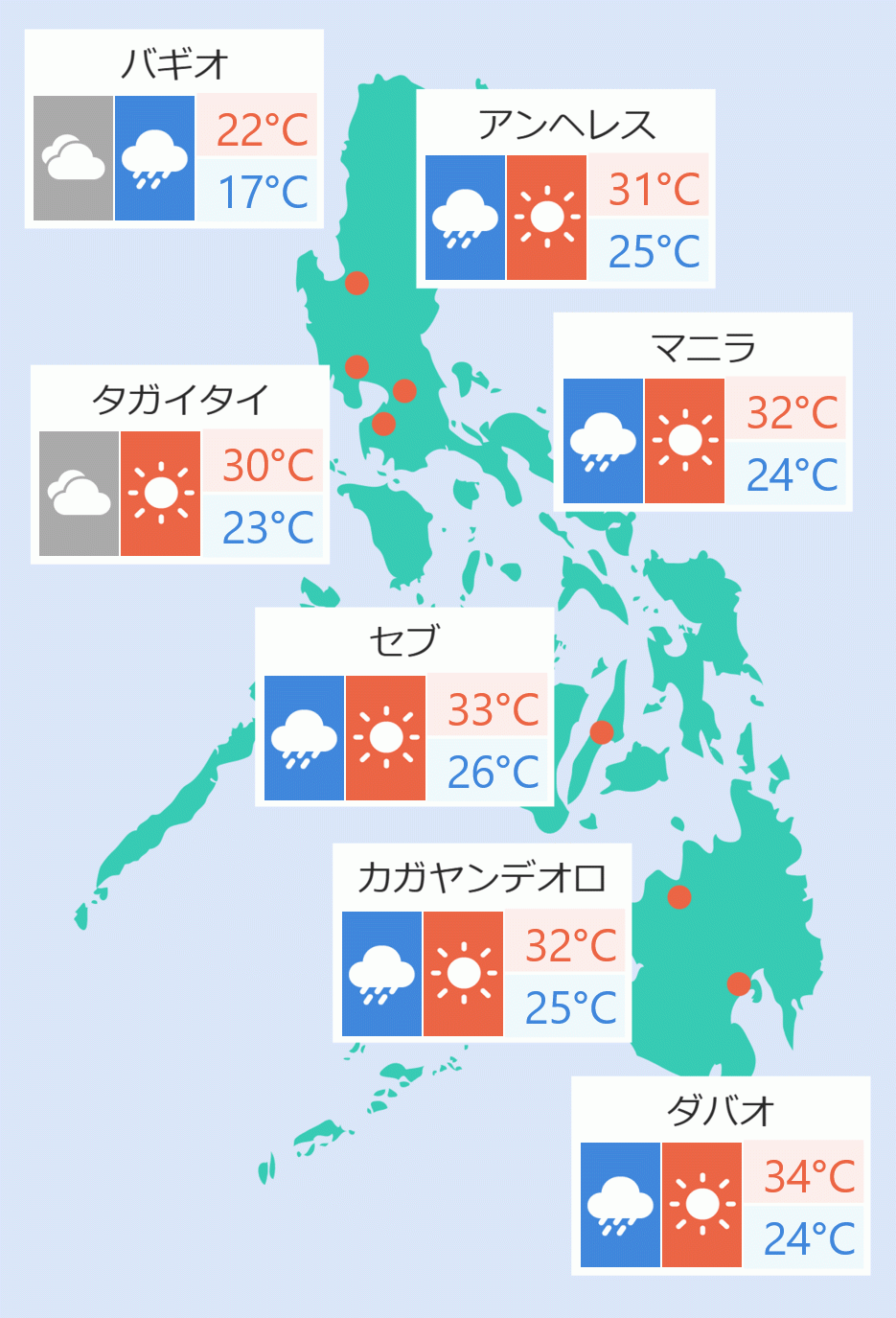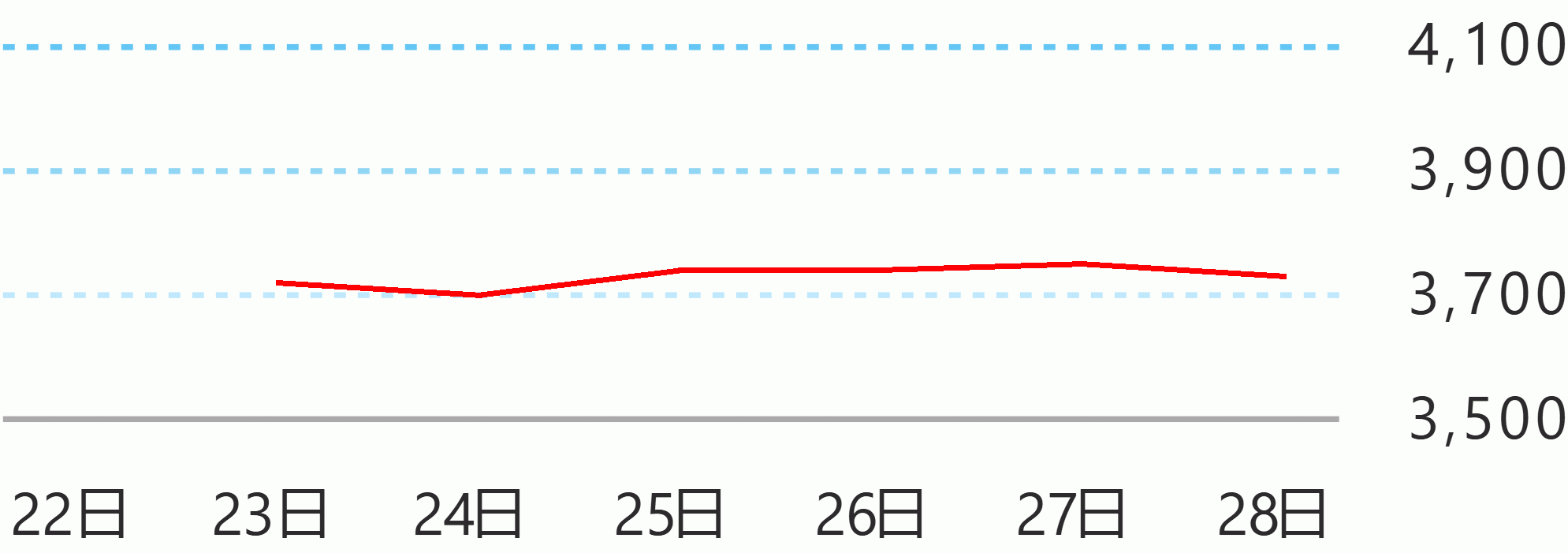陸地が見えたのは明け方だった。大きな島だ。ちょうど500年前の1521年3月16日のこと。その島(サマール)の南方沖に無人島(ホモンホン)を見つけた船団は慎重に近づき、翌日、上陸。水を補給し、休養をとるためだった。
何しろ、南米大陸南端の海峡を抜けてからここに着くまで3カ月余り、ひどい飢えに苦しんできた。新鮮な食料は何一つ残っていなかった。虫がわき、ネズミの小便の臭いにむっとする乾パンで食いつなぐ。飲み水は腐って黄色くなっていた。マストの帆桁を補強する牛皮まではがしてしゃぶった。歯茎が腫れ、壊血病で隊員が息絶えていく。
当時、西洋人の間で「マール・デル・スール」(南の海)と呼ばれていた太平洋がこれほど広大な海原とは。船団を率いるベテラン探検家マゼランにも想定外だった。
それでも、ホモンホンでひと息つけた。次の日、舟に乗った男たち9人が近寄ってくる。離島(スルアン)の住民で、漁にきていたのだ。
ものの道理が分かる
彼らは「(船団の)訪問を喜んでいる様子」。マゼランが赤い縁無し帽子、鏡、櫛、麻布などをプレゼントすると、返礼に魚やバナナ、ヤシの実、ヤシ酒などを差し出す。食料が欲しかった船団には僥倖(ぎょうこう)だった。身振り手振りで意思を通わせる。
これがマゼラン一行と「フィリピン人」が初めて遭遇した場面である。マゼランは男たちの振る舞いから「ものの道理の分かる人たち」とみてとった。まずは友好的な出会いだった。
以上の記述は、マゼラン船団に同行していたアントニオ・ピガフェッタ(1491〜1534)の航海記録を下地に書き起こした。
彼はイタリア出身の地理学者で、地図や天文学などにも通じていたとされ、航海記録を毎日書き続けた。幸い無事にスペインまで帰還できた数少ない生き残りの一人だ。
後年、航海記録は複数の言語に翻訳され出版を重ねる。その過程で改変されたりしたらしいが、専門家の間で「信頼すべき」とされるバージョンが日本語にも訳されている。16世紀初期、まだ「フィリピン」の呼称がなかった地域一帯の文書史料は極めて限られているだけに、ピガフェッタの航海記録は現在もなお一級の価値がある。民族誌であり、優れたルポルタージュだ。
しかし、地元側からの見方については、断片的な口承の民話以外に記述が残っていない(セブのサンカルロス大の歴史学者の話)のが残念だ。
平和と怠惰と静安好む
500年前に戻ろう。マゼラン一行は地元漁民らと親しくなり、彼らの支援を得てレイテ島沖の小島などを経由し、4月初旬、セブ島へ。
この間に出会ったのは「たいへん陽気でおしゃべり」な人たちだった。ピガフェッタによると、各所で酒食に招いてくれた。魚や豚肉をよく食べ、「ものすごい大酒飲み」でもあった。ビンロウジュの実を割り、少量の石灰と一緒にキンマの木の葉に包んで噛む習慣についても細かく記録。ドロドロになると吐きだし、「口の中が真っ赤に染まる」と描写している。
高床式の家に住み、家屋の下で豚やヤギ、鶏を飼う。「法秩序を持ち、度量衡を定めている。平和と怠惰と静安を好む」とピガフェッタは観察している。セブで、有力者の邸宅での晩餐に招かれた時は、若い女性4人が青銅製の打楽器を演奏してくれた。「4人はかなり美しくそして色白だった」と書く。
何だか、今日のフィリピンの人たちとほぼほぼ同じようではないか。
友好的な出会いではあったが、マゼラン船団が無防備、無警戒だったわけではない。上陸時には戦闘態勢をとり、大砲を一斉に発射したり、剣や盾で完全武装した船団員が互いに戦う様子を見せたりして威嚇した。
「敵ではなく友人として訪れた」。マゼランは地元の有力者にそう伝える。だが、デモンストレーション効果は絶大だった。住民たちは「大いに驚き恐れた」とピガフェッタは書き残している。笑顔と恐怖が交差する出会いだったのだ。(客員編集委員 大野拓司、続く)
◇
マゼラン船団の記録 日本語に訳出されたピガフェッタの航海記録とマゼラン船団の生き残った船団員からの聴き取り調書は、長南実訳「マゼラン 最初の世界一周航海」(岩波文庫、2011年)で読める。後年、当時の様子を扱う研究書などが出版されているが、その多くはピガフェッタの記録や船団員の調書を引用している。
◇
おおの・たくし 1948年生まれ。70〜77年、フィリピン大学大学院で遊学生活を送った後に朝日新聞社入社。マニラ支局長。ナイロビ支局長、シドニー支局長、AERA副編集長などを務める。共編著に「フィリピンを知るための64章」など。


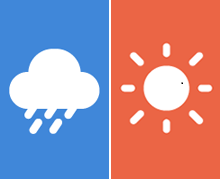


 English
English