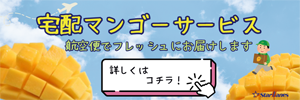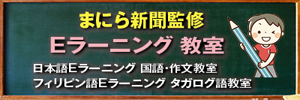今月には第二次トランプ政権が始動し、5月には中間選挙が行われるなど、内外の政治状況が大きく変動する2025年。混迷を深めるフィリピンの民主主義をどう読み解くべきなのか。40年近くにわたりフィリピン政治に向き合ってきた経験に基づき、昨年「ルポ フィリピンの民主主義ーピープルパワー革命からの40年」(岩波新書)を上梓(じょうし)したジャーナリストの柴田直治氏(朝日新聞元論説副主幹)に話を聞いた。後編は現政権への評価、そして厳しさを増す国際情勢の中で日本は比とどう向き合うべきかについての同氏の見解を紹介する。(聞き手は竹下友章)
―「デジタル権威主義」の前政権を引き継いで誕生した現在のマルコス政権をどう評価するか。
父の戒厳令を「正しかった」と公言するボンボン氏が歴史的な大勝をしたことで、ドゥテルテ政権以上に強権主義的な政権運営がなされる可能性も指摘されていた。だがフタを開けたら、権威主義を前面に押し出すことはなかった感じだ。あくまで前政権との比較でだが、押さえつけられていた法の支配がある程度回復し、強権的な色彩は薄れたように見える。
例えば対外的には、ドゥテルテ氏が軽視していた2016年の南シナ海仲裁裁判所判断を根拠に国際法に基づく権益主張を行い、欧米先進国の支持を集めることに成功している。国内的には、ドゥテルテ政権下で多数の訴訟にさらされたラップラーCEOのマリア・レッサ氏への無罪判決が政権交代後に相次ぎ、前政権で長期拘束されていたレイラ・デリマ元司法相も保釈され全裁判で無罪を勝ち取った。一方で、ドゥテルテ政権下の「赤タグ付け」で有名だった「共産主義勢力との武力紛争を終わらせる国家タスクフォース」のバドイ元報道官に対しては、マニラ地裁が罰金の支払いを命じた。麻薬戦争も前政権から180度転換し、多数の「超法規的殺害」を伴う過激な捜査より、予防と更生を重視する方針を強調している。
だがこれは、ボンボン氏自身が「法の支配や自由民主主義を回復させたい」という信念を持っているからではないだろう。自陣営の政治的基盤を強くするために前政権へのアンチテーゼを打ち出したい政治的思惑の結果としてみるべきだ。本当に法の支配を貫徹したいのなら、最高裁判決が出ているにもかかわらず未払いのままの2030億ペソの相続税を、まず自分が支払っていないとおかしいからだ。
また、ボンボン氏自身はノイノイ・アキノ元大統領と同様に「育ちのいい二代目」であるため、権威主義に振り切るほどの野心を持たない性格というのもあるだろう。
しかし一方で、目立たないようにじわじわ歴史を改ざんする動きも見せている。例えば、2月25日のエドサ革命記念日を理由を付けては一日ずらしたり、祝日から外したりしている。また小学校社会科の教科書に出てくる「マルコス独裁」の単語が、「独裁」という表記に変えられた。最近だと動物を絵柄にした新札を発行したが、狙いはアキノ夫妻の肖像が載る500ペソ札の将来的な廃止だろう。こうした動きに対し、国内からの反発は大きくは聞こえてこない。ある意味で、様子見しながら「うまくやっている」。
―大統領とドゥテルテ家との対立をどう見る。
マルコス陣営の中にも強硬派から穏健派まで濃淡あると思うが、ボンボン氏の性格を考えたら、現時点では父娘を刑務所送りにするような徹底的なドゥテルテ家つぶしを行うことは考えにくい。サラ氏の弾劾に対する否定的な発言は素直に受け取っていいと思う。
ドゥテルテ氏の超法規的殺害に関する問題は、プーチン大統領やネタニヤフ首相への逮捕状を出させた国際刑事裁判所(ICC)のカーン主任検事が取り組んでおり、今後の展開に注目している。ただ、超法規的殺害問題については下院が人道に関する罪を規定する国内法違反で告発した。これは、国内で人道犯罪容疑者を訴追する意思・能力が欠如している場合にのみ司法管轄権を行使する「補完性の原則」を持つICCの今後の動きに影響する可能性がある。
いずれにしても、ボンボン氏としてはしっかり切り札を確保しつつ、「ケツをまくったら何するか分からない」怖さのあるドゥテルテ父娘とのこれ以上の衝突激化を避けながらも、父娘の力をそぎたいといったところが本心ではないか。
―「トランプ2・0」はフィリピン外交にどう影響するか。
比の政府高官は口をそろえて「今の方針が維持される」と強調している。それは、私には不安の裏返しにみえる。第二次トランプ政権(トランプ2・0)での比米外交関係の焦点は、やはり南シナ海問題だ。「鉄壁」をうたう今の比米防衛関係だが、トランプ氏は基本的にフィリピンや東南アジアに関心がない。ドゥテルテ前大統領が比米訪問軍協定(VFA)の破棄を通告したのはトランプ政権下の20年だったが、当時トランプ氏は「破棄されても正直気にしていない」と述べている。バイデン政権下では、米国は南シナ海問題でフィリピンと肩を並べて中国に対峙(たいじ)する姿勢を見せてきたが、政権交代ではしごを外される可能性は除外できない。そこで問題となるのがここ数年、急速にフィリピンとの海洋安全保障協力を推し進めてきた日本だ。
―日本はフィリピンとどう付き合うべきか。
今、南シナ海の領有権争いの最前線で中国艦船との小競り合いを続ける比沿岸警備隊(PCG)は日本に「おんぶにだっこ」状態だ。動いているほとんどの巡視船は日本の政府開発援助(ODA)で調達したものだし、そのメンテナンスもトレーニングも全て日本が支援している。最近では軍事協力も進み、政府安全保障能力強化支援(OSA)を通じた比国軍への沿岸レーダー無償供与を決定したほか、部隊間協力円滑化協定(RAA)も締結見込みだ。
フィリピン国民やメディアの間で、南シナ海でもしものときに日本が助けてくれるという期待が高まっていることに驚くことがある。こうした状況下で、トランプ政権が南シナ海問題から手を引いたら、日本だけで支えられるのか。フィリピンの人々に肩透かしを食わせることにならないか。専門家の中には今こそ日本が支える時だと主張している人もいるが、支えるだけの国力がいまの日本にあるはずもない。
安全保障協力を推し進めるほど、「巻き込まれリスク」は高まっていく。もし南シナ海「レッドライン越え」の事態が起こり、比が軍を出すという局面になったとき、日本がフィリピンを助ける意思や能力を持っているとは到底思えない。そもそもそうした事態に対して日本国民は無関心というより、状況自体を認知していないし、国会ですら議論されていない。そのうえトランプ政権からはしごを外されたら、日本は(サッカーの)オフサイドトラップにかかったような状況に陥る危険がある。
たしかに、比中の軍事力格差を背景に、フィリピンの南シナ海の実効支配がじわじわ削られているという現実がある。中国の横暴は目に余るし、心情的にはフィリピンに肩入れしたい。しかしながら安全保障分野の協力は、第一に同盟国である米国の役割だ。日本は、地下鉄などのインフラ整備や経済的支援でフィリピンが国力を高める手助けをすることに専念する方が良いと私は考える。餅は餅屋だ。
◇
しばた・なおじ 19
55年生。早稲田大卒。朝日新聞マニラ支局長、アジア総局長、論説副主幹などを歴任。退職後は近畿大教授を経てフリーに。現在アジア政経社会フォーラム共同代表。著書に「バンコク燃ゆ:タックシンと『タイ式』民主主義」(めこん、2010年)、「ルポ フィリピンの民主主義ーピープルパワー革命からの40年」(岩波新書、2024年)。


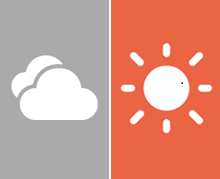


 English
English