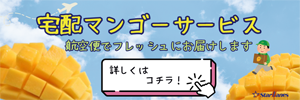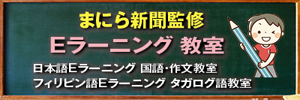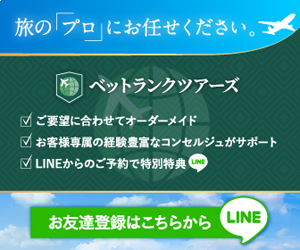フィリピン日本商工会議所は先月、昨年11月に制定された企業復興税優遇措置法改正法(CREATE MORE法)の施行規則(IRR)が2月に相次いで発出されたことを受け、税務の専門家を招き、CREATE MORE法の留意点に関するオンラインセミナーを開催した。セミナーには、二瓶大輔経済公使、商工会議所の藤井伸夫副会頭のほか、進出企業の税務・法務を支援する「PwCフィリピン」の東城健太郎氏、在比日本国大使館業務委託弁護士をしているTMI総合法律事務所の團雅生弁護士、同事務所の生駒大典弁護士が登壇。長年の懸案である輸出企業の国内調達に関する間接税(VAT)の還付制度について、施行規則がどこまで有効な手立てとなっているかについて見解を共有した。
施行規則の概要説明にあたりPwCフィリピンの東城氏は、21年4月のCREATE法発行後の経緯を説明。内国歳入庁(BIR)は21年6月、実態が伴っていなかったにもかかわらず「VATの還付制度が確立された」ことを理由に、ローカル企業から輸出型企業への間接輸出に対し、歳入規則を通じてVATを課すことを唐突に宣言。さらに同規則は、CREATE法本文で投資促進機関(IPA)への登録企業(RBE)をVATインセンティブの対象としていたのを、登録輸出型企業(REE)のみに限定したほか、国内調達に関するVATゼロレートの適用に関し、「登録事業に直接的かつ排他的に使用される」という条件が新たに加えたものの、その「具体的説明については皆無だった」と指摘した。その後施行規則が2回改定されるなど、紆余(うよ)曲折を経たことを振り返り、「今回施行規則が出たからといって、それが最終とは限らない」と注意を促した。
今年2月に税優遇措置再検討委員会(FIRB)、財務省、内国歳入庁(BIR)などから相次いで発出されたCREATE MORE法のIRRについては、「CREATE法の時と異なり、法律とIRRに大きな不整合は見られない」としながら、VATゼロレート適用に関し、改正前の「直接的かつ排他的使用」から改正後に「直接的帰属」と拡大された条件について、「条件に適合しているかどうか最終的に判断する主体がIPAだと法律に明記されているにもかかわらず、BIRが2月に出した歳入規則では、『直接帰属』するか否かを、BIRが事後的に調査すると書いてある」と指摘。「BIRが独自ルールで追徴課税してくることはこれまでも発生したこと。将来的に何らかの問題を起こしかねず、安心できない」と強調した。また、「IRRは既に支払ってしまった税金の還付・控除は認められないと定めており、救済措置は取られなかった」と報告した。
長年制度がありながらも機能してこなかったVATの還付については、「今回のルールがしっかり運用された場合、ゼロレートが適用される輸出型企業がVAT還付申請する機会は今後はなくなると考えられるが、サプライヤー側が還付ポジションを持つと考えられる」と説明。これまで否認されることが多かった還付申請について、「今回の新規則でBIRへの異議申し立ての仕組みが導入されたが、法律は昨年11月に発効しているにもかからわず歳入規則は4月1日から適用されると読める内容となっている。その間にも還付申請が否認された企業もあり、そうした企業はどうなるのか不透明だ」と指摘した。
還付申請については、昨年1月に制定された納税容易化法(EOPT)により、申請がこれまでの履歴などにに基づき低・中・高の3段階のリスクに分類され、低リスクの申請については迅速に処理される方式に変更されているが、この新方式についても「最初の数回の申請は自動的に高リスクに分類され、一度低リスクに分類されても何回か続けるとまた高リスクに戻される規則になっている」と問題点を説明した。
BIRのVAT還付否認に対する不服申立てについて、TMI総合法律事務所の生駒弁護士は「否認の通知から15日以内に申し立てなければならないと規定しており、しかも、租税控訴裁判所(CTA)の上訴はBIRへの不服申立てを経ないといけないと読める内容になっている。これまでCTAへの上訴は否認通知から30日以内だったが、タイムラインは以前よりシビアになった」と警鐘を鳴らした。
経済特区内のロジスティクス企業がVATゼロレートの対象外と取り扱われたことで、22年以降各企業から悲鳴が上がったVAT問題。その根底にあるVAT還付制度の機能不全は、「ゼロレート適用より大きな問題」(TMI総合法律事務所團弁護士)だ。
東城氏は、「還付制度の改善で本気度が感じられたのは、2018年のTRAIN法制定(加速と包括のための税制改革法)だった。このときに、VAT徴収額の5%を還付予算に充当するというルールもできた。実は、BIRは2018年だけVATの還付情報を開示している。しかしそれ以降、還付額は開示されておらず、5%の還付予算がどう利用されたかも公表されていない」と述べ、VAT還付制度がいまだ不透明な状況にあることを説明した。
商工会議所の藤井副会頭は「VATの関係については長いこと議論してきたが、今回の施行規則は一言でいえば安心できない。この国では交渉が重要となっていて、税務当局が何か言ってきたら、こちらも理屈を立てて対応するという心づもりが必要だ」と強調した。(竹下友章)


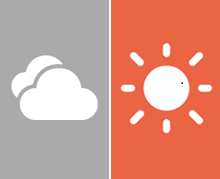


 English
English