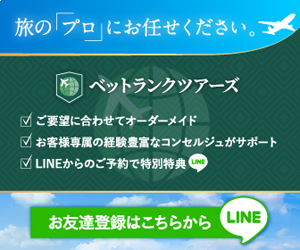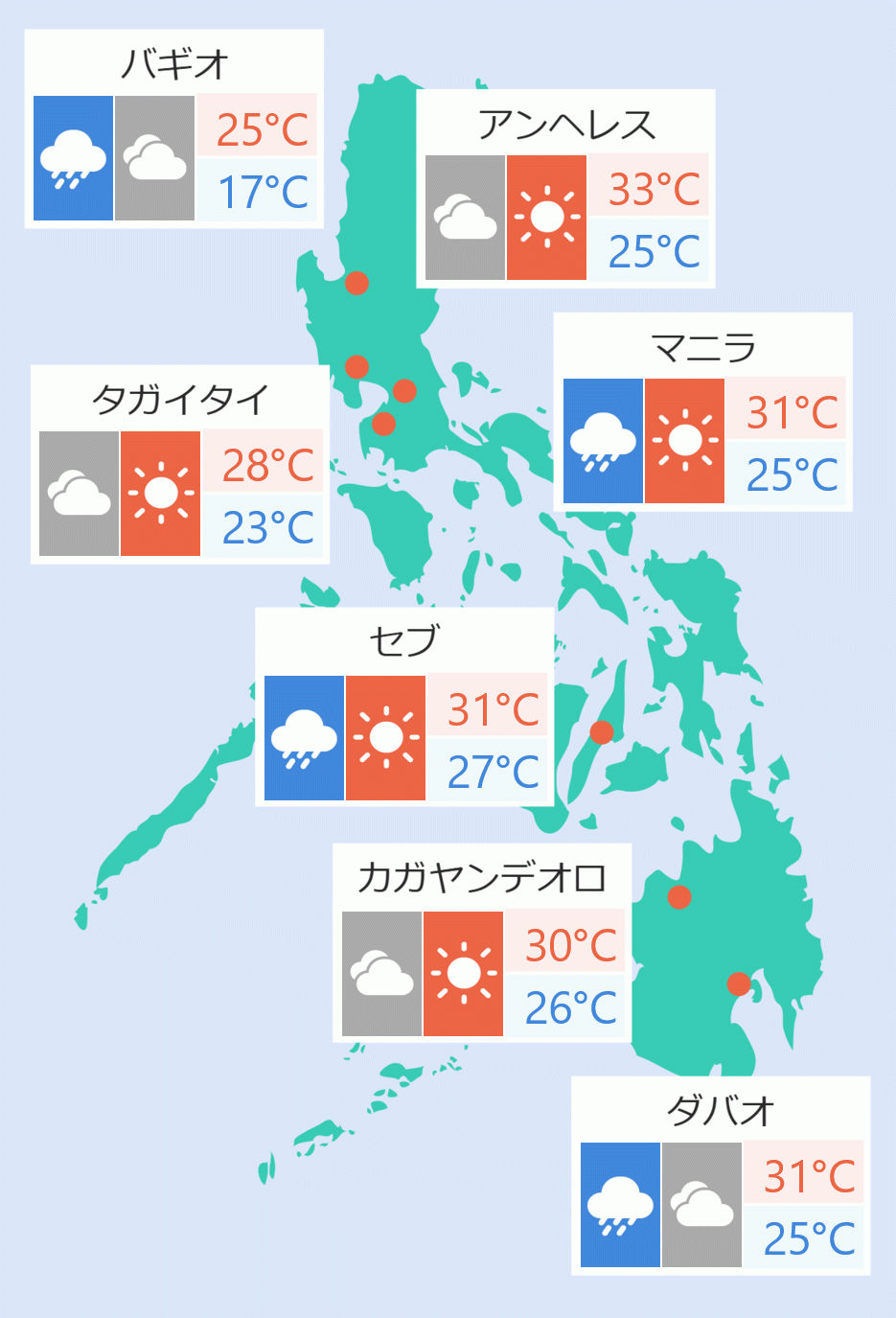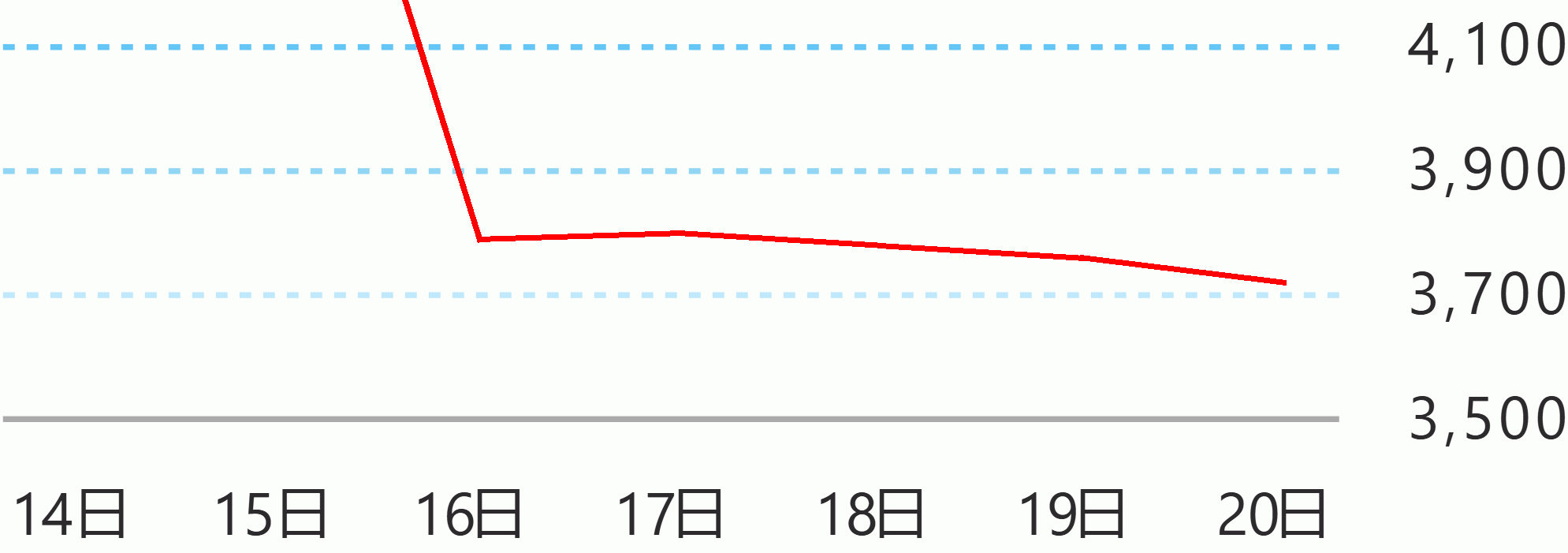世界銀行は、フィリピン経済が25~26年の間に上位中所得国(中進国)入りするとの見通しを明らかにした。19日の英字紙ビジネスミラーが報じた。国家経済開発庁(NEDA)のバリサカン長官は、25年に中進国入りする可能性があるとの見通しを示していたが、この予測が世界の国々の所得分類を担う世銀から一定程度支持された格好だ。
フィリピンは1987年以来、下位中所得国にとどまっており、先に中進国入りしたマレーシア、タイ、インドネシアの後塵(こうじん)を拝する。中進国入りすれば約40年ぶりの画期的な所得階級の上昇となるが、一方で政府開発援助(ODA)の金利上昇や、欧州諸国などによる途上国対象の関税優遇措置の資格の喪失など、先進国からの経済協力の変化にも直面する。また、これまでの成長パターンが限界を迎え、成長が停滞する「中進国の罠」を乗り越えるために、政府はより生産性の向上にフォーカスした経済構造の転換への取り組みを迫られることになる。
世銀は1人あたりの国民所得(GNI)の水準によって国・地域の所得を分類する。現在は4516ドル~1万4005ドルを上位中所得国としており、23年の比の1人あたりGNIは4320ドルだった。
▽「生産性主導」の経済に
ビジネスミラーの取材に対し、世銀のムスタファオール比担当責任者は「フィリピンが上位中所得国に移行する中、成長を持続させ、中流社会の確立と貧困の撲滅というビジョンを達成するには、『投資主導型』から『生産性主導型』への成長への転換が必要だ」と強調。「高価値の雇用を創出するために、比政府の戦略は、競争の促進と事業コストの低減、デジタル・AI(人工知能)技術の推進による生産性向上とイノベーションにフォーカスすべきだ」と述べた。また貿易可能な部門を刺激するために、「貿易障壁の低減、物流の改善、そして外国直接投資によるスピルオーバー(技術伝播などの経済効果)を進めるべきだ」と提言した。
さらに、生産性を向上させるための重要要素として人的資本への投資を挙げ、「発育不良を低減し、初期教育を改善するとともに、技術の変化に対応できるように、現在の労働者のリスキリング(技能再習得)・アップスキリング(技能向上)を進めるべきだ」とした。
80年代から90年代にかけ、途上国から中進国へと目覚ましい発展を遂げたシンガポールや韓国などの新興工業経済地域(アジアNIEs)を世銀は93年に「東アジアの奇跡」と称揚した。それに対し、経済学者のポール・クルーグマン=2008年にノーベル経済学賞受賞=は、論文「アジアの奇跡という神話」(1994)の中で、当時のアジアNIEsなどの経済成長は莫大な資本の労働の投入によって説明でき、高成長期のソ連経済と同じパターンだったことを指摘。教育やイノベーション(技術進歩)などによってもたらされる、労働・資本の投入増以外による生産性(全要素生産性)の向上を進めなければ、ソ連と同様に成長が限界を迎えると指摘している。(竹下友章)


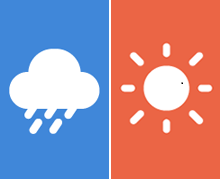


 English
English