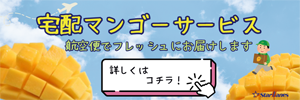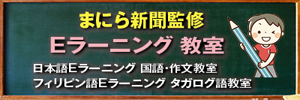第6回 ・ 比日の自然素材と技術融合 手すき紙、豆本作家の志村朝夫さん

ルソン地方北部の避暑地として観光客の人気も高く、教育の中心地でもあるベンゲット州バギオ市。そこから満員のジプニーに乗ること2時間半、さらにトライシクルで15分ほど行くと、同州カパガン町ラボックのポキン地区に着く。澄んだすずしい空気に、見渡す限りの緑。およそ外国人は滅多に訪れそうにない山中の農村に、比日の自然素材と技術を融合して手すき紙や豆本(3インチ四方の小さな本)、紙布を作る日本人アーティストがいる。
志村朝夫さん(63)=山梨県出身。自宅を中心に、ピニャ(パイナップル)やアバカ(麻)、サバ(調理用バナナの一種)など比で採れる自然の繊維を使い、日本の手すき技術で紙を作っている。紙を裂いて「より」を掛け、糸にしたものを織り込んで作る日本にしかない技術「紙布」や、最近では、比日で手に入るコンニャクを煮出して作った「のり」を紙に塗ることで、耐水性や強度を高める「コンニャク加工」を実践中。1990年代には、ピニャ織りの技術を持つビサヤ地方アクラン州で紙すき、紙糸、布づくりの指導をしたほか、貿易産業省(DTI)に招かれビコール地域で講習会をしたり、米国など海外で紙すきや豆本の講習会に招かれることも多い。
都内の工業高等専門学校に通っていた60年代、静岡県富士市田子の浦港では、製紙工場から排水されるヘドロ公害が問題になっていた。水質分析を専攻していた志村さんは、工場排水が流れ込んだ水のサンプルを取り、水質を分析して学園祭で発表した。
「機械を使った製紙業が環境に及ぼす影響を実感した。製紙産業への反発から、環境や人に負荷のない紙すき和紙へ傾倒していった」。卒業後に福岡で体験した藍染めと和紙との出会い、書店を経営していた実家の兄から、はがきサイズまで印刷できる活版印刷機を譲り受けたことなどが重なり、志村さんは、自ら紙を作り、その紙を染め、自分で書いた文章を印刷し、製本して豆本を作る、マルチな芸術家となった。
初めて比を訪れたのは、1983年。京都で開催された国際紙会議で、バギオ市で紙すきを教えている米国人マイケルさんと知り合ったのがきっかけだった。89年、日本で体調を崩していた時、マイケルさんからバギオ市で活動する民間団体への就職を勧められ、同市に住み始めた。最初は気分転換のつもりだったが、91年には、仕事場で知り合った比人妻のアンドレアさん(49)と結婚。2男1女を授かった。アンドレアさんの前夫との娘と、孫1人も含め、家族7人でアンドレアさんの出身地である、カパガン町に住んでいる。
自宅を訪ねると、志村さんが手製カレーを振る舞ってくれた。自家製キムチに、熱帯果物で酸味があるサントルの自家製ジャムも一緒。何でも自分で作ってしまう。「サントルにはタンニンが含まれているので茶色が出る」。作業場には、もらってきたばかりの地元の茶葉とレモンジュースを使って、コンニャクのりで手すき紙に色をつけた試作品が干してあった。植物や鉱物を目にすると、どんな色が出るか想像して試したくなるという。
志村さんは7月、自宅に3平方メートルのミニミュージアムを開いた。日本で活版印刷した世界の手すき紙に関する豆本36冊を展示している。年内には「ノー・ワン・ウッド・カム(誰も来ない)」と名付けた6平方メートルのスペースもスタジオやギャラリーとしてオープンする計画だ。
作った紙糸をアクラン州に送り、現地の職人が織り込んで紙布にし、それをバギオ市の仕立屋に依頼して帽子や服を作ったり、イフガオ民族の木彫り職人に版木を作ってもらい、ピニャの手すき紙に般若心経を印刷する││。志村さんの創作活動が、比日、また比国内のさまざなまな地域の職人の技術を生かし、協働を通してつなげている。
すでに、バギオ市を拠点とする若手アーティストと、スタジオを使って紙布服のファッションショーを開いたほか、デジタル印刷のワークショップや、比の旅行記、料理本を作ってバギオ市周辺の本屋で販売する計画もある。
志村さんによると、日本で手すき紙を作っているのは200カ所ほどで、減少傾向にあるという。作り手不足に加え、農家の高齢化で紙の国産原料の減少も著しい。一方、比にはアバカやピニャなど紙の原料が豊富だが、価格競争で機械に勝負できない手すき紙や織物作りは、担い手がいなくなれば地場産業はなくなってしまう可能性がある。
「地元の芸術家と、紙すきの講習会や作品作りの場として共有していきたい」。ミュージアムを通した志村さんの創作活動が、北部ルソンを中心に比国内の若い芸術家を巻き込み、比日の自然素材、伝統技術を活用した新しいアートシーンが盛り上がろうとしているのを感じた。(大矢南)
(2013.9.9)


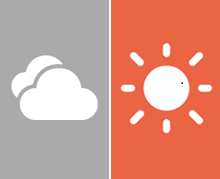


 English
English