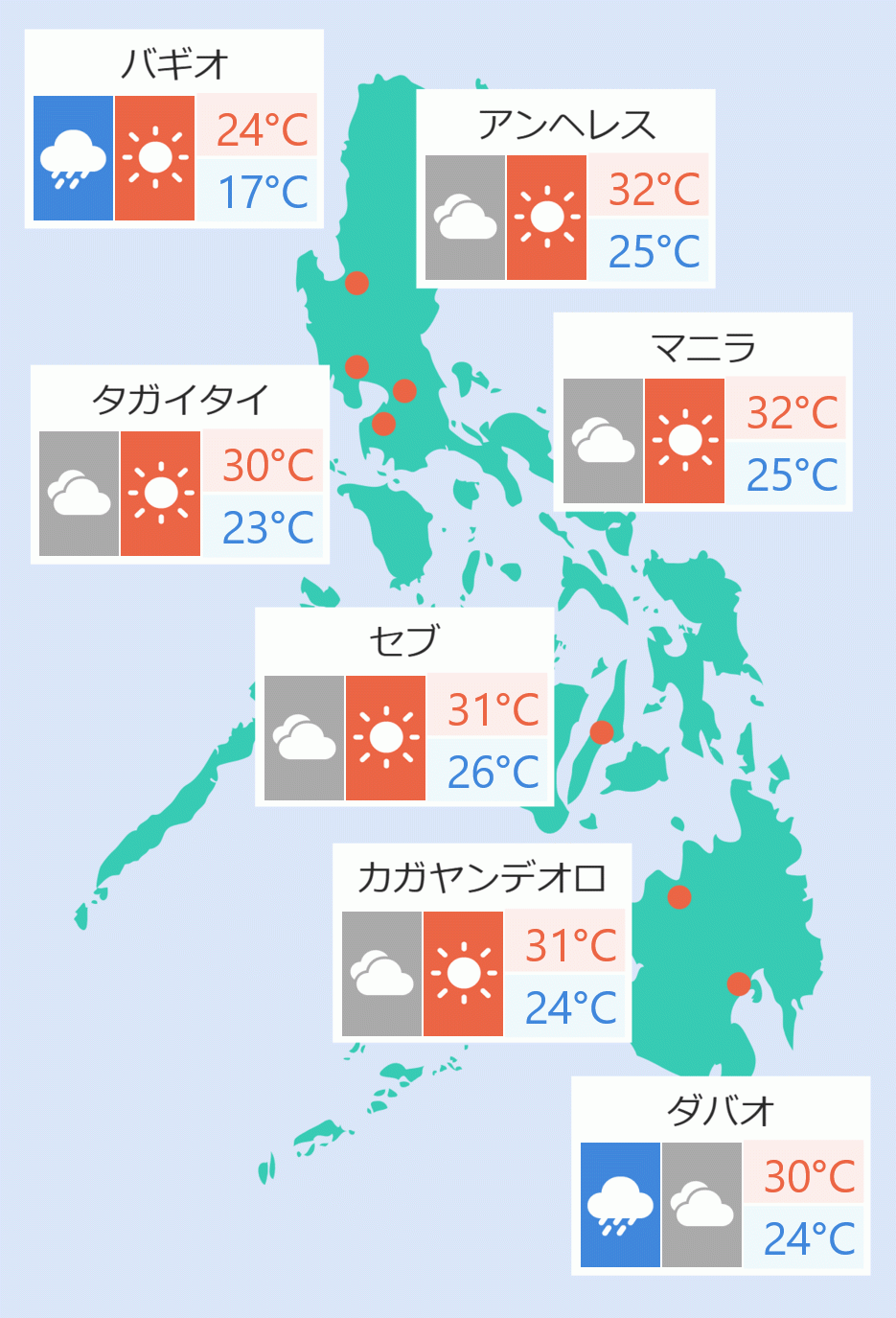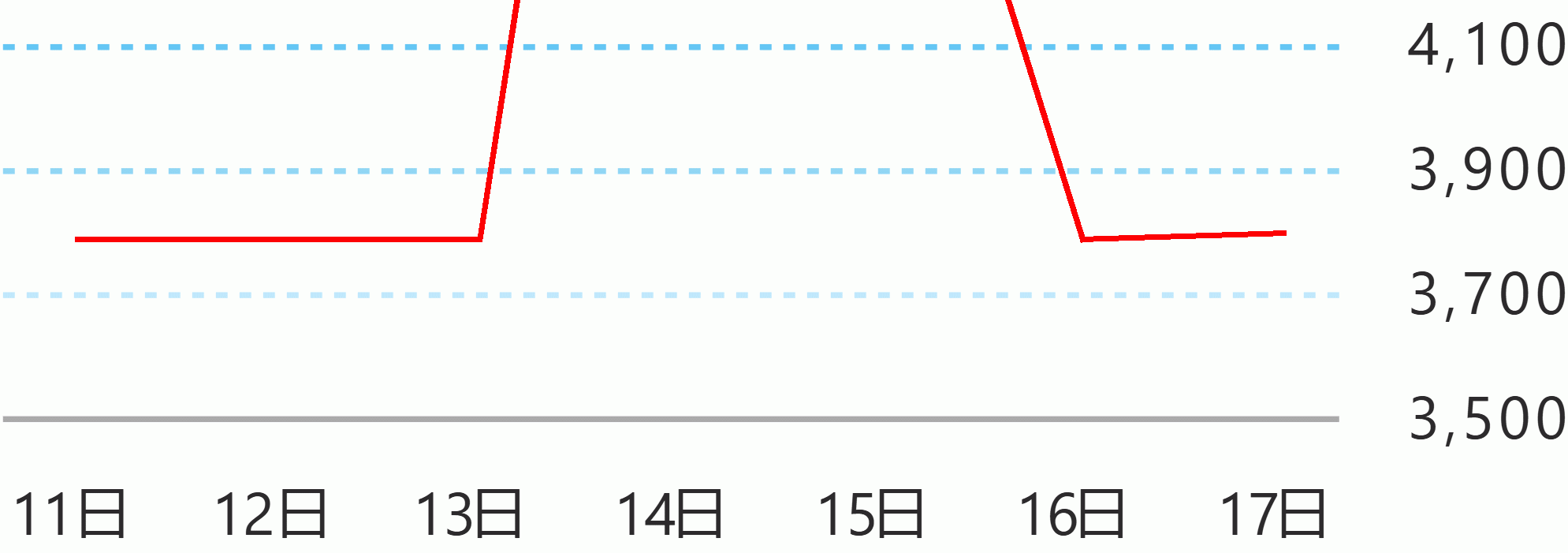第1回 ・ 結び直された縁

旧日本軍戦没者の慰霊碑を守り続けて約四十年。クリスティーナ・ラミレスさん(80)=北部ルソン地域パンガシナン州ウルダネタ市=には、若き日の秘めた思い出がある。
時は、約六十年前の太平洋戦争中。場所は、父の生まれ故郷サマール州。開戦直前、ウルダネタ市から同州へ渡ったラミレスさんは、侵攻してきた日本軍の兵士に求愛された。当時十七歳。「タカハシ」というその兵士は二十歳。片言の英語で「戦争が終わったら日本へ帰るが、必ずここに戻ってくる。一緒に日本へ行こう」と約束したという。
約束から五カ月後、タカハシは戦死する。一九四五年だったが、正確な月日は思い出せない。その朝、「ゲリラを殺しに山へ入る」と告げたタカハシ。ラミレスさんは「気をつけて」と見送った。昼すぎ、日本兵四人の遺体が村へ担がれてきた。その一人がタカハシだった。
「タカハシの誠意は片言の英語から伝わってきた。遺体を見た時は涙がこぼれました」と追想するラミレスさん。同州から生まれ故郷のウルダネタ市カバルアンへ戻ったのは戦後の一九四八年三月だった。
同市に近いリンガエン湾は開戦時と戦争末期、日米両軍の上陸地点となり、激戦は地元住民から家や田畑、家畜など財産を根こそぎ奪い去っていた。ラミレスさん一家の自宅も跡形なく消え、宅地跡周辺には人骨やヘルメットが散乱していたという。
家を再建し、骨などを拾い集めながらトウモロコシや野菜を植えると、思いもしない事が起きた。「採れる作物がみな通常より大きいのです。近所では『兵士の死体が肥料になったからだ』とうわさになり、私は絶対口にしなかった」
「うわさ」を裏付ける日米の局地戦が戦史に刻まれている。戦いの舞台は、ラミレスさん宅のある小高い丘。一九四五年一月、鹿児島県出身者で構成される旧陸軍歩兵第七一連隊所属の大盛支隊約九百四十人が丘に陣取り、米軍の艦砲射撃や爆撃にさらされ約二週間で八百人強が戦死した。ラミレスさんが戦史を知ったのは、遺骨収集団が丘を訪れ始めた六〇年代に入ってから。以後、遺族らの依頼で丘に立つ慰霊碑の清掃を続けるようになったという。
慰霊碑は一九八二年に建て替えられ、今はマンゴーなど木々の深い緑が周囲を包む。戦争の痕跡が消えようとする玉砕の丘。碑を訪れる鹿児島県の慰霊団は二〇〇二年を最後に途絶え、タカハシとの出会いから六十年以上続いてきたラミレスさんと日本人との「縁」も切れようとしていた。
そんな縁を新たに結び直すような慰霊祭が〇五年二月、丘で行われた。参加者は地元住民や日系人団体関係者ら約三百人。慰霊祭前で祈りをささげたのは、日本人僧侶ではなく比人カトリック神父。「日本側遺族・戦友不在の慰霊祭」だった。
慰霊祭を実現させたのは、退職後にウルダネタ市へ移住、比人女性と結婚した斎木一さん(64)=東京都大田区出身。「この地に住む日本人として、碑の意味を妻や娘、比の人たちに伝えていきたい。そのことが日比友好と碑を守ることにつながる」との思いに突き動かされたという。
ラミレスさんが慰霊碑の清掃を一人続けていることも、斎木さんを通じて鹿児島県遺族会に伝わり、ラミレスさん八十回目の誕生日の〇五年十一月十五日、遺族会から「二十一インチのカラーテレビ」が贈られた。高齢のため丘へ来れなくなった戦友・遺族らの謝意が込められていた。(酒井善彦)
◇
年間企画「慰霊碑巡礼」の第三部では、日本の遺族らがルソン島各地に建立した慰霊碑と、これら碑と隣り合わせで生きるフィリピンの人々の今をつづる
(2005.12.5)


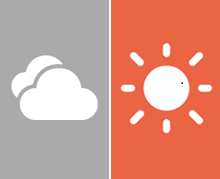


 English
English