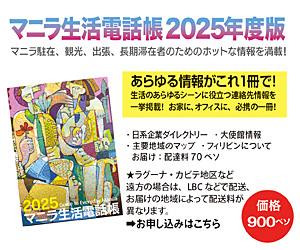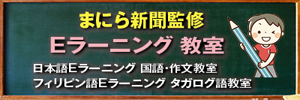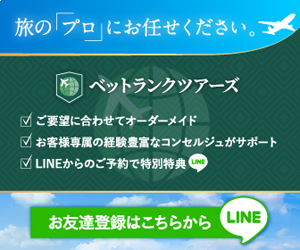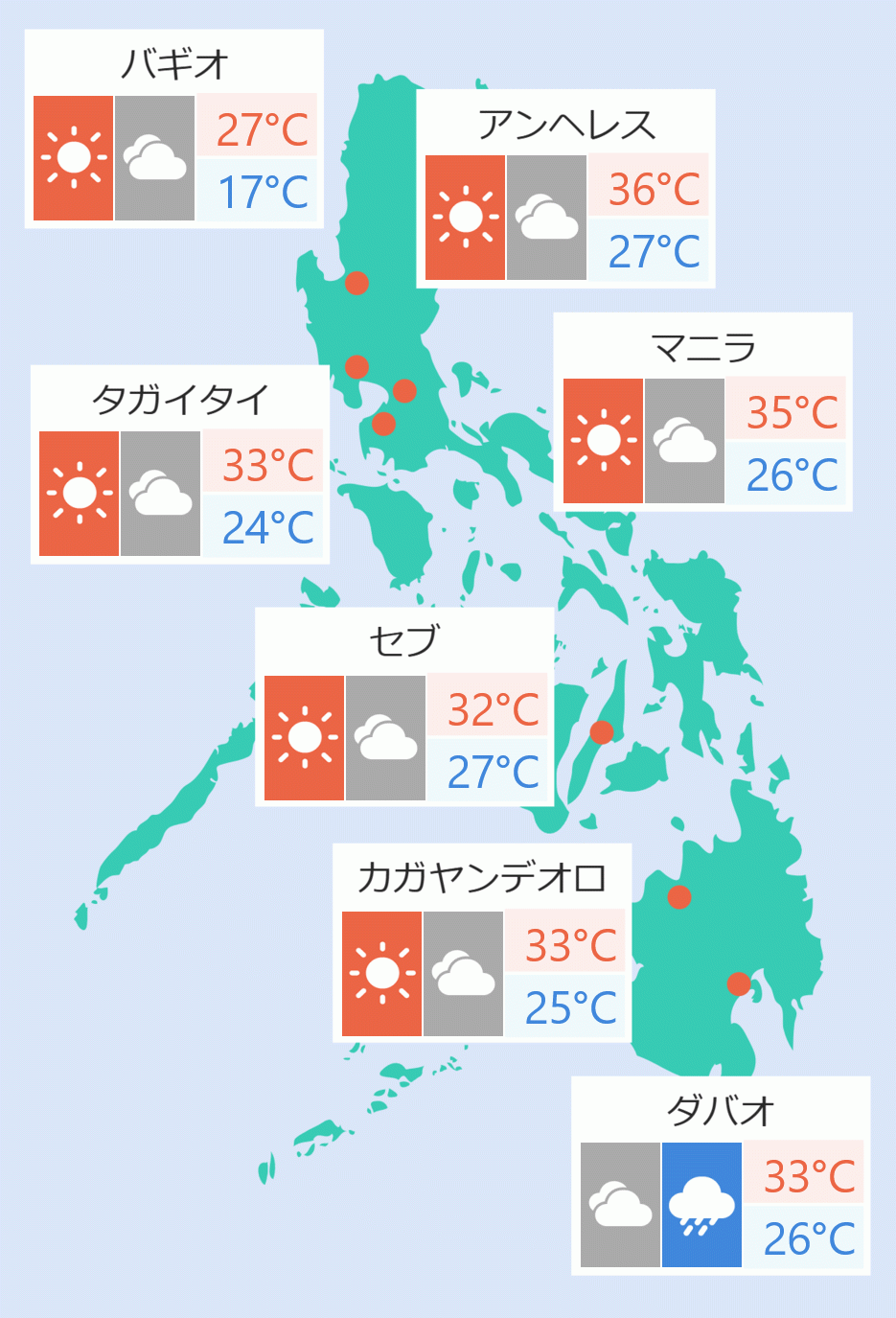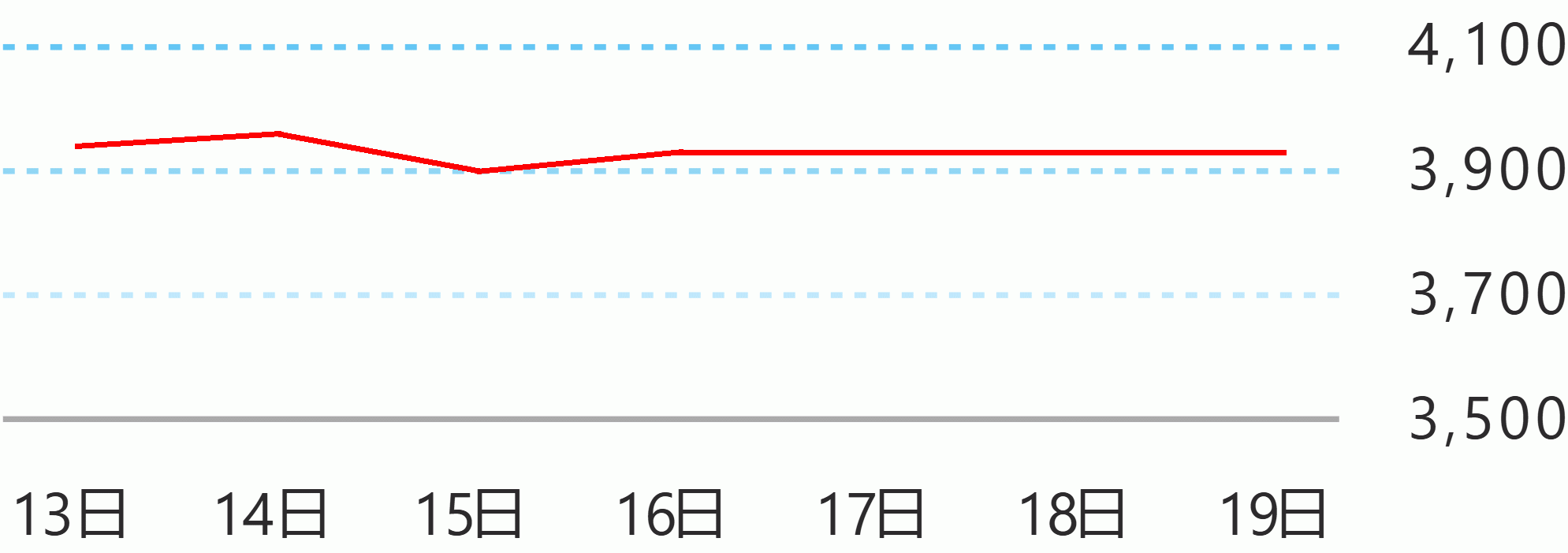今月末で帰任する国際協力機構(JICA)フィリピン事務所の坂本威午前所長。その3年の任期では、南シナ海の最前線で中国船と対峙(たいじ)する比沿岸警備隊(PCG)への97メートル級船舶5隻の追加に向けた借款の決定や、初の比日米首脳会談を踏まえた3カ国協力の取り組みなど、地政学的側面の強い案件形成も劇的に進んだ。そうした協力が平和的協力の原則に沿っているのかどうか、米トランプ政権の不透明性にどう対応するのかについて、坂本氏に率直に見解を尋ねた。
(聞き手は竹下友章)
―南シナ海の小競り合いの最前線にいるPCGへの協力を加速させているが、これはODAの平和的協力という原則から外れていないか。
全然外れていません。日本のODA(政府開発援助)は他国よりずっと手間をかけていて、案件の採択に向けた調査をするかしないかを決めるときに、開発協力適正化会議といって外部有識者の意見を聞く。そこでも厳しい意見も出るし、軍事的要素に使われないことを確実にするために、非常に神経を使っている。そもそも、98年にPCGは国防省から運輸省傘下に移管されている。うちが支援できるようにするために、明確に文民統制機関になってくれた。
岸田前総理は、23年11月の来比時にPCGも訪問した。出迎えたガバン長官は「多目的船調達を支援してもらって助かっている」といって、まず挙げたのは、油流出事故対応などの環境対策と、災害時の避難民救助・救援物資輸送の活用事例だった。本当に助かっていると。その次に、海洋状況把握(MDA)を説明していた。
これほどまでに、軍事協力と混同されないように、組織も文民統制に変えてるし、船のスペックにも注意を払っているし、軍事活用はしないと合意書にも書いてもらっている。
また、海上法執行能力強化の領域で重点的に協力しているのは、合気道のような逮捕術。武器を使わない。相手を傷つけずに制圧する技術。こうした思想・対応が基本として徹底されている。
―とはいえ、南シナ海の領有権争いの最前線で、日本ODAで調達したPCG船が中国の公船に衝突されて穴を開けられたりして、緊張が高まっている。
あれは向こうも賢くて、向こうも海警局なんです。だからグレーゾーンという。要は軍と軍が対峙すると本当に戦争につながりかねないから、海上法執行機関同士の対応としている。PCGも、最前線で戦うために行っているということではなく、管轄権内で環境汚染がないか、海難事故や救助の必要性はないか、法執行上の問題はないか、などということで巡回を行っている、という整理だ。実態として、中国勢力との対峙というのはあろうが、それは付随的に発生したことで、本来業務のメインではない。
―逆にそういう「付随的な事象」がこれからの支援の妨げになることはないか。
ないと思います。ないからこそ97メートル級の5隻追加の協力文書にも署名できた。油流出の対応も、天災時の救難も、活躍するのはPCGの船。その隻数がどれくらい必要かって言うと、領海線の長さに対する船舶数で比べると、PCGは日本の海保の10分の1くらい、中国と比べたらもう100分の1とかいったレベル感で、とにかく圧倒的に不足している。これは、海の安全を守り、海洋環境を保全するなどといった重要な開発課題に関わっており、しかも比は大事な国だから、これらも協力する。
―PCGの能力強化に関しては、激増した人員のスキルアップや、スービックの拠点作りに取り組んでいたと思うが、その最新情報は。
私がいた3年間でPCGの人員は3倍ぐらい増えた。新規雇用隊員をしっかり訓練できないと、せっかくの船舶のメンテナンスもできずにまともに動けないということも発生しかねない。まともに動けない、といったことは、実は他国の支援船舶で実際に発生している。だから、資金協力と技術協力をセットで行うというJICAの特徴は重要で、増員人員の相応の訓練や技能レベルアップなどにJICAは注力しており、これは、他のドナーとの差別化にもつながる。
次に、スービック拠点整備に関して言えば、今ある2隻の97メートル級多目的船をはじめ、運営・維持管理的にも、PCG保有船舶のために、やはり母港は必要。今は港湾公社から埠頭を借りているだけで、一度に97メートル級の多目的船2隻も停泊させられない。今後、同型船が計7隻になるので、ますます スービックの拠点整備の必要性が高まっている。
スービック拠点整備の協力に向けた準備状況のアップデートについて付言すれば、フィジビリティースタディー(実現可能性調査)を今実施中であり、近々の完了を期待している。
―なぜフィジビリティースタディーが長引いているのか。
もともとは、今年3月くらいで同調査を完了させようとしていたのだが、長引いているのは土地問題。具体的にはアクセス道路の用地取得が難航している。代案についても追加的に要検討となり、そのため時間がかかっている。しかし、質の高いインフラを作れるよう、着々と進んでいる。
―もう一つ地政学がらみの話だと、米トランプ政権発足後に米国際開発庁(USAID)が閉じられたり、ウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談で前代未聞のちゃぶ台返しが起こるなどした。バイデン政権下で推し進められた3カ国協力の枠組みにも急な方針転換のリスクや、既に被っている影響があると思うが、それにどう対応するか。
われわれが何をすべきかという観点から言えることは二つ。
まず一つは、予見不可能性のリスク、政策不一貫性のリスクが顕在化・先鋭化したことを踏まえて、「他山の石」的に、「日本は、ブレずに協力を継続する」ということがますます重要になった。かえって、「日本は信頼できる」というパーセプションを反射効果的・差別化的にフィリピン側に強く与える好機、とすら言える。昨今の情勢を踏まえて、なおさら、日本は愚直に、きちんと約束したことは守っていくべき、ということを、今まで以上に強く思っている。
もう一つは、事業の透明性・発信力を高め、世論の理解を広く得るべき、ということ。トランプ政権による「過激なUSAIDたたき」の背景に、いわゆる「フェイク情報」が出回り、世論もそれを踏まえてUSAIDたたきに賛同した、とも見られている。これは決して他人ごとではない。間違った情報に基づく間違った判断が発生しないように、われわれは透明性を高め、かつ納税者の理解を得なければならない。だから、これまでも対外発信に力を入れてきている。
現地広報も大事。現地で歓迎されない協力などいい結果を出さない。そこでまずは現地をちゃんと理解することが出発点。それには、メールや電話のデスクワークで仕事をした気にならず、対面で話をし、信頼関係を築き、現場に足を運び、現地での情報を取ってきて、ちゃんと意見交換をすること、こういう基本動作を疎かにしてはいけない。比政府、困難に直面する裨益者(ひえきしゃ)の方々、移転等事業影響住民、民間企業の方々に直接話を聞く。真摯に対応すると、必ず意は通じる。だから、JICAの評判はいいんですよ。
各国別のJICAに言及する現地報道の数ランキングみたいなものを本部がまとめているが、フィリピンは、全世界の中でだいたいいつもベスト5に入る。しかも、報道の中身も、ベタ記事も多くなく、サポーティブで充実している。比政府のJICAに対する扱いを知っているから、現地メディアも私にインタビューしたがるし、しっかりと記事化してくれる。
―3カ国協力に関連して、日米韓によるバンサモロイスラム自治地域(BARMM)の母子保健と、比日米サイバーセキュリティーの2件があったと思うが、今回どう影響を受けたか。
1月のUSAID業務凍結懸念発生後、国家経済開発庁(NEDA)のバリサカン長官が即座に記者会見を開き、USAIDの協力規模は大きくないからそんなに影響が大きくない、といった発言をした。翌週にはNEDAの次官がより鮮明に同趣旨を述べている。確かに、USAIDのフィリピンにおける協力規模や直接的な影響も限定的なのかもしれない。ただし、バリサカン長官発言の数日後に、パガンダマン予算管理相が、BARMMの母子保健といった重要事業もあるから心配している、早く戻ってくることを期待している、ということを言った。
もちろん、USAIDの業務が戻ってくることはフィリピンにおいても歓迎されるだろうし、JICAとしてもせっかくこぎつけた3カ国協力が元に戻って推進されることは望ましい。
ただ、複数国間協力の仕方には2種類あり、資金を拠出・持ち寄って一緒に事業を進めるジョイント型と、領域を分けてそれぞれで相互補完的に協力するパラレル型とに分かれるが、BARMMの母子保健やサイバーセキュリティーはパラレル型なので、JICAが進める協力ができなくなるわけではない。しかも具体的に動き出している日本と違い、米韓はこれからという、いまだ準備段階だったので、相互補完性の関係上、深刻な問題が発生しているというまでではない。基本的に、われわれはやるべきことを粛々と、かつ着々とやっていく。 (続く)





 English
English