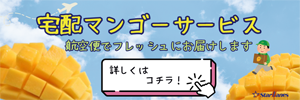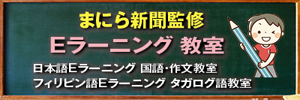ミンダナオ島最南・西ダバオ州ホセアバドサントス町から、海岸沿いに悪路に揺られること約3時間。南コタバト州に位置するジェネラルサントス市に到着する。先月中旬、ホセアバドサントス町で電気の通っていない日系人集落に太陽光装置を届けるプロジェクトを成功させたフィリピン日系人リーガルサポートセンター(PNLSC)の猪俣典弘代表、フィリピン日系人会のヘレン・エスコビリャ法務担当らが次に向かったのは、同市にある高齢男性の住む家だ。その男性は、戦前ホセアバドサントス町に移住した日本人・羽渕清五郎の12人の子の一人、羽渕セルヒオさん(85)。ワークショップ実施1週間前のタイミングで、無国籍状態にあったセルヒオさんへの日本国籍への就籍が家裁から認められたため、この機会に合わせての就籍通知となった。通知を受けてセルヒオさんはこの日、二つの涙をこぼした。 (竹下友章)
父が移住し、開拓したホセアバドサントス町で生まれ育ったセルヒオさん。現在は高齢のため歩行困難になり、ジェネラルサントス市に暮らす息子一家に引き取られている。「グッドニュース」。そう切り出したエスコビリャ法務担当が、日本の司法によって日本人だと認められたことを伝えた際、セルヒオさんは涙を浮かべ、こう喜びを語った。「約80年もの間、いつか日本人だと認められる日を夢見てきた。あまりにも長い時間待ち続けたが、それでも希望を失わなかった」――。
▽10年間の逃亡生活
セルヒオさんの父・清五郎は戦前にダバオ地域の開拓を主導した太田興業で働き、先住民マノボ族の女性と結婚。土地を取得、開拓し、現在のホセアバドサントス町で豊かな暮らしを築いた。そんな父は戦時中、比米軍に連行され、処刑される。
父の死後、母に連れられきょうだい2人と共にセルヒオさんは山に逃げた。戦中・戦後の日本人狩り、日本人への迫害から自分たちの命を守るため、山での逃亡生活は10年にも及んだ。
「山の中を転々とし、大きな木を探してその下に宿った」「物乞いしなければ、バナナを食べられなかった。物乞いしなければ、キャッサバを食べられなかった」――。逃亡生活は、飢えだけでなく、人の尊厳も奪う過酷なものだった。
一度山を降りた後も苦難は続く。「山を降りた後に差別を受けたか、その後の暮らしはどうだったか」との質問に、セルヒオさんはこう語った。「山を降りた後、(町長をしていた)ジョン・ジョイス氏に保護を求めたとき、食事だけ与えられたが、『あなたが日本人だと分かったら、(復しゅうのため)追ってくるものがいるだろう。他の人が来たら、すぐ逃げなさい』と言われた」「父の土地も接収されて他人の所有物になっていた」「食べ物もない。着るものもない。学校にも行けなかった」――。
その後も農業に従事しながら厳しい暮らしをしてきたセルヒオさん。再び目に涙を浮かべ、声を詰まらせたのは、亡き父への思いを語ったときだ。「もし父が死ななければ、私の人生はこんな惨めなものではなかっただろう。父が死ななければ、学校に行けただろう。父が死んだから、われわれの生活はいまだにこうだ」――。息子のロシノ・ハブチさんによると、セルヒオさんを病院に連れていきたいが、資金難のため診療させられていないという。
「私の父は日本人。だから私も日本人だ」と明確に自分のアイデンティティーを持つセルヒオさん。日本人として認められたいという積年の願いは、「父に守ってほしかった、父に救ってほしかった」という、決して満たされることのなかった幼少期からの思いと分かちがたくつながっている。
そして「自分の子孫たちに(日系人として)日本に行く権利を遺(のこ)してやりたい」との希望には、戦後長らく極貧の暮らしを強いられた多くの残留日系二世と同様、「せめて子孫の世代には、日本人の子孫としてゆたかな暮らしを手に入れてほしい」という、叶わなかった自らの願いを子に託す親の心が見て取れる。
▽「私たちは忘れられた」
羽渕清五郎の12人の子どものうち、国籍回復ができたのは、昨年就籍が認められたヒチさん(82)とセルヒオさんの2人だけだ。戦争を生き延びたきょうだいも多くいたが、日本人として認められるという願いが叶うことなく亡くなった。
「国籍回復まで79年かかった。遅いと思うか」。この問いにセルヒオさんは、「遅かった。他のきょうだいはみんな死んでしまったから。たぶん、日本は私たちのことを忘れてしまっていたのだろう」と静かに語った。
日本人であることが認められず亡くなったセルヒオさんのきょうだいは、ただ思いを果たせなかっただけではなく、その子孫が日系人の資格で訪日・就労することも困難となった。このような現状は、日本政府全体としての取り組みの遅れだけでなく、フィリピンの「同胞」に対し日本国民があまりに無関心でい続けたことの結果でもあるだろう。(続く)


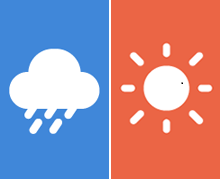


 English
English