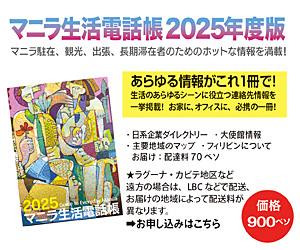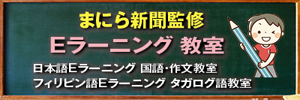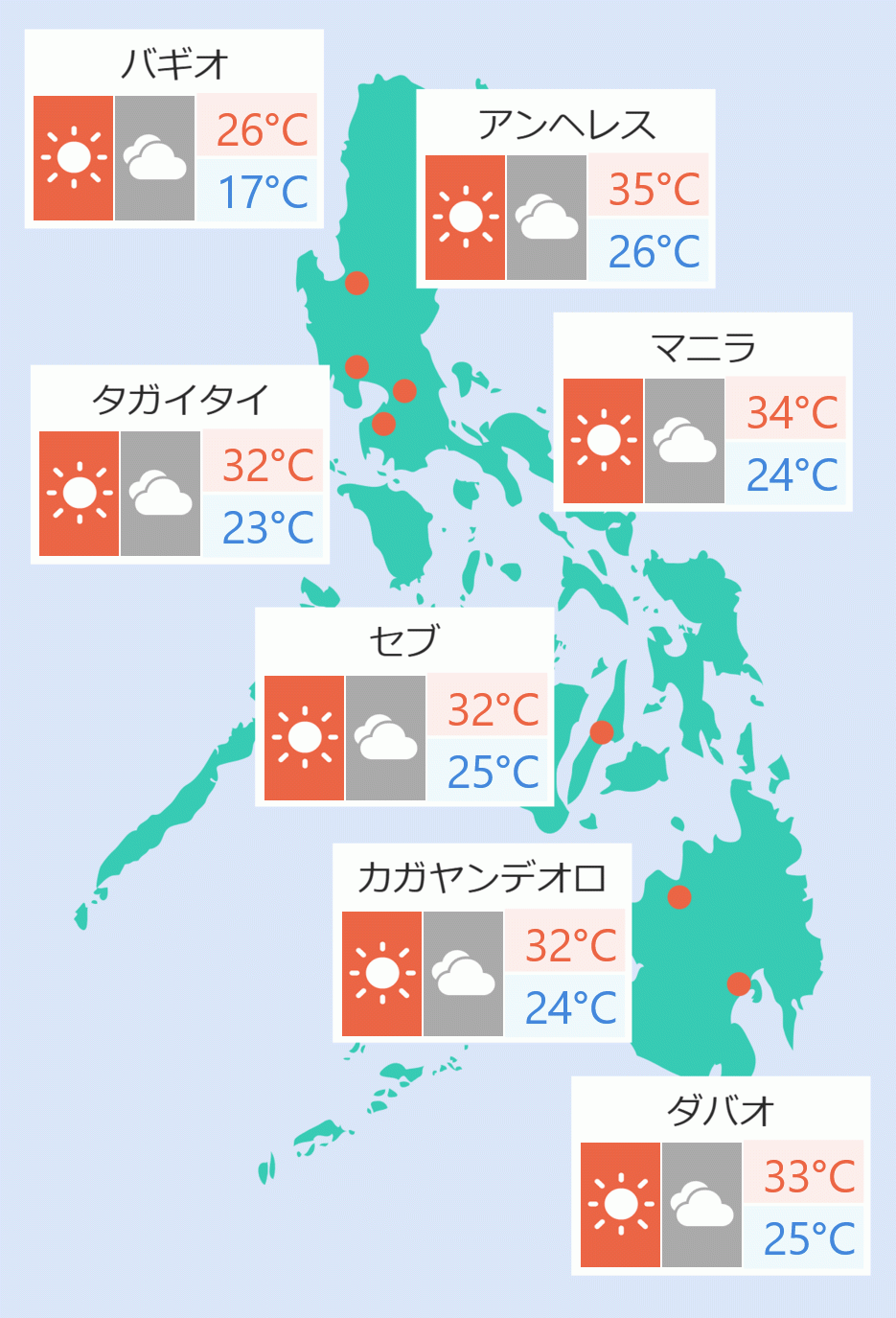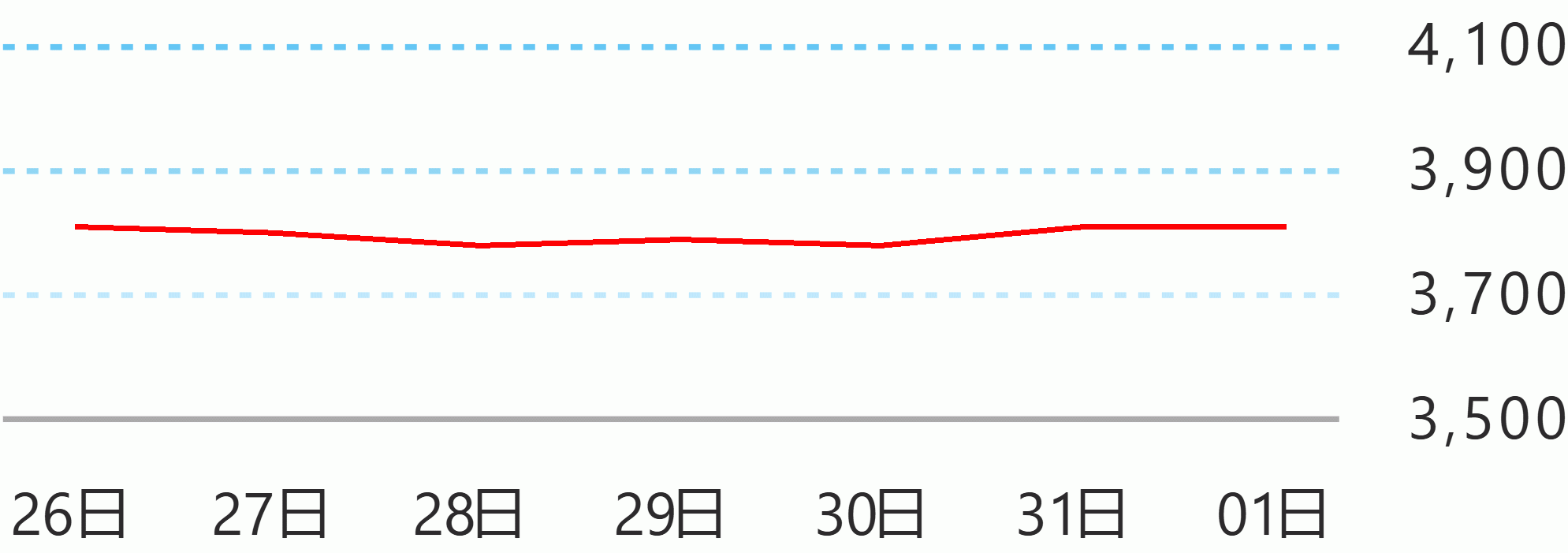首都圏マカティ市の日本国大使公邸で26日、国際協力機構(JICA)の海外協力隊員やその関係者らを招待したレセプションが催された。JICAフィリピン事務所からは協力隊員9人の他、坂本威午所長や竹中成文次長、同事業に携わる調整員らも出席した。
一同は大使公邸で、公邸料理人の料理に舌鼓を打ち、庭で記念撮影や植物を鑑賞するなど、都会の中での憩いの時間を満喫。2023年度2次隊として着任したばかりの4人の隊員の自己紹介も行われた。また、2022年度7次隊として、すでに1年近く活動している先輩隊員1人の活動報告も行われた。
島根県の消防士で、防災・災害対策の方面で現職参加となる山本士温隊員は、ベンゲット州ラトリニダッド町役場に配属となる。小学校での防災教育や救急法の指導などを行なう予定だが、海外は今回初めてだという。「フィリピンで見るもの食べるもの全てが新鮮で、楽しい日々を送っている」と力を込めた。
学生時代に1年間のガーナ留学を経験し、農協で3年間働いた兵庫県出身の木下剛志隊員は、「野菜栽培隊員」としてサンバレス州内の大学への派遣を待つ。大学では農業指導や教員との共同プロジェクトの実施を計画している。一週間の視察を経てすでに「日本のものを改善に役立てられる点や、日本に持ち帰って日本の農業改善に活かせる点もある」と気づきを得たことに触れた。
▽隊員による活動報告
また、東ネグロス州ドゥマゲテ市のドゥマゲテ酪農共同組合で家畜の飼育支援を行ってきた工藤祥平隊員(31)は、1年近くの活動を報告。従業員6人、酪農家約50戸が加入するという同協同組合で、酪農家が生産した牛乳の加工や販売を実践してきた。主な活動目標として、①酪農家の酪農技術の向上②生乳生産量の増加③生乳や製品の品質の向上――を挙げ、その結果は「酪農家の所得向上」につながることを強調した。
青森県弘前市が出身で、元々「人より牛と過ごした時間の方が長かった」と笑う工藤隊員によると、現在、比は国内の生乳自給率が1%と少ない。そのためオーストラリア産、ニュージーランド産など大半を輸入に頼っている。個体当たりの1日の生乳生産量も7~8キロ(日本では20~30キロ)と少なく、廃棄乳も生産量の約10%に及ぶことから、改善が求められる点として挙げた。
比農務省は現在、家畜と酪農拡大プログラムを掲げ、搾乳牛の頭数と牛乳の生産量10%引き上げを策定。そうした課題の達成に向けた活動として、工藤隊員は①所得向上につながる効率的な乳製品の製造、②酪農家の飼養環境の改善、③生産性の高い効率的な飼養管理の実践――を柱に据える。残り1年間の任期への抱負としては「能動的になること」「(酪農家との)コミュニケーションの強化」を掲げた。
▽多文化共生社会へ
越川和彦大使はかつて4年間、JICA副理事長を務めた経験から、海外協力隊事業への思い入れも人一倍強い。自身が20歳の時に海外を回った経験から、国内も含め、異なった環境に一度身を置くことの大切さに触れた上で、「日本の若い人が内向きで、外に出ないと言われる中、協力隊として海外に出たことに敬意を表する」とたたえた。
同副理事長時代に、中小企業支援の一環で全国都道府県を回った際、「どこに行っても外国の人が一所懸命働いていた」と越川大使。農業や廃棄物処理、製造業はもとより、全ての業種に外国人の方が入っている」実情を目の当たりにした。そして、人口減少へと向かう日本にとって、多文化共生社会の達成が欠かせないとの思いを語った。
また、協力隊など海外経験者が「地方自治体に入っていって、労働者の人々と地元コミュニティーとの意思疎通の橋渡しになれたら」との期待も込めた。一方で、大使は外務省国際協力局長だった時代、当時は帰国した協力隊員の就職先に気を揉んだが、「もはやその必要性はなくなった。日本社会がどんどん変わり、社会や国にとって必要な人材になった」との見方を示した。
さらに大使は、能登半島地震後に見られる「ボランティア活動の浸透は、非常に良いことだ」とし、元協力隊員の団体による、長年の被災地域での活動を紹介。「みなさんの帰国後の貢献も楽しみにしている」との希望も伝えた。(岡田薫)





 English
English