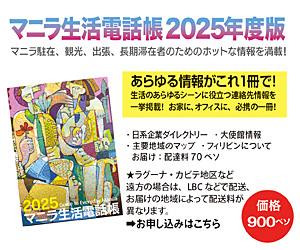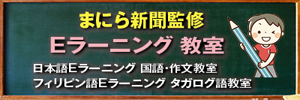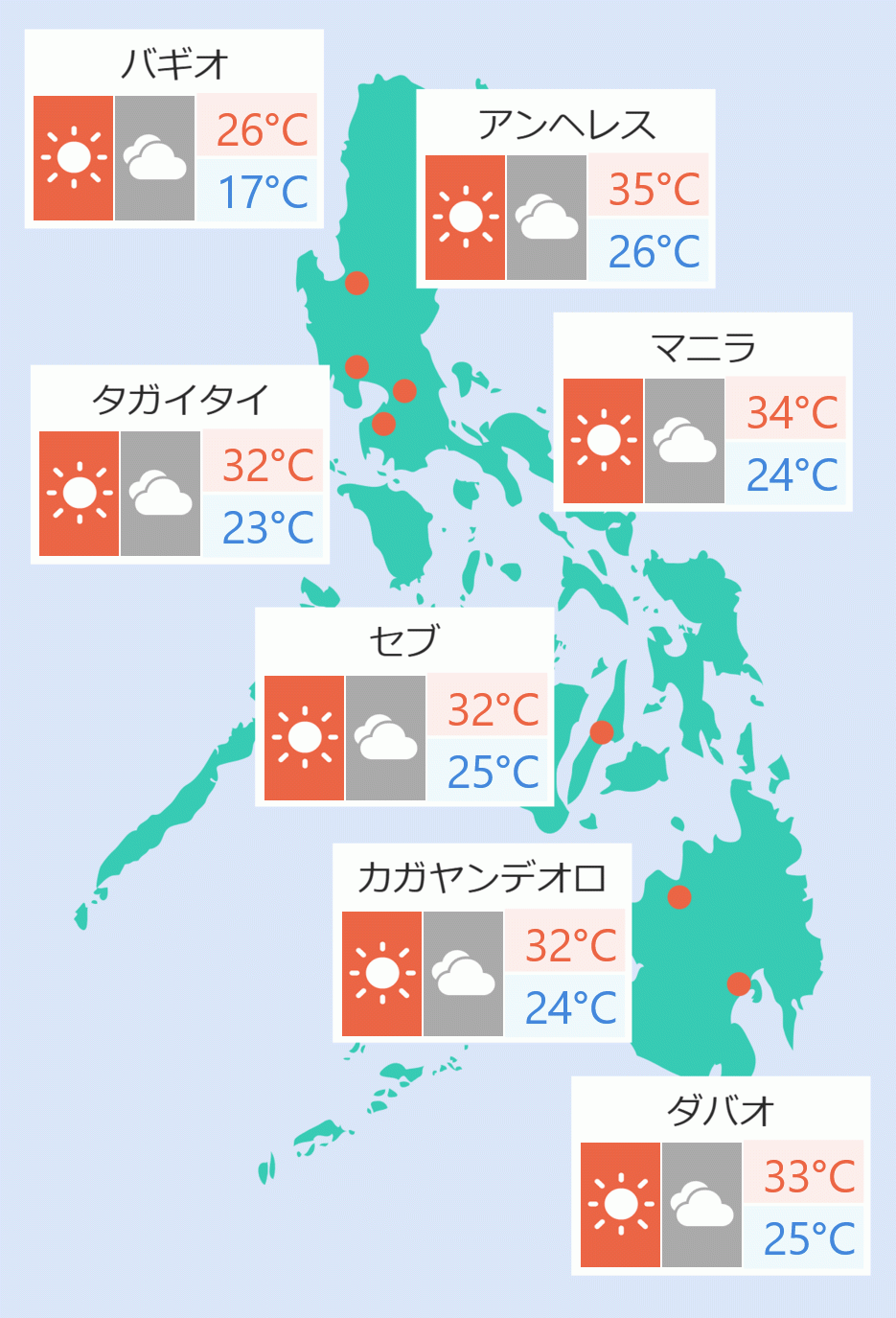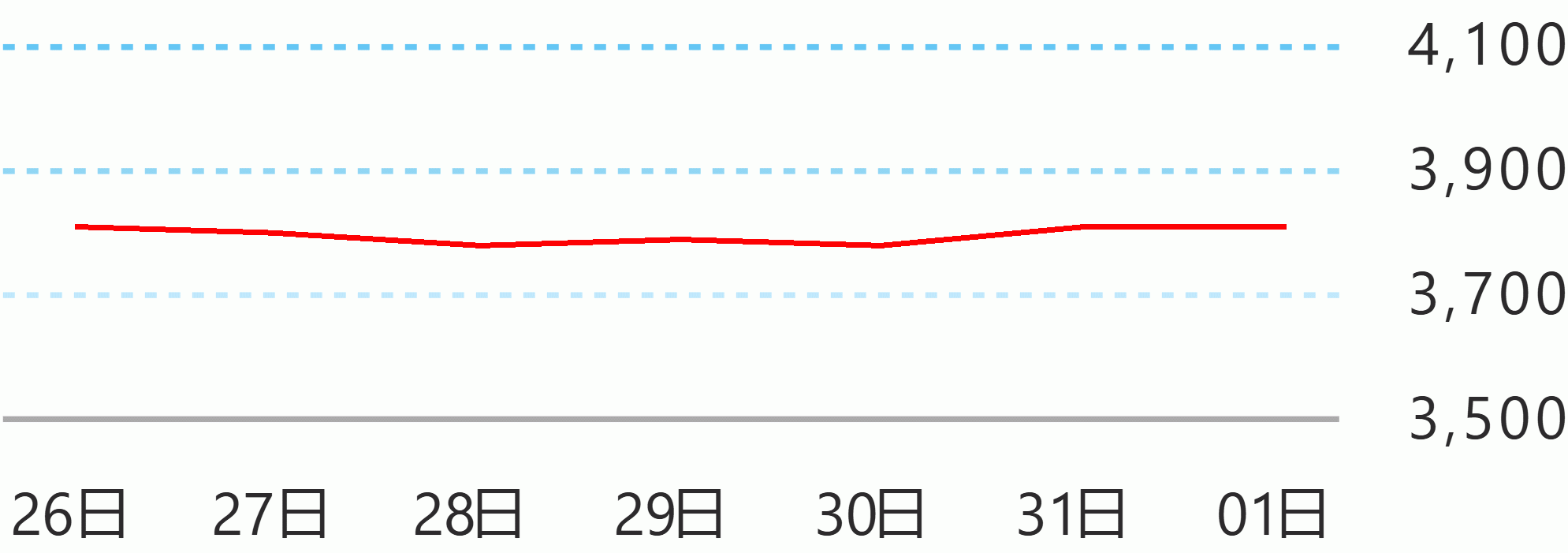比に関係のあるジャーナリストや評論家から絶賛を博した映画「世界は僕らに気づかない」(2023年、英名アングリー・サン)が2月から始まる日本映画祭(国際交流基金)を通じ首都圏、セブ、ダバオなど全国6カ所で無料上映される。映画に造詣の深い国際交流基金マニラ事務所の鈴木勉所長も「日本人・比人ともに見るべき映画」と広報に特に力を入れる本作。日本映画祭での上映を前に、同映画の脚本・監督を務めた飯塚花笑氏がまにら新聞への単独インタビュー(遠隔)で、作品に込めた意図と近年のLGBTQ(性的少数者)問題への見方について語った。 (聞き手は竹下友章)
▽たくさんいる多重マイノリティー
偽装結婚を通じて日本に渡航しフィリピンパブで働く母の子として、母子家庭で生まれ育った主人公の純悟(堀家一希)のセクシュアリティーは同性愛者。彼は複数の意味でマイノリティー(少数派)に属している。この人物像は、飯塚監督が当事者の比人2世、偽装結婚を通じパブで働いている比人女性たちへの丹念な取材に基づき形成された。その中には2世で、かつ同性愛者という人もいた。
「映画が公開されると、LGBTの方もたくさん見ていただいた。主人公の純悟と同じで2世かつゲイという人もこんなにいるのかというくらい名乗りを挙げてくれた」。自身もトランスジェンダーである飯塚監督は、多重マイノリティーが映画上の設定でなく、実は現実にたくさんいる人々だと強調する。
血縁上の父を知らない主人公の純悟は国籍問題も抱えているほか、映画には他者に対し性的欲求・恋愛感情を抱かない「アセクシャル」の女性も登場するなど、本作では多様性に対して意識して光が当てられている。それに対し、日本のマジョリティー(多数派)の反応はどうだったか。「日本公開前の映画祭巡りの時の日本の映画人の反応は『設定を詰め込みすぎて闇鍋みたい』というものだったが、一般公開後も『複雑』『難しい』という声が多かった」と監督は振り返る。「2世の当事者の方も、私たちも、決して複雑ではないとは思うのだが、こうした反応の背景には、日本に『移民』という概念が浸透してないことがあると感じた」。
▽少数派の視点に多数派を連れてくる
多重マイノリティーへの生きづらさを正面から描き出す本作。だが少数者の生の苦しみを描く純文学的作品というよりは、笑いあり、心温まる人情あり、観客を幸福な気持ちにするハッピーエンドありのエンターテインメント作という形式をとっている。これは意図してそう作ったという。
「マイノリティーとして生まれ、映画作りを仕事にしている私の使命は、マイノリティーの視点にマジョリティーを連れてきて気持ちを共感してもらうことがだと思っている」と監督。「日本社会にはマイノリティーは自分がそうであると明かしにくい状況が存在し、可視化されにくい。それで『少数者がそこにいるのに、いないかのように認識される』ということが起こる。映画は、ある意味生きた人間を眼前に登場させる機能があり、少数者の気持ちを多数派に伝えるのに優れた手段でもあると思っている」
本作は、差別される少数者が差別する多数派や社会に対し異議申し立てを行うという形式は取っていない。その代わり、母子関係・恋人関係という、人種やセクシュアリティーを問わずに共感できる人とのつながりが軸となって物語が展開される。「理解してもらいたいと思っている側が拳を振り上げてると、それに対して同じくらいの力で反発がある」という同監督。この作劇には、より普遍的な部分にフォーカスし、多数派にも共感の輪が広がるようにとの意図が込められているという。
「例えば主人公が、俺はこんな目にあって、被害者で、俺が正しいのになんで分かってくれないだと、常に正論を振りかざす男だとしたら、受け入れてもらえない。また、主人公が清く正しくて、教科書のようなことを言っているっていうパターンも考えられたが、こういうのを作っても来た人は映画を見に来た意味がない」。そうして誕生した主人公・純悟はあえて「性格を悪くした」。「被害者意識が強すぎて人を傷つけることもあるし、良いところもあれば悪いところもある。そういう人間として当たり前にある色んな面を描いた」。
▽摩擦は前進の過程
性的少数者を巡っては、自治体レベルの同性パートナーシップ条例の拡大、LGBT理解増進法制定、経産省トランスジェンダー職員に対するトイレ使用制限への最高裁による違憲判決など、性的少数者の権利が拡大する方向へ進む。一方で、自民党の杉田水脈衆議院議員が保守系雑誌への寄稿で「LGBTには生産性がない」と主張し(2018年)、荒井勝喜元首相秘書官が「(同性カップルを)見るのも嫌だ。同性婚を合法化したら日本を捨てる人も出てくる」(2023年)と発言するなど、性的少数者に対する嫌悪や警戒も表面化している。
こうした反LGBTの言説について、飯塚監督は「国政にあずかる人々の発言だから問題視されたが、当事者からは以前から学校の先生だとか、校長先生だとかから同趣旨のことを言われたという声は聞いていた」と語る。「LGBT問題への取り組みが進むとこういう摩擦が発生するのは既定事項。一つ一つ議論されて、少しずつ前進して行くということかと思う」と冷静だ。
また、ローマ教皇が昨年、同性婚への祝福を認めると宣言したことについては、自身もクリスチャンの親族から自分のセクシュアリティーについて「考えを改めるよう」一方的に説得を受け、最終的に関係を遮断せざるを得なかった経験を明かした。「取材した人でもまさに比人2世で同性愛の方が、カトリックのお母さんに同性愛者であることを打ち明けたとき、叩かれたりするなど苛烈な反対に遭っていた。だから、こうして権威のある方から正式に承認のお触れがあることはとてもうれしいこと」と述べた。





 English
English