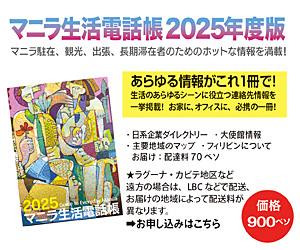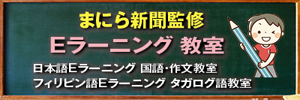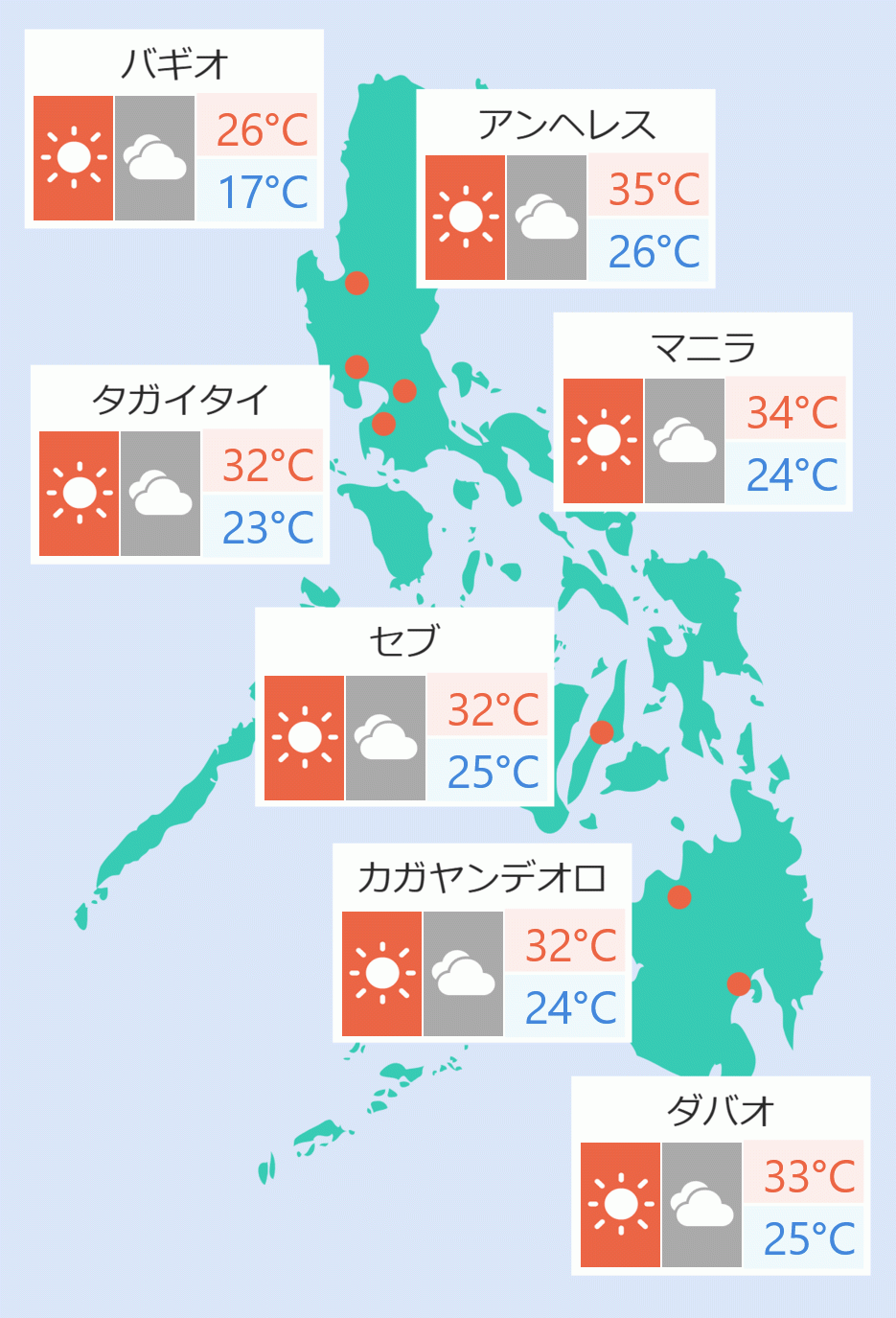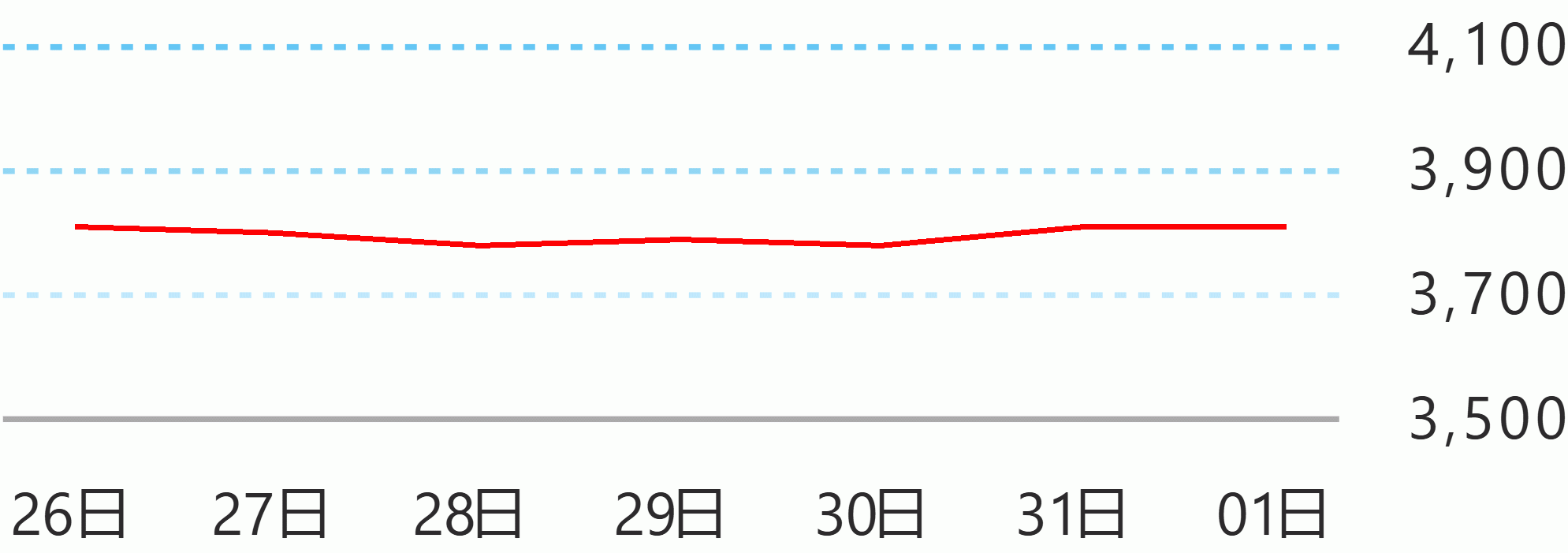首都圏ケソン市のフィリピン大ディリマン校でこのほど、「北・東・東南アジアの移民の流れに関する国際ワークショップ」と題した、同大アジアセンターと東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所による比日研究者間のアジア研究学術交流が行われた。同センターのジョセリン・セレロ准教授と東京外語大同研究所の床呂郁哉教授が共同企画者。床呂教授が司会進行を務め、広島大学人間社会科学研究科の長坂格教授、早稲田大学国際教養学部の陳天璽(てんじ)教授を発表者に迎えた。比側はアジアセンターのミシェル・パルンバリット、ノエルクリスチャン・モラティリャ両准教授が発表を行った。
長坂教授は1992~93年にかけてアジアセンター(旧校舎)で学んだ経験を持ち、主に比人の国を超えた移動について20年以上研究を続けてきた。ワークショップでは新型コロナ禍が海外比人就労者(OFW)に及ぼした影響を、日本や他国の事例から発表した。
英国で看護師をしているOFWの体験として、一度に500人の渡航枠制限が設けられたこと、看護大3年だった比人学生が、病院勤務に就く選択肢を与えられ、「雇用機会」に繋がった事例などを伝えた。また、国連事務総長が「ウイルスとヘイトへの社会的免疫の強化」を呼び掛けるも、各国で「安全」を名目に、差別的政策が多く実施されたことにも触れた。
日本政府のコロナ時の水際対策といった政策が「健康な国家を外部の脅威から守るイメージを強化する役割を担った」と指摘。また、台湾では外国人労働者が寮からの外出を禁じられ、香港ではコロナ検査が外国人だけに課された事例にも言及した。
一方で長坂教授は、コロナ禍が外国人労働者にとって「機会の提供」やコミュニティーにおける貢献や認知のきっかけとなった側面にも触れた。その例として台湾やマレーシアでの不法就労者を含む外国人労働者全般への無料ワクチン提供、さらに受け入れ国において「使い捨て」とされてきた外国人労働者が、危機下での社会的基盤の最前線の担い手として、認知されるようになった点も強調した。
▽国と国のはざまで
横浜・中華街で生まれ育ち、「無国籍」(新潮文庫)の著者で、NPO無国籍ネットワークの代表も務める陳教授にとって、今回の訪比は2009年にNHKの比における無国籍の人々を扱ったドキュメンタリー取材で訪れて以来。それ以前にも日本へ渡る比人エンターテイナーの研究などで来ていたという。
自らが当事者である「自己エスノグラフィー」の観点から研究してきた陳教授によると、世界に無国籍者は1200万人いると言われるが、国籍を持たない人を探すこと事態難しく、国連統計も急増するなど変化が大きい。
現在102歳で横浜に住む陳教授の父親は、中国・旧満州のハルピンで生まれ、第二次世界大戦や国共内戦を経験。共産党の迫害を受け台湾へ逃れた。そこで中国・湖南出身の陳教授の母親と出会い、やがて一家は日本へと移住した。
1972年に中国と国交正常化した日本は、台湾と国交断絶。両親は生まれたばかりの陳教授を「無国籍」として育てることを選択した。陳教授は16歳で外国人登録をしており、日本では「永住権を持っていたが、国籍は無国籍」と明かす。92年に旅行先の比から、台湾の親戚を家族と訪ねた際、陳教授だけ入国できず、1人日本へ帰国。そこでも「ビザを更新していない」と入国拒否に遭い、パスポートが無効となり空港ターミナルに閉じ込められた男性を描いた米映画「ターミナル」以前に同じ経験をしていたことを振り返った。
念願だった国連での仕事は「無国籍」を理由に断られ、ハーバード大で無国籍について研究を始めたという。陳教授はまにら新聞に「法的に国籍を与えれば、その問題は終わりだと思われがち。でも実際には別のアイデンティティーや悩みも持つ」とし「無国籍をネガティブに捉えるのではなく、人間らしさ、国籍の有無に関係なくその人自身に価値があるのだと思ってもらえたら」と語る。
また「国籍がある以上、無国籍者は発生する。無国籍を無くすというより、国籍そのものを考えなければ」と陳教授。「フィリピンと日本の間で生まれた子が、どちらかを選択しなければならないのは、どっちも私なのにどうしてという気持ち」であり、無国籍者に「日本国籍をあげれば日本人になれるかというと、それまで生きてきた人生がある。そうした無知が差別を作ってしまう」とも指摘した。(岡田薫)





 English
English