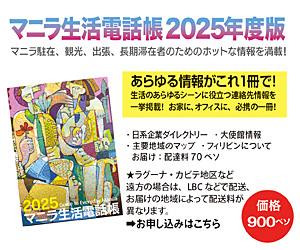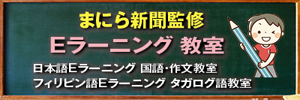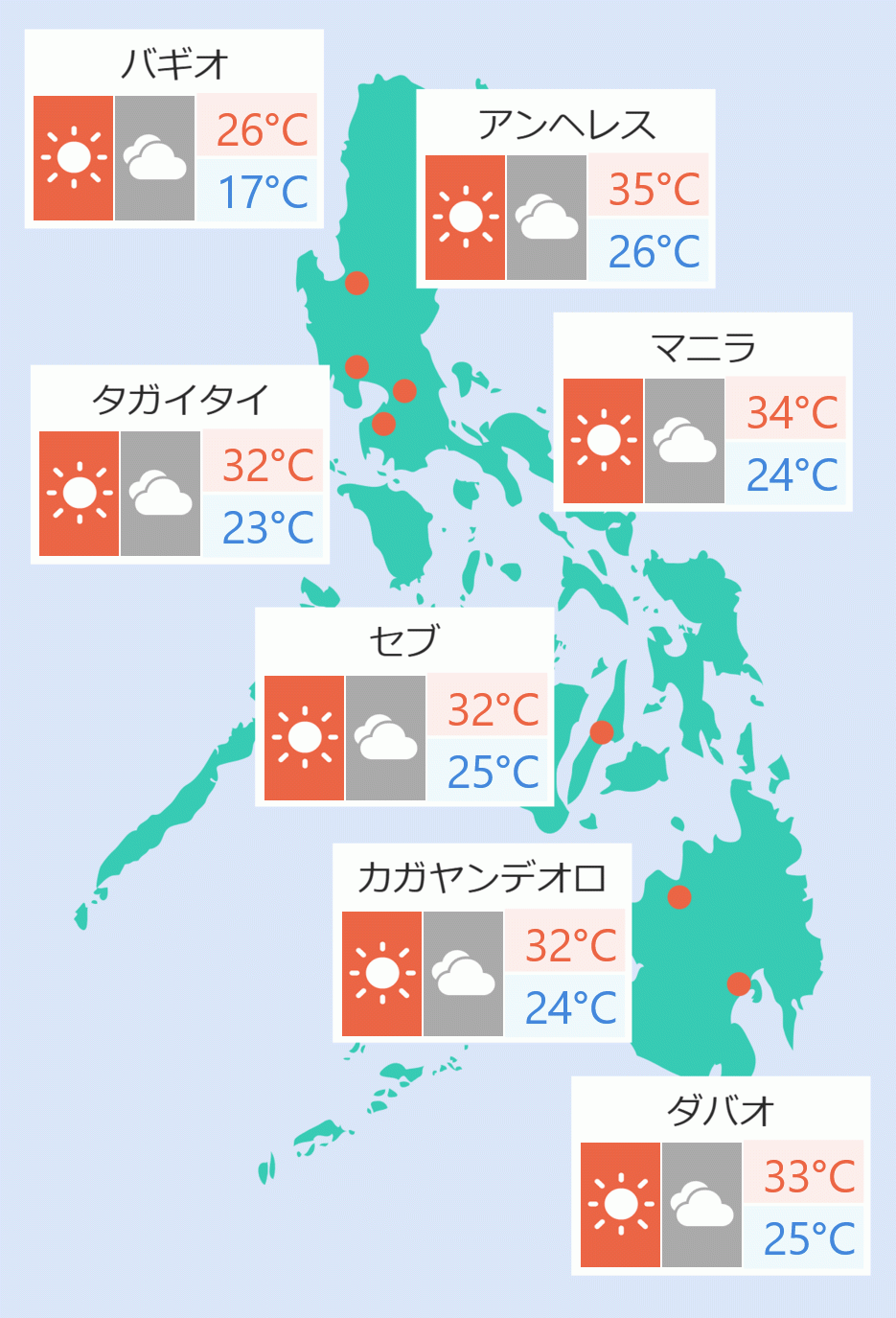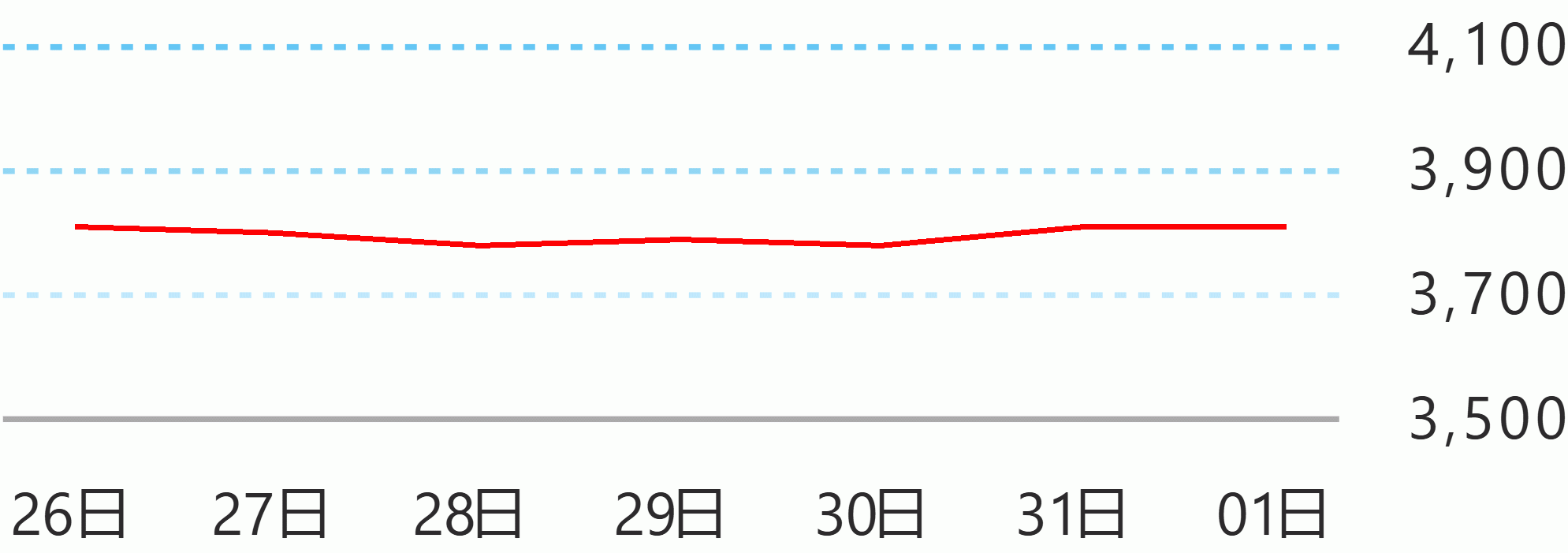ダバオ市の中心市街地から車で約1時間。かつての日本人地区・トリルのバショウに囲まれた道を歩くと瀟洒(しょうしゃ)な一軒家が見えた。中に入ると、同居する親戚に手を引かれてリビングに出てきたのが田中愛子さんだ。田中さんは、日本語の話せるダバオ残留日本人の最後の語り部とされる人物。2016年には、天皇皇后両陛下(現上皇后両陛下)のご訪問時に謁見(えっけん)したこともある。
▽豊かだった戦前
田中愛子さんは昭和6年(1931年)生まれの91歳。父吉郎、母アリガンの間に8人きょうだいの第4子として生まれた。母はバゴボ族のクラタ支族出身。父は大正元年(1912年)生まれの熊本出身。移住後は太田興業と並ぶ勢力を持っていた古川拓殖でアバカ(マニラ麻)栽培に従事していたが、母との結婚後はバゴボ族から土地を借りトリル地区バラカタン集落で自分たちの畑を持った。
「父は日本の戸籍に登録してくれた。こちらで生まれたので、教会でも洗礼を受け登録された」という愛子さん。幼少期は「何も不自由なし」。太田興業による対日貿易により「かまぼこも漬物もミソもみんなあり、日本と同じ食事だった」。
田中家では「子どもを日本人として育てる」というのが方針。家では日本語で通した。若くして結婚した母も日本語を話したが、それは「父から覚えた熊本弁。『ほんに』『どげんすると』なんて言っていました」。
▽銃後の徴用
そんな生活も太平洋戦争が始まると一変する。
1941年12月、愛子さんが10歳の頃に日本の攻撃が始まり、年末に日本軍上陸。現地人・比軍は山に避難しゲリラになった。輸入もなくなり、肉はブタやニワトリを育て、野菜は家庭菜園で作る自給自足生活に。みそも麹(こうじ)から作った。「全く昔の豊かさが崩れてしまったの」と愛子さんは振り返る。
日本統治下では各家庭の父親や男子は徴用された。田中家では父吉郎、長男吉継が軍に協力。目と足の悪い父は、軍人用の草履やカゴの製造や畑仕事の要員として、吉継はトラック運転手として協力した。
愛子さんもダバオのサンタアナに作られた兵器廠(しょう)に徴用され、装備品輸送の電話係をすることになった。カガヤン地方などの各駐屯地から弾薬や機関銃・大砲をどれくらい送れといった連絡を受け持った。無給だった。
大戦末期の45年4月ごろ、兵器廠から「来週は出勤不要。日曜に小学校で指示を出す」と言って帰された。日曜日に小学校に集まると避難指示が出た。家に帰ると母は既に知っており、避難中の携行食として大豆を炒(い)っていた。子どもたちはそれぞれ自分の食料を背負い夜中にタムガン山を登った。
移動中、昼は動かず、夜になると「そろそろとまた出かける」。別行動だった父は山中でつえを頼りに避難しており、山中の滞在先で合流できた。
▽終戦と父の「戦死」
終戦の日、米軍の航空機によって終戦を告げるビラがばらまかれた。それを歩けなくなった父に読んで聞かせると、父は「お前らは俺を置いて出て行け。お前たちが出て行った後は手りゅう弾で死ぬ」とどなった。「天皇陛下に命を捧げる」とかねてから言っていた母アリガンは「共に死ぬ」と懇願した。
そんな母に父は「違う。お前は一人でも子どもを育ててくれ」と譲らず、「アリガン、子どもたちをしっかり育ててくれ。頼むよ」と繰り返し言い聞かせた。母と愛子さんたちは泣きながら父を残して下山する。
日本軍と行動を共にしていた兄・吉継はうわさを聞きつけ翌日父の元を尋ねた。兄の話だと、その時父は湿って爆発しない手りゅう弾をなんとか起爆させようと石に打ちつけていた。既に歩けず、牛に乗せようとしても落ちてどうしようもないため、その日は他の避難民のいるところに置いて軍に戻った。翌日戻ったら亡くなっていた。
皆疲弊の極みにあったので、遺体は浅く掘った穴に埋葬し、兄は父の遺髪・遺爪を持ち返った。愛子さんに父の死因を尋ねると、しばしの沈黙の後「戦死ですよ」と険しい表情で一言。
山を降りると米軍キャンプに保護され、収容所に搬送された。米軍の対応は優しかった。収容所は「柱が8本くらいある広いテントが400以上あり、一つのテントに10人くらい住んでいた」。食事はチーズやコンビーフなど米軍食。十分配給されたが、日本食で育ち、長く十分な食事をとっていなかった避難民には合わずみんな腹を下した。
収容所の生活が2カ月も経ったころ、日本への送還が始まった。収容所のオフィス代わりのテントで面接があり、母の番が来たとき、米軍の担当者から「日本に戻るか、比に残るか」と聞かれた。母は「主人がいないから、行っても頼る人がいない。だから私は残る」と言った。
当時19~23歳になっていた2人の姉と兄は日本送還が決まった。当時14歳だった愛子さんも、日系米国人とみられる通訳から、「あなたはもうすぐ15歳になるけれど、日本に帰るの?」と聞かれた。その時母は泣きながら「愛子は残して下さい」と懇願。愛子さんと下のきょうだいは比に残ることになった。
▽日本人の子は殺す
「日本人の子どもは敵の子ども。日本人の子どもは全部殺すというのがゲリラの命令」。元の家の周りはゲリラが多く、帰宅を止められた。その時、一家をかくまってくれたのがバゴボ族タガバワ支族のマトゥテ村長だった。マトゥテは日本人に土地を貸しながら仕事を手伝い豊かになった人物だという。
1947年になってやっと弟・妹らと学校に再び通えるようになる。ただ通い始めると、「日本人を授業に参加させるな」との生徒からの声が出、きょうだい4人で黒板の前に立たされた。
さらに、下校時襲撃するため待ち伏せしている人がいると近所の人から忠告された。これを聞いたマトゥテは「このままでは危険だから、私の息子と一緒になりなさい」と言い、17歳のころ結婚する。
「生きるための愛の無い結婚。結婚前は夫婦2人で学校に通えばいいと言われたけれど、結婚したらそんな余裕はなかった。だまされたのね」。そんな夫は「口数が少なくとにかくまじめ」。父から譲り受けた土地で換金食物を栽培し「普通の家庭よりいい暮らしだった」。夫婦は10人の子宝に恵まれ、何人かは日本国籍を選んだ。
その後、70年代から始まった日本慰霊団・墓参団の通訳を引き受け、日系人組織化にも携わった愛子さん。孫の世代は比日を股にかけ活躍する。愛子さんは戦前の教育をしのばせる上品な日本語で「ダバオで当時を知っている方々は次々亡くなり、残っているのは私だけ。今記録に残さないと失われてしまう」と語った。(竹下友章、続く)





 English
English