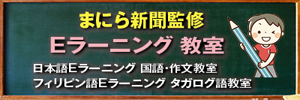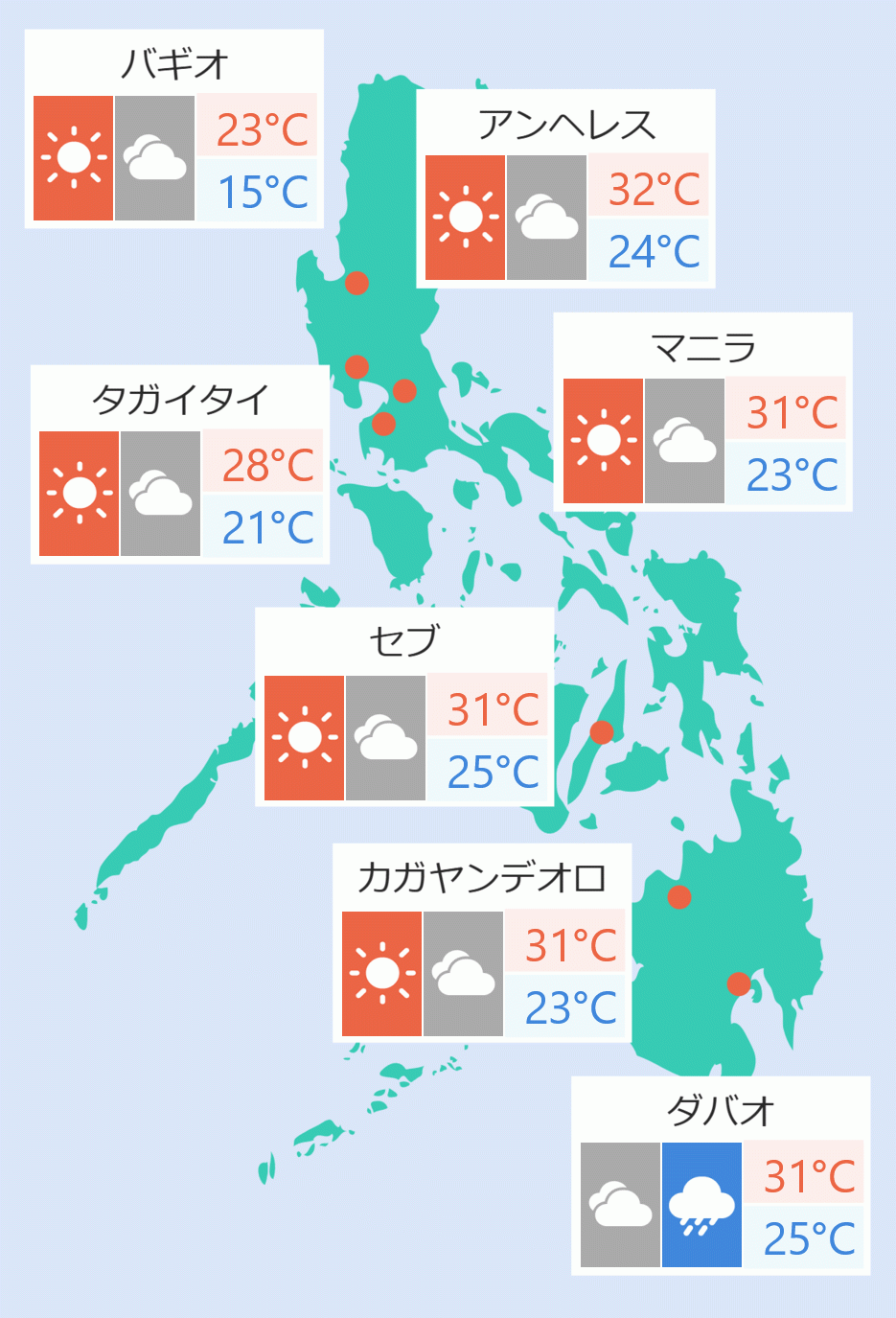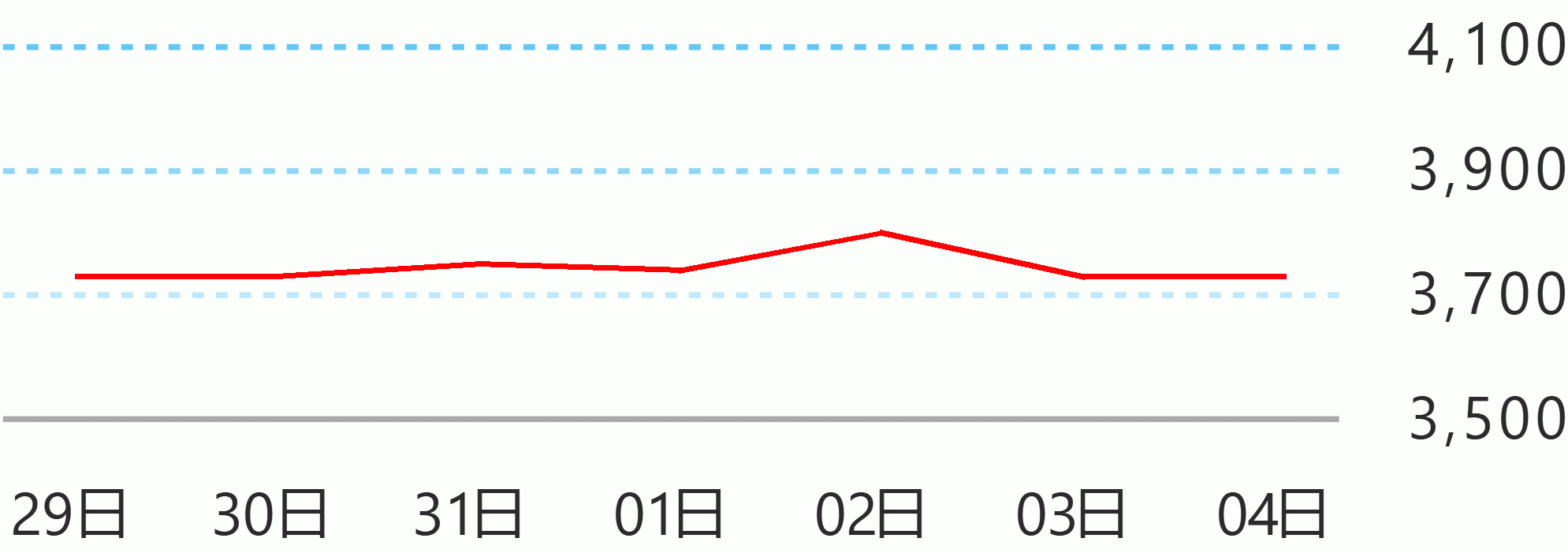一介の大学院生が、研究対象だった比人ホステスと恋に落ち、最終的には暴力団系のマネージャーと直談判、偽装結婚問題を乗り越えてゴールインするまでの経験を赤裸々につづったルポ「フィリピンパブ嬢の社会学」(2017年、新潮社)の著者・中島弘象さん(33)が9月、映画版の撮影のため3年ぶりに来比した。
就職活動も思わしくなく、大学院修了後肉体労働に従事しながら、いずれ結婚式を挙げようと2人夢見るところで終わっていた同著。中島さんの生活はその後どう変わったのか、また、自身の壮絶な体験を踏まえ、日本の比人出稼ぎ労働者をどう見ているのか。まにら新聞の単独インタビューに、自身の考えを語った。(聞き手は竹下友章)
―出版後の生活は。
2017年2月に出版した後、長女が生まれた。同年11月に地元の印刷会社に就職し、2018年に映画化の話をもらったころには、現代ビジネス・オンラインへの寄稿など執筆の仕事や、講演、ラジオドキュメンタリーの仕事などを始めていた。
妻は出産を機に主婦業に専念。2020年には次女も生まれた。結婚式は結局実現しなかったが、映画化が夫婦の結婚式代わりになればいいなと思っている。
―フィリピンパブはその後変わったか。
小さい変化はある。来日後マネージャーの管理下に置かれながら給料を中抜きされ、6万円程度の手取りで働く契約期間は以前は2〜3年だったのが、現在は4〜5年に伸びたりとか。以前の妻のように全く自由がない状態で働く人もいる一方で、かなり自由をもらえている子も出てきた。ただ、偽装結婚など女性たちの渡航手段や契約内容、労働環境に基本的な変化はない。
フィリピンパブは売春も行っているとの誤解があるが、実際は違って、日本のキャバクラと同じ。店のシステムとしての売春はない。パブ嬢の中には個人的に客と肉体関係を持つ人もいるだろうが、仮にそういうことがあっても店にお金が落ちるシステムにはなっていない。
―興行ビザ発給厳格化をどう思うか。
2005年までは興行ビザで多い時期は年間約8万人が来日しパブで働いていた。ビザ発給が厳格になってからは、偽装結婚という非合法な手段が主流になった。それで自由を剥奪する理不尽な契約を結ばされたりしている。根本的な問題は、「来日してパブで働く」という道が出来上がってしまった後に、表の道を大いに狭めたこと。それで地下に潜ってしまった。
―興行ビザ発給を緩和すべきか。
そう言うと批判もある。今、技能実習生が人身売買の温床になっているというのと同じで、かつては興行ビザが人身売買の温床になっていると言われていたから、発給を厳しくしたという経緯がある。もし、夜の産業がダメというのなら、別の産業で門戸を開いていいのでは。現状、正規の方法は、学歴や日本語講習など、色々要件が多く難しい。そのハードルを超えられない人達が日本に出稼ぎをするときに頼らざるを得ないのが偽装結婚ということ。何かを緩和したからといって簡単に解決できる問題ではない。
―比人出稼ぎを巡る従来の議論に対してどう思うか。
先行研究で主に書かれているのは、被害者としての比人。ところが彼女たち自身は自分のことを被害者とは思っていない。一人の人間として、プライドを持って生きている。置かれている環境は酷い人も多いが、人間としては対等。それを「支援してあげる」となると、どこか「上から目線」を伴ってしまう。僕個人はそれを止めて、一人の友人として向きあう道を選んだ。もちろん、せいぜい悩みを聞くくらいしかできないが、友人として付き合う方が彼女たちをより理解できる。
―出版した時の世間の反応は。
「フィリピンパブなんて」とか「社会学じゃない」とはよく言われた。ただ、これまで偽装結婚の実態を明らかにしている文献はないし、ここまで入り込んで彼女たちの生活を描写しているものはない。彼女たちの感情の部分まで書いた。
「事実」と「感情」。これが社会を作っているのだから、僕はこれを社会学だと思っている。文献を読み従来の理論に根ざす社会学もいいが、既存のレールに乗ることだけが本当に社会学なのかと。社会はいっぱいアメーバのようにある。その中の一つを見つけ出さないことには社会学にならないと思う。社会学じゃないという批判に対しては「僕の本を読み込めていなかっただけじゃないですか」と思う。
―日本で育つ比日ハーフの子どもについては。
比日ハーフの子どもたちは、自分のルーツについて何かしら「他の国のハーフとは違う」と思うところがある。送金問題などで世間のイメージが悪かったり。ただ、比日ハーフだからといって「問題を抱えている」と決めてかかるとよくない。ネガティブ一辺倒な解釈に陥ってしまう。もっと楽観的・客観的に、そういうフィルターなしに見たほうが実状への理解が深まる。
自分は「他の比日ハーフの子はどうなっているんだろう。話を聞きに行こう」という姿勢で関わり始めた。もし困ったことを抱える子がいたら「どこどこのお兄ちゃんは同じ悩みを持っていたけど、こうやってプラスに変えたんだよ」と伝えるような関係でいたい。
―今後書きたいことは。
ベースになっているのは家族。自分の生活から見える範囲のことだけ書く。それが強みだと思っている。感情や人となりを重視しているため、身近な人のことしか書けないというのもある。日々の生活が先にあり、そこで浮かんだ疑問を契機に取材をしていくのが自分のやりかた。
現在、第二弾の書籍を執筆している。1章で子どもが生まれたときのこと、2章で幼稚園に入るまで、3章で比への帰国と送金、4章で2世の子ども、5章で外国人として日本に住むこと、6章で今の生活を書く。来年の映画公開に合わせて出版を計画している。
なかしま・こうしょう 1989年生まれ。愛知県出身。中部大大学院国際人間学研究科修了(国際関係学)。現在会社員として勤務する傍ら、文筆業、講演などマルチに活躍。





 English
English