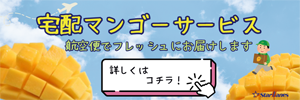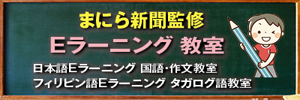首都圏の貧困地区で生きる邦人男性4人を追った粂田剛監督のドキュメンタリー映画「なれのはて」が、新宿ケイズシネマで12月18日から一般上映される。同作品は2020年東京ドキュメンタリー映画祭で長編部門グランプリ・観客賞を受賞。粂田監督から比を題材にした作品などについて、オンラインで話を聞いた。(聞き手は岡田薫)
─撮影までの経緯は
2011年に当時まにら新聞記者だった水谷竹秀氏の著作「日本を捨てた男たち」が出て、12年にそれを読んだ。テレビ番組の制作などに関わる仕事をしており、フジテレビの「ザ・ノンフィクション」用に面白そうだと思い、取材を始めたのがきっかけ。フジテレビのプロデューサーも最初は「これ面白いね。昭和30年ぐらいの日本だよ」と喜んでいた。ただテレビには制約が多い。自分の好きなように取材し編集したくなった。自らが面白いと思える作品にしたい。そう思ったら映画しかなかった。
12年9月に、まにら新聞関係者を通じてこの映画に出てくる脳梗塞で倒れ、首都圏で不自由な生活を送っていた嶋村さんを紹介してもらった。仕事の合間に比へ通い、1回の滞在は10日〜2週間。最終的に約50人の日本人と会った。
編集は17年から始めた。当初6〜7人を登場させていて5時間の長さがあった。知人に相談すると「無名監督の5時間もの作品を映画館では流せないよ」と諭された。最終的に4人に編集し直し、2時間6分の作品に。それで20年の東京ドキュメンタリー映画祭に応募した。
─比との関わりはいつから
1999年ごろに日本の障がい者団体を紹介するビデオを作成し、比での支援に同行したのが最初。今では相当発展したけれど、かつては走る車もボロボロだった。スモーキーマウンテンに行って「これはすごいな」と思った。オロンガポの教会や孤児院にも行き、翌年はアエタ族の村で1カ月居候もした。その時マニラで強盗に遭い、身ぐるみ剥がされた。忘れもしない聖週間。怪しいおじさんに騙されて一文無しになってしまった。途方に暮れていたらオロンガポから知人が迎えに来てくれた。「お金を盗られて大変だったね」と、比人の優しさが身にしみた。
2007年にも比観光庁の仕事で、パラワン島やセブ島、ボホール島で、日本向けに観光をアピールする映像を作った。もう一度比を題材に何か撮りたいと考えていたところで、水谷氏の本と出会った。言葉はよく分からなくても比ではなんとなくこう行くんだよな、という感触は分かっていた。
─撮影はスムーズにいったか
撮ってもいい人に会うのが大変で、顔を出してしゃべることに抵抗がある人が多かった。中には「顔が映ると殺されます」という人や落ちぶれたところを見せたくないとか。最初のころは苦労した。
彼らの大半は邦人社会から離れて生活しているので、日本語を話したがり、歓迎はしてくれた。比在住の日本人には怪しい人もいる。そういう人たちに酷い目に遭った経験から、最初は「こいつは何だ」って警戒する人もいたと思う。でも、彼らには取られるものはもう何もない。そういう意味で開けっぴろげでもあった。
彼らは悲惨は悲惨だけれど、日本人からするとどこか懐かしい。日本も昔こうだったような。いつの間にか息苦しい社会になってしまった。一言で言えば「冷たい」のかな。貧しい人には「生活保護でも受けに行ったら」で終わってしまう。比にいる間、私もどこか開放感を感じていた。もちろん実際の彼らはお金もなくて大変だ。そこに至るには葛藤があったと思うけれど、どん底まで行ってしまえば比の人々とワイワイ楽しくという感じもした。
─次作について
次作の「ベイウォーク」が今月11日に始まる東京ドキュメンタリー映画祭で初日に上映される。撮影してきた6人のうち4人が「なれのはて」になり、これは他の2人の話。
マニラ湾沿いの路上で寝泊まりするホームレスの日本人がどうなっていくのか。またその目の前のコンドミニアムを購入した日本人が老後を過ごそうとやってくる。一人は地べたを這(は)いずり回る生活を送っている。2人の生活圏はほぼ一緒で、触れ合わないけれど、すぐ近くにいる。環境が大きく異なった2人に焦点を当てたもの。
「なれのはて」は、新宿を皮切りに、年明けには神戸、大阪、京都、名古屋、横浜、宮崎まで決まっている。約30カ所を目指したい。また、来年は比へ行けることを願っている。
◇
粂田剛(くめた・つよし) 1969年、愛知県生まれ。都立大学人文学部卒。フリーの助監督として原将人、矢崎仁司、松井良彦監督らの作品に参加。企業PR、教育映像やNHKプレミアム、フジテレビなどの番組ディレクターとしても活動。


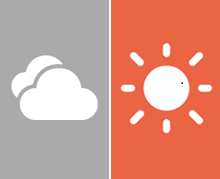


 English
English