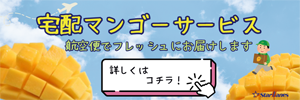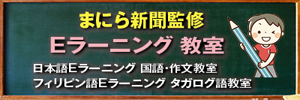3月23日午前11時5分、暗く冷たい静寂の宇宙に、小さな希望の光が打ち上げられた。北海道、東北両大学の協力で製作されたフィリピン初の人工衛星「DIWATA(ディワタ)=妖精=1号機」の打ち上げは、比国内で大々的に報じられた。東南アジア初の快挙として注目されるフィリピン自前の超小型衛星。開発の背景には、宇宙利用におけるこれまでの方法論をがらりと塗り替える、ある挑戦があった。
DIWATAの開発に携わった北大宇宙理学専攻の高橋幸弘教授(50)は、2009年に北大へ赴任して以来、ある同様の不満を同僚研究者から聞くようになった。「いまいちなんだけどなぁ、このカメラ」「この微妙な解像度をどう使ったら良いんだろう」。
北大では農学や水産学などの分野でフィールド科学の研究が盛んで、多くの研究者が地理データの分析に衛星からの観測データを活用する。ところが、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が運用する大型衛星からのデータは広範なものが多く、詳細なデータを求める研究者のニーズに適していないことが多々あった。研究者の不満はここから発されたものだった。
「全体的にみると、(JAXAは)大きな衛星、ロケットを作る人が偉い世界」と高橋教授は話す。はじめに豊富な資金力を持ったメーカーが大型で精密な衛星を作り、その上で研究者や他国に利用を促すのが日本の宇宙利用のやり方だ。しかし、その方法では実際の利用者が本当に必要なデータを得ることは難しい。発展途上の国々も、予算面から自前の衛星を開発できず、先進国の衛星データを買うしかない。
この問題を打破する方法として高橋教授が目を付けたのが、1990年代末期に英国で生まれた「超小型衛星」だった。
開発費は大型衛星のわずか100分の1。小回りが利くので、これに最先端のカメラを積めば、狙った地域の詳細なデータを得ることもできるはず。資金がない途上国でも、技術さえ向上すれば開発は可能だ。この発想を基に、高橋教授はベトナムやインドネシア、バングラデシュなどアジアの途上国8カ国を駆け回り協力者を求めた。この時、頭の中にはある構想が芽生えていた。
「アジア・マイクロサテライト・コンソーシアム」。そう名付けられた高橋教授の構想は、発展途上のアジア諸国で自前の小型衛星を開発し、必要に応じて共同利用するというものだ。普段は自国の研究に活用するが、大規模災害が発生した時は、参加国のすべての衛星を被災地観測に集中させる。これによって大量の観測データを頻繁に得ることができる。これまでの先進国主導とは違う、新しい宇宙利用の方法だった。
これにいち早く反応したのが比の科学技術省だった。2015年1月に総額8億円(約3億4千万ペソ)を投入してプロジェクトを開始した。政府開発援助(ODA)に頼らず、経費は比が全額負担した。同省やフィリピン大から優秀な人材9人を留学生として日本に派遣し、未経験の場合、通常3〜4年かかるといわれた小型衛星開発を、わずか1年で完成させた。「ほとんど奇跡だ」。比の熱意に高橋教授は舌を巻いた。
比大工学部から派遣されたジョエル・マルシアノ教授(43)は衛星開発の意義についてこう語る。「比にとって歴史的な瞬間に立ち会えたことは光栄。これで、比は科学技術の面で国際社会に積極的に貢献できる」。現在、国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」に収容されている1号機は、今月27日にも宇宙に向けて放出される予定だ。日本では、比の小型衛星2機目になる「DIWATA2号機」の設計が進んでいる。1号機は日本側があらかじめ設計図を用意したが、今回は比人研究者自らが設計段階から議論に参加している。完成予定は2年後だ。
「比のような意欲があってこれから伸びていく国が、正しい宇宙利用モデルを作れば良い」と高橋教授は考える。上からの技術の押しつけではなく、新しい技術と実際のニーズとをどうやって結びつけていくのかが、宇宙利用の本質だ。そうして作られた新しいモデルは「私たちのモデルにもなる」(高橋教授)。
宇宙にぽつんと灯る小さな光が、やがて無数に増え、地球全体を明るく照らす。そんな未来は、もう近くまで来ているかもしれない。(加藤昌平)





 English
English