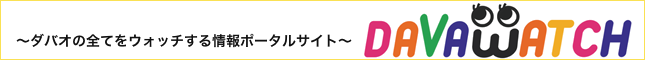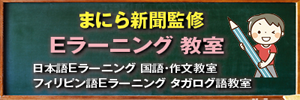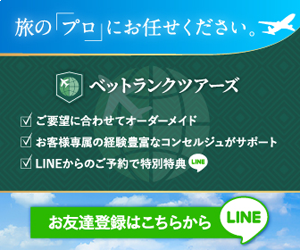移民1世紀 第1部・1世の残像
「外国」だった父の国

「おれをおいて行け。お前たちだけ早く行け」
尾辻ヨシさん(78)の父林造さん‖当時(63)‖は、イフガオ州キアンガン町付近の泥田に半身を埋めながら別れを告げた。手には出稼ぎで得た金を入れた貯金通帳と印鑑が握りしめられていた。ヨシさんは三歳の長女を連れてその場を立ち去った。一九四五年(昭和二十年)五月二十三日、雨の降り続く夜のことだった。
林造さんは、鹿児島県加世田市の農家の長男。息子を高校へ入れるため、一九一〇年ごろフィリピンへ渡ったという。ベンゲット州バギオ市で農業やかじ屋を続けながらイゴロット民族の女性と結婚、ヨシさんらをもうけた。
他の日本人移民の家庭と同様、尾辻家の生活も戦争により砕かれた。米軍がリンガエン湾に上陸した四五年一月、ヨシさんは「カガヤン州アパリ町から引き揚げ船が出る」という話を信じて父、娘とともに家を出た。四一年に結婚した日本人の夫は、四四年九月に現地召集されて行方不明になっていた。
アパリ港までは直線距離で約二百五十キロ。「イモやマメ、果物を食べながら夜間だけ歩く」日々が続く中、あの雨の夜が来た。
ヨシさんは言う。「キアンガン町に着いたところで父は歩けなくなり、私がおぶったの。ところが足が滑って父と私は泥田へ落ちてね。栄養失調で父を泥から助け上げる力はもうなかったわ。翌日、田へ戻ったら父はもう死んでいました。埋葬もできず、ワラをかぶせただけで立ち去りました。むごい話ね」
残された母と長女はなおも歩き続け、イフガオ州の山中で終戦を迎えた。しかし、その数日後「おうどんが食べたい」という一言を残して長女も死亡。栄養失調とアメーバ赤痢だった。ヨシさん自身も生死の境をさまよったが、途中から合流しためいらに助けられて一命を取り留めたという。
日系二世の大半が戦地に残る中で、当時二十一歳のヨシさんは四五年十月、「お父さんの国を見に行きたい」と引き揚げ船に乗った。広島に上陸後、長崎県の夫の実家に身を寄せたが、バギオ生まれの日系二世にとって、父の国・日本は「外国」だった。
「姑(しゅうとめ)は大変厳しい人で、いつも『うちの嫁はアイノコで・・』と人に紹介されたわ。結局、家を出て、米軍人のメードをした後、五六年から米軍座間基地で働き始めたの。あのころは、どうして私たち混血を生んだの、と両親を恨んだわね」
米国人相手で気が楽だったという基地の仕事は二十九年九カ月間、六十歳の定年まで続けた。退職後は老人ホーム入所も考えたが、「命の恩人のめいらに退職金で家でも建てて恩返ししよう」と八九年にバギオへ帰郷。現在は日系人組織「北ルソン比日基金」(カルロス寺岡理事長)運営の宿舎「アボン」(家)を切り盛りする、同基金の「顔」の一人だ。
長い戦後を一人で生きてきたヨシさんが肌身離さず持ち続けているものがある。カンルーバン日本人収容所で支給された米国製の金属食器セット。「日本へ行く前の一カ月間、入れられたの。日本へ持っていったのはこのセットだけね」とヨシさん。コーヒーカップも日本製ではなく、二十八年前に座間基地で買った米国製を愛用している。(つづく)