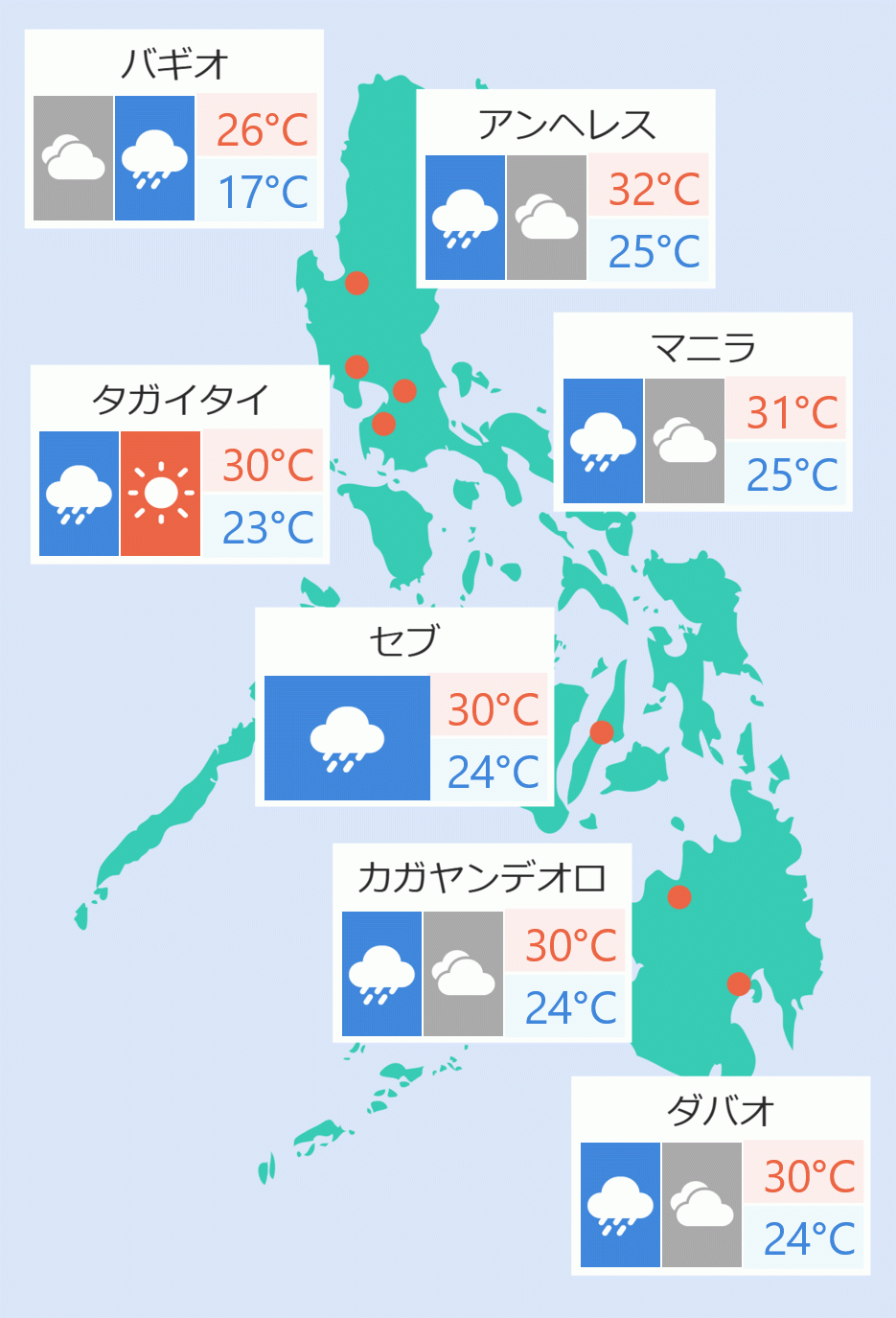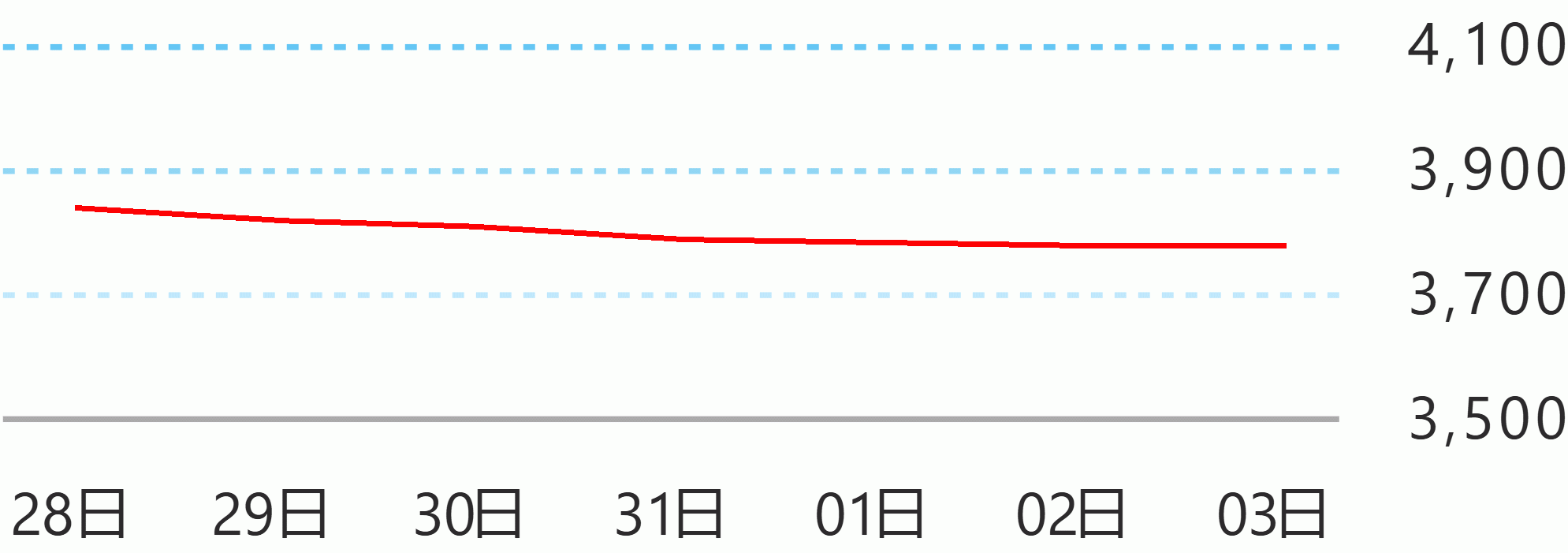第5回 ・ 軍人から「比人の敵」へ

一九四一年十二月から四年近く日本の軍政下に置かれたダバオ。日本人移民を父に、フィリピン人を母に持つ日系二世の多くも軍人・軍属として軍政支配に組み入れられた。そして、日本人の両親を持つ移民二世が日本へ強制送還された敗戦後、日系二世は母とともに戦地に残され「比人の敵」として戦後を生きた。その数は千人を超えるといわれる。
ダバオ市郊外でトウモロコシやコーヒーを栽培している栄幸一さん(75)もそんな日系二世の一人だ。父は山口県大島町出身の直吉さん(一八八三年一月生まれ)。母は少数民族バゴボの比人女性。直吉さんは一九〇三年にルソン島へ渡りベンゲット道路建設に従事。その約二年後にダバオへ移り、マニラ麻を栽培していた。
栄さんはミンタル日本人小学校初等科、トンカラン日本人小学校高等科で学んだ後、四二年からダバオ軍政監部で給仕として働き始めた。そして、徴兵年齢が十七歳に引き下げられた四四年、召集令状を受け取り陸軍工兵隊に配属される。
「赤紙(召集令状)を見ても特に驚きはなかった。日本人だから当たり前です。基地へ行ったらほかにも日系人がいました」と栄さんは言うが、彼の出生がダバオ日本領事館に届けられたのは召集のわずか六年前。当時、日本政府は近い将来の開戦を見越して二世たちの戸籍登載を奨励しており、栄さんの現地召集もそのライン上にあった。
入隊後間もなく、米軍によるダバオ空襲が始まり、栄さんの部隊は山へ逃げ込む。「遺体が転がる川の水を飲み、野草を食べる生活」が続いたある日、竹を切り出して十メートル間隔で地面に立てるよう指示された。聞けば、パラシュートで降りてくる米兵を串刺しにするためという。「工兵隊の仕事と言えばそれまでですが、これでは負けると思いました」
一緒に山を逃げ惑った「松田隊長」「アラタ曹長」「ソノダ曹長」らは敗戦直後、収容所送りとなったが、栄さんはダバオ市ダリアオンバンカスに残してきた母の元へいったん戻った。隊長らとともに引き揚げ船で日本へ行くことを告げると「生活に困る。残って欲しい」と母に泣きつかれた。「本当の気持ちは日本人ですから。日本へ帰るつもりだった。母のことを思って比に残ったが、今でもあの時日本へ帰っていれば・・と思います」と栄さんは振り返る。
「母を置いてでも日本へ帰ればよかった」。栄さんを後悔させているのは、戦後六十年近くを経ても「何ちゅうても日本人ですから」と言わせる強烈な自意識と戦後の過酷な境遇だ。
他の二世軍人・軍属とともに村山政権時代の日本政府に提出した「太平洋戦争間、勤労動員、徴用、召集未払給料請求書」で栄さんはこう訴えている。「戦争前の生活は何の不自由もなく親と一緒に住んでいましたが、戦争が始まって以来、私たちは大変惨めな生活をしてきました。みんな日本政府の罪であると思います。軍人恩給も一切もらっていません」
戦後、比人の復しゅうを恐れ「コンスタンショ・アモイ」と名を変え、隠れるように生きてきた栄さん。隣人たちの知る名前は今も「サカエ」ではなく「アモイ」だ。九〇年代に入って子供四人が日本へ出稼ぎに行き、生活は多少上向いたが、「(請求書への)答えは返ってこなかった。どうして日本政府は日本人として扱ってくれないのか」という思いは胸に沈んだまま消えない。(つづく)
(2003.4.19)





 English
English