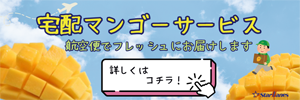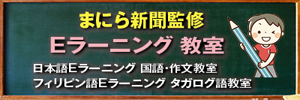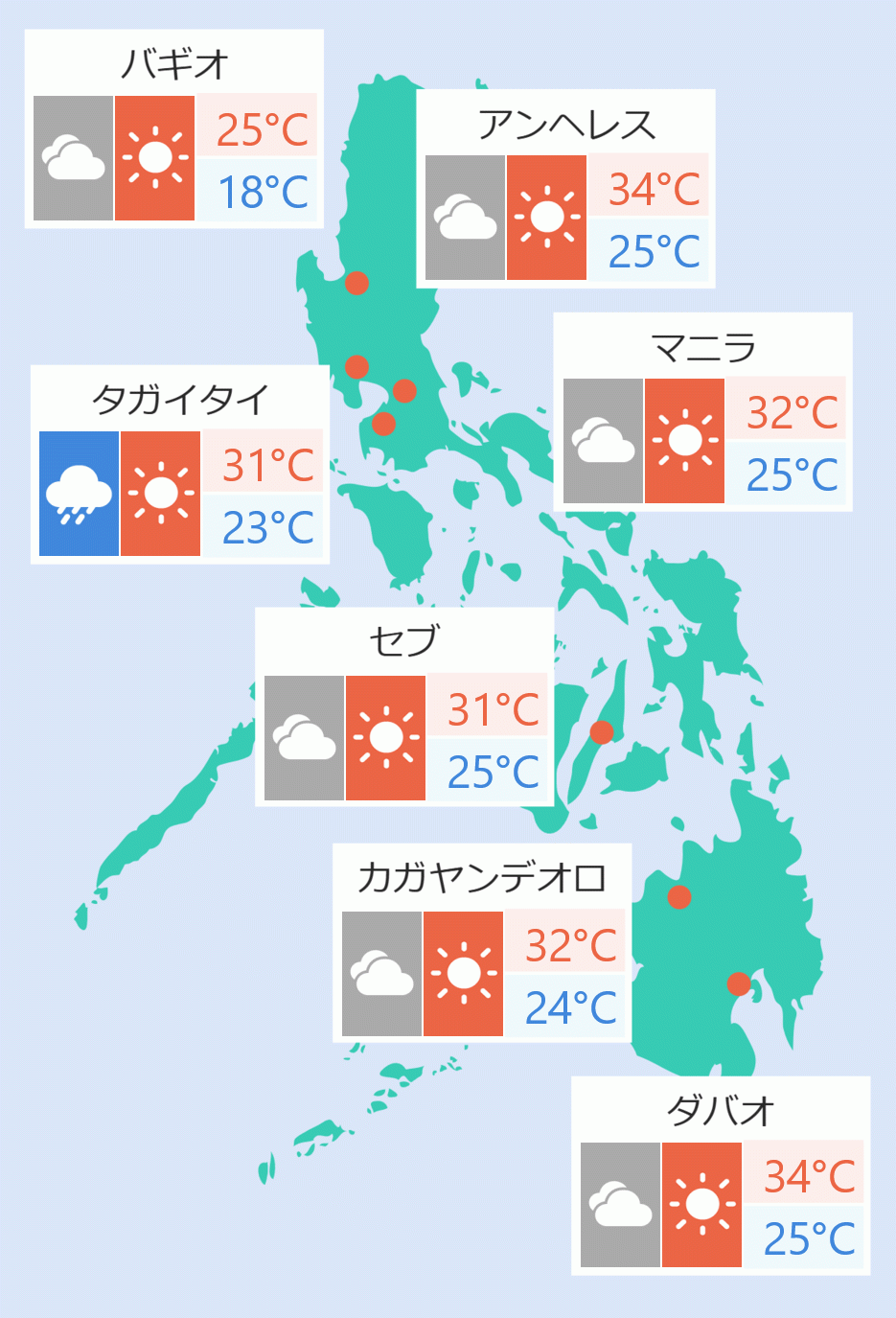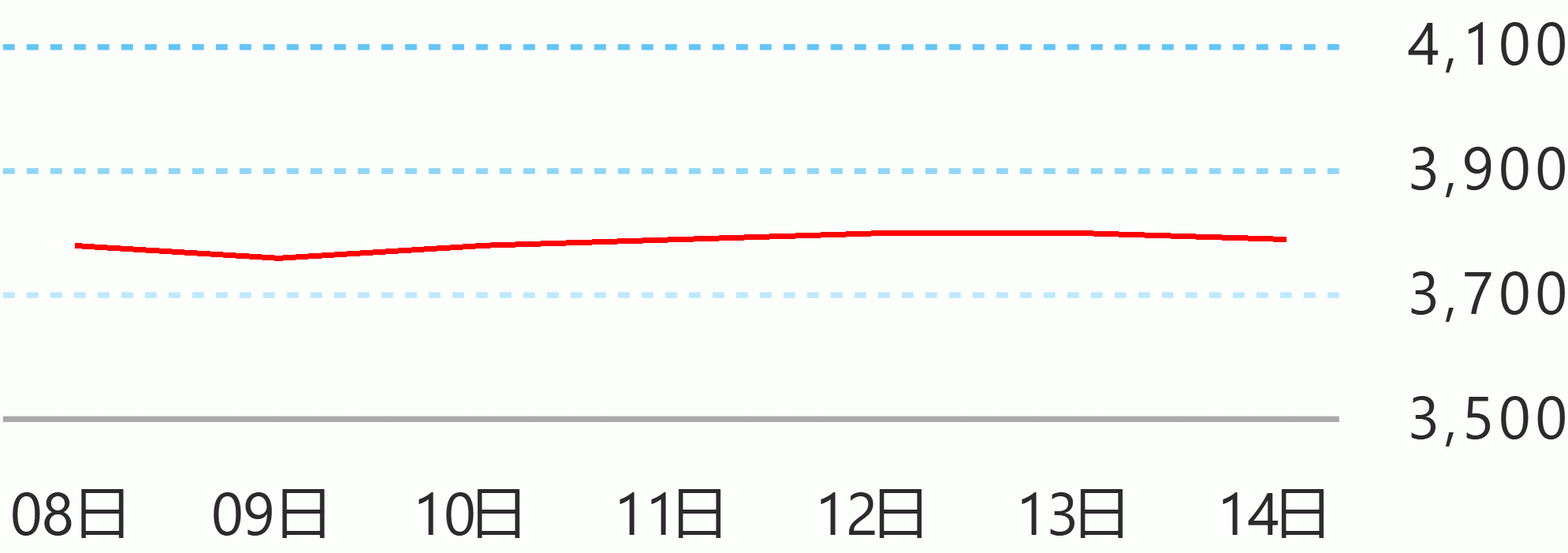第2回 ・ 両親の残影を追い求め

「お父さん、お母さん。私を生んでくれてありがとう。清子ちゃん、盛正。生きている時に会いたかったよ・・」。二〇〇二年八月、「ダバオ慰霊と交流の旅」に参加した山田春子さん(68)=沖縄県具志川市=が、朽ちかけたヤシの切り株に語りかけた。左手には古ぼけた一枚の家族写真。切り株に挟み込まれた日本製タバコの煙が、雑草生い茂る野の風にゆらぎながら青空へ消えていく。
家族写真に写っている人物は四人。山田さんの両親と妹清子さん、弟盛正さんだ。両親は山田さんが二歳の時、沖縄からダバオへ移りマニラ麻栽培に従事した。初孫だった山田さんは祖父母とともに沖縄にとどまり、その後、ダバオで妹と弟が生まれた。このため、戦前の昭和十二、三年ごろダバオで撮影され、沖縄へ送られた家族写真に山田さん自身の姿はない。
現地召集された父親は一九四五年(昭和二十年)五月、ダバオで戦死した。母親も敗戦直後、八歳の妹と六歳の弟を連れて山野をさまよう中でマラリアに倒れた。孤児となった妹弟は引き揚げ船で広島県宇品港へ送られ、そのまま近くの孤児院に入った。日本にたどり着いたものの、二人は極度の栄養失調状態。医師らが原爆被害者の救済に追われる状況下、二人は同年十一月までに相次いで息を引き取った。
十三年後の五八年(同三十三年)になって、引き揚げ者の記録から二人が宇品港に着き、孤児院に収容されていたことが分かった。「妹と弟が生きておれば、両親の話が聞ける」。山田さんはすぐさま孤児院へ向かったが、待っていたのは二つの小さな骨つぼ。名前の分からなかった弟の骨つぼには「南太郎」と仮の名が付けられていた。南方から帰ってきた男の子、という意味だった。生前の様子を知る孤児院関係者から「二人には『日本に着いたのにおじいちゃん、おばあちゃん、お姉ちゃんが連れに来ないのはどうして』としきりに言っていました」と聞かされ、胸が張り裂ける思いだった。
妹弟の死によりいったん途絶えた「両親探しの旅」。しかし、両親の生きた土地を見たい、飲んだ水を飲みたいという思いは絶ちがたく、敗戦から五十五年後の二〇〇〇年八月になって初めてダバオの土を踏んだ。手がかりは「ダクダオ耕地」と呼ばれた麻栽培地に家があったという伝聞情報。そして家族写真だけだったが、同耕地で麻産業にかかわった古老たちを当たり続けた結果、ついに戦前に父親に雇われていた比人男性(82)を探し出した。男性は写真にうなずきながら山田さんに語りかけた。「お父さんはとてもいい人だったよ」。
男性とともに「家の庭に大きなヤシの木が三本立っていた」という両親の家の跡へ向かった。一帯はマンゴの木を植えるため耕されてはいたが、男性の言う通り、朽ちかけたヤシの切り株が三つ並んでいた。
二年後の〇二年八月、山田さんは再び切り株の前に立った。三つあった株は一つになり、戦前に麻畑が広がっていた耕地はマンゴー林へと姿を変えようとしていた。「両親が写真を沖縄へ送っていなかったら、両親や妹弟の顔さえ知り得なかった。写真があったからこそこの切り株までたどり着けたのです。株がなくなってもこの場所は忘れない。また帰ってきます」。そう言いながら、タバコの火が燃え尽きるまで株を見つめ続けた山田さん。ダバオ生まれの日本人と同様、ダバオと向き合いながら戦後を生きてきた一人だった。(つづく)
(2003.4.15)


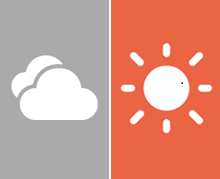


 English
English