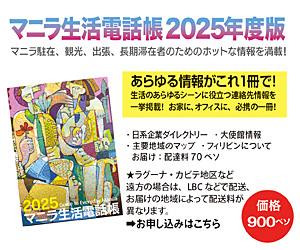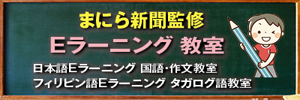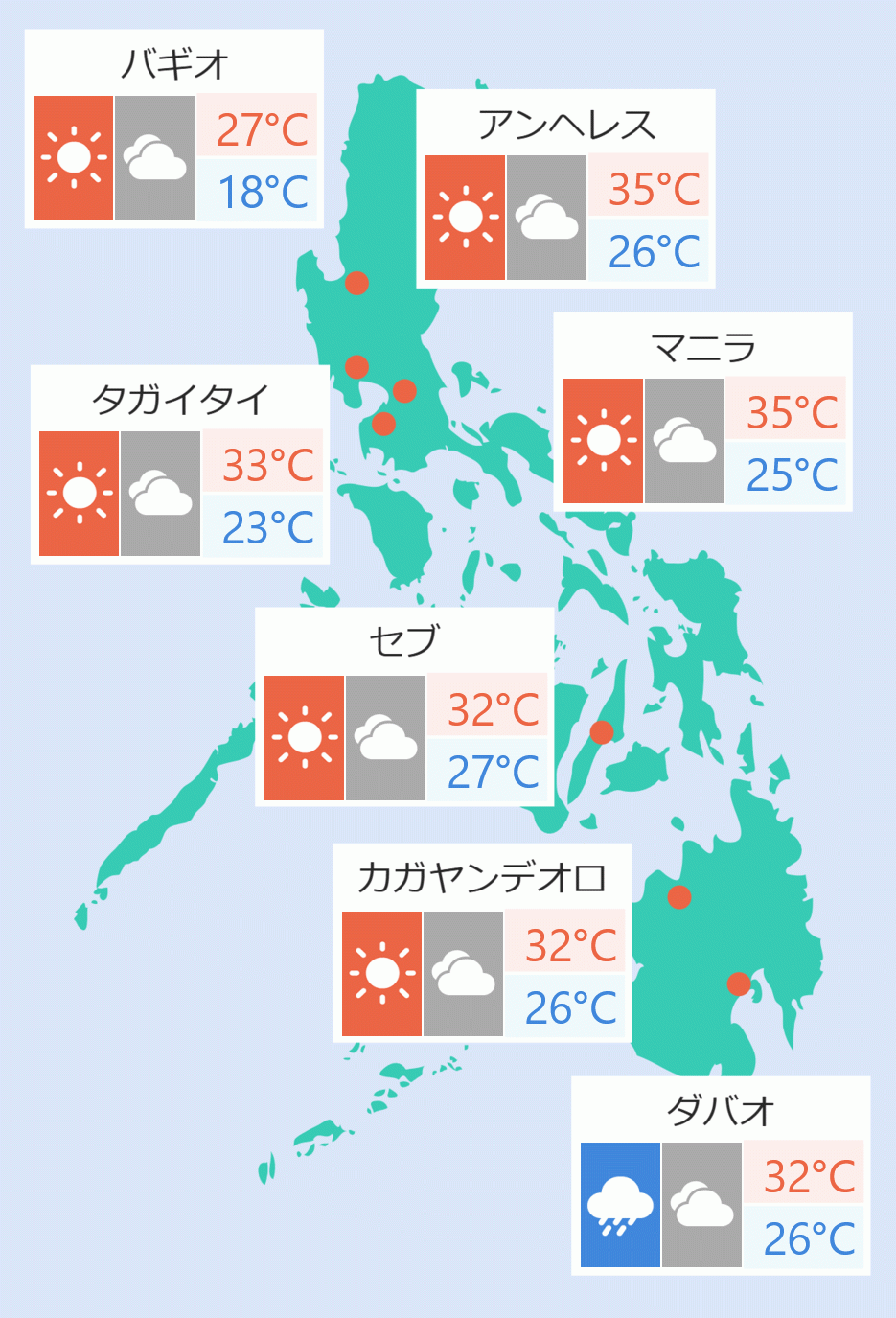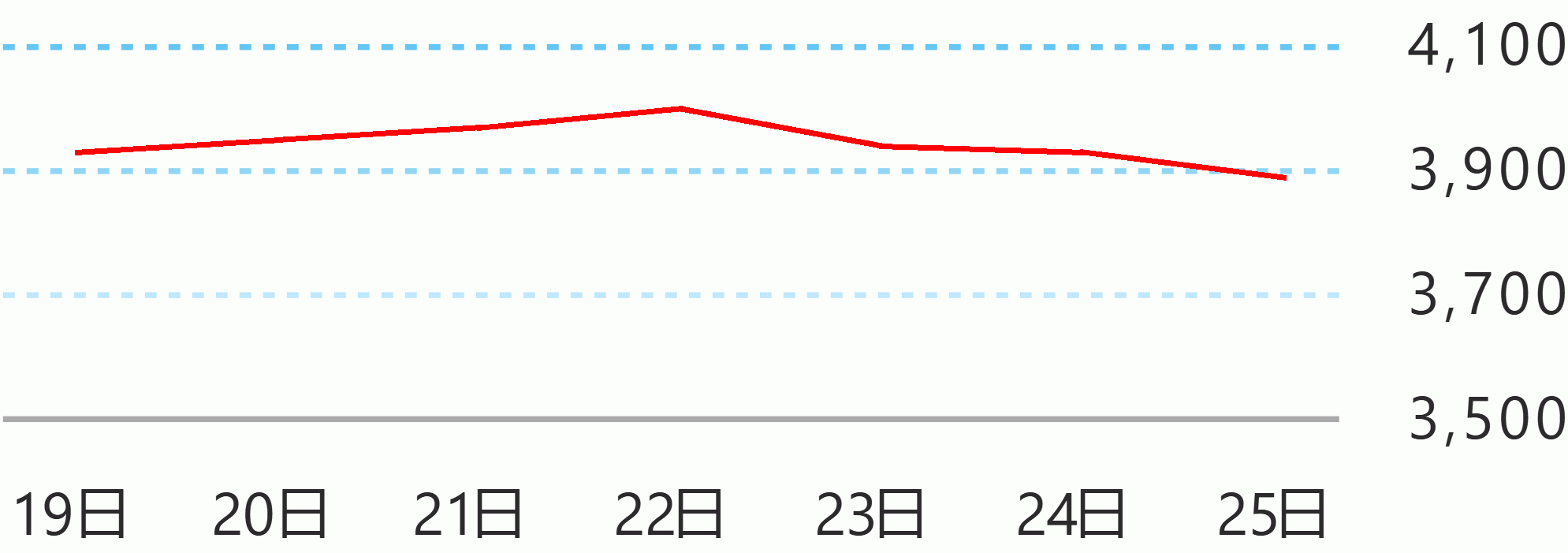貧しい環境に育ってまともな職につけないフィリピンの若者たちを雇い、自立を支援する自然食レストラン「ユニカセ」。一度は閉店を余儀なくされたが、今年4月に首都圏マカティ市のマカティ通り沿いに新規店舗を開いてから、半年余がたった。スタッフの離職や資金難など、様々な困難を抱えながら、スタッフは共に支え合ってそれぞれの夢を追う毎日だ。
▽今の仕事に満足
経営者の中村八千代さん(44)の下で、常勤のスタッフは現在3人。2010年10月からユニカセで働いているレイア・デロスレイエスさん(23)は、父が病気で亡くなった後、家族を支えるために大学を辞めた。定職もなく、貧困支援の非政府組織(NGO)からの援助を受けていたが、ユニカセを紹介された。今は中心スタッフの1人として中村さんを支える。
デロスレイエスさんには無職の夫と3歳の子供がおり、生活は依然厳しいが、「今の仕事に満足している。毎日努力することで、少しずつ自分がプロに近づいていると実感している」と話す。「以前は夫に逆らえなかったが、今は逆に夫を叱り飛ばせるようになった」と笑った。将来は「ユニカセを自分たちで経営できるようになりたい」と、抱負を話す。
▽新作にも意欲
調理を担当するジェイサー・ギバラさん(24)は7歳の頃、市場で親とはぐれたところを保護された。今でも両親がどこにいるか分からない。孤児院で育ち、11年からユニカセで働くようになった。一度はユニカセを辞め、建設労働や路上で野菜売りの仕事をしていたが、まとまった収入にならない日々が続いた。やはり「厳しくとも、ユニカセで再び働きたい」と戻る決心を固めたという。
ギバラさんは、ユニカセでの調理に絶対の自信を持つ。この仕事ができるのは自分だけだと誇る。「本やテレビを見ながら、新作メニューを考える」と笑顔を見せた。色とりどりの野菜のサラダ、メーンディッシュの豚生姜(しょうが)焼きや鶏肉のココナツミルク煮など、日本人の味覚に合った味付けのレパートリーは豊富だ。カラマンシーを使ったケーキやかぼちゃプリンなど、デザートにも工夫を重ねている。将来の夢は「自分の店を持つこと」だと話す。特にケーキやパンを作ることが得意なのでパン屋を開店したいという。「将来、自分の店とユニカセで協力して何かができれば」と語る。
▽息子には良い大学へ
マリベス・ベルデホさん(21)は18歳からユニカセで接客担当として働く。家族は首都圏ケソン市パヤタスにあるごみ集積場で集めたごみをカネに換えながら暮らしている。今でもパヤタスから約2時間ほどかけて通っているという。ベルデホさんも、一度はユニカセを辞めている。姉の子供を世話したり、接客業などで働きながら1年が過ぎたころ、ふと自宅においてあったユニカセの制服やトレーニングで使用した調理器具などが目についた。その時、レストランの厳しくも楽しい日々が頭によぎったという。ベルデホさんは勇気を出して中村さんに連絡を取った。
ベルデホさんには2歳になる男の子がいる。彼女の将来の夢は「息子に良い大学を出てもらうこと」。高校しか出ていない彼女は、学歴が低いために定職に就けなかった苦い体験がある。「自分の人生はすべて息子に捧げている」とベルデホさんは言い切った。
▽周りが足を引っ張る
中村さんはNGOスタッフとしての長い経歴を持つ。10年にマカティ市ジュピター通り沿いに最初の店舗を開いたが、家賃の値上がりなどで11年11月に閉店した。
ユニカセは開店以来、計24人のスタッフを雇ったことになる。そのうち残っているのはパートタイムで働きながら大学へ通うスタッフも含め4人だけだ。初めはやる気もあり、まじめに働くのだが、途中で脱落してしまうスタッフが多い。周囲の環境が彼らの足を引っ張っているのだという。
ユニカセは月給制だが、給料日まで待てず、両親から日銭が必要と言われ、ユニカセから日雇い労働に転職させられたスタッフもいる。そんな状況を改善することが一番の課題だと中村さんは話す。
▽目標までは道半ば
ユニカセは「NGOと企業の橋渡し役」だと中村さんは話す。NGOなどから紹介された若者たちを現場で訓練し、ゆくゆくは企業への就職を目指している。そのためにスタッフは働くことが決まると、レストランでの実務以外に、マネジメントの方法や資金管理などの技能訓練を中村さんからたたき込まれる。ユニカセという店名の由来は、「ユニークだから」ほどの意味という。一生懸命なスタッフをみやりながら、「まだまだ目標までの道は遠い」と、中村さんは自ら厳しく評価した。(加藤昌平)





 English
English