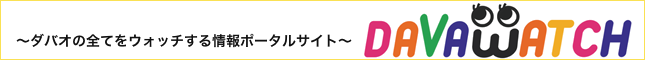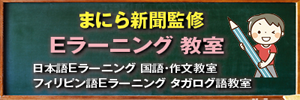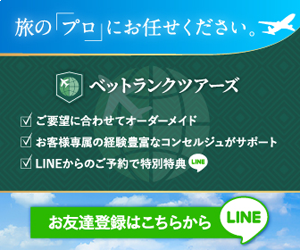「分かりやすくする気はない」 映画「フィリピンパブ嬢の社会学」
来年秋公開予定の「フィリピンパブ嬢の社会学」の白羽弥仁監督に単独インタビュー

名古屋市のフィリピンパブを研究対象にしていた大学院生が、対象の比人女性と恋に落ち、裏に暴力団がいると知りつつ愛を育み続け、修羅場を超えて結婚に至る一部始終を描いた話題作「フィリピンパブ嬢の社会学」(新潮新著、2017)が、来年秋公開をめどに映画化される。比人エンターテイナーが日本で味わう辛酸という古くて新しいテーマを取り扱う本作。メガホンを取った白羽弥仁監督は映像化に際し何を表現しようとしたのか。映画化にかける思いを聞いた。(聞き手は竹下友章)
―特に描きたい部分は。
原作をそのまま映画化すると、反社会勢力の話も含め大きくなりすぎるから絞った。原作はあくまで(著者の)中島さんから見たヒロインのミカとの関係で、男性目線。だからミカさんはどう思っていたのか、ミカさんから見た中島さんはどうだったのか、という部分は付け加えた。
―2人の関係性は。
ミカさんからの見方を確認したところ、原作とはまた全然違っていた。疑心暗鬼の部分もあるし、すんなり恋に落ちたわけでもない。一目惚れだったわけでもない。お客とホステスとの関係から、2人の関係がどう変わっていくのかという部分は映画化に際しディティール(細部)を加え描いた。
―ラブストーリーにすると報じられているが。
通り一遍の面白おかしいラブストーリーにするというのは、日本のプロデューサーやディレクターがよく考えることだが、絶対やりたくなかった。分かりやすいラブロマンスにするつもりも、ピュアなラブストーリーにするつもりもない。
2人とも内心自分が得するための計算もあったはず。利害が衝突する部分もある一方、それを乗り越えたときに「一緒に生きていきましょうよ」ということになったのであれば、それも一つのラブストーリーだと思う。
―昨今の日本映画をどう見るか。
今の日本映画がダメなのは、ウソみたいな純愛劇だったり、「お前のためなら死ねる」みたいなことを平気で言うようなところ。反知性的ですらある。関西弁でいうところの「アホか」と。もうちょっと打算もあり「ずるさ」もありで、そんな中で肩を寄せ合って、「気がついたら一緒にいるんだね」というところに持っていきたい。
―社会問題として描きたい部分は。
偽装結婚の実態。映画の中ではちゃんと描いている。パブで働くフィリピンの女性たちが日本でどんな部屋に住み、どんな生活をしていたのかというところは見せたい。
―出稼ぎ女性を犠牲者とする見方と主体性を重んじる見方がある。
一方的に比人女性がかわいそうで人権無視されてということではない。彼女たちが日本で勤め先がなければそれも困る。また非常に誤解されているところだが、フィリピンパブは売春組織ではない。そこの線引きは彼女たちの中でキチっとできている。「フィリピンパブで働いている女性=売春婦」という認識が誤解であることは、映画の中でしっかり言わせた。
―制作に至るまでの苦労は。
この映画を作るときの障害はまさに「フィリピンパブ嬢=売春婦」という誤解だった。企業にしても官庁にしても中身を見もしないでタイトルだけで制作に協力できないと言われた。(公正や平等をうたう)SDGsなんて標榜しながら、嗤(わら)っちゃう。本当は差別意識、誤解丸出しで何も知ろうとしない。制作の過程でそういうことがよく分かった。
―フィリピンでの撮影は。
日本では予定をガチガチに決めて撮影したが、比では現場現場で流動的にシーンを撮った。比ではわれわれもエトランゼ(異邦人)なので、あれも撮りたいこれも撮りたいとなったが、そういう思いつきで撮っている部分は映画の中で活きると思う。比人スタッフは想像していたよりずっとプロフェッショナルでしっかりと仕事をしてくれた。
ヒロイン、ミカの実家を訪問するシーンでは、(ミカを演じる)一宮レイゼルさんの実際の親戚の方に協力していただいた。比に帰った出稼ぎ労働者が親族にどうお金を配るのか、実にリアルなシーンが撮れた。
―比社会の印象は。
日本人スタッフ・俳優みんなが比を好きになった。日本では、知らず知らずのうちに自主規制している部分、責任を回避するために行動を起こさない部分があるが、この国にはない。比人を鏡にそういう日本社会を振り返る契機になった。
また、幸せとは何かと改めて考えさせられた。大金持ちになり、人の上に立つことなのか、聖女ではないけど目の前にいる人を愛するのが幸せなのか。いろいろな形があると思うが、日本の場合は経済や、悪い意味での人間関係が絡むし、幸せのカタチを作るものが個人の主体性にない部分がある。私が幸せだと思えば幸せなのに、それを周りが時に社会が許さない。
―比人は貧しいが幸せになる方法を知っていると言うが。
もちろん貧困そのものが良いわけではない。こっちに来て思ったのは、野良犬がみんな痩せていること。人が食べるのに精一杯だから野良犬でさえ食べるものがない。「貧しくともそれぞれの眼が輝いていれば幸せ」というのも綺麗事だ。
一方で、日本のように会社の仕事が辛くて電車に飛び込む人もこちらにはいないはず。幸せの求め方とは、会社で上手く立ち回ってお金をもらうことなのか、それとも日がなすることは無いがこれからを悲観せずに考えて生きていけることなのか。輝かしい未来があるとは限らないが「まあ何とかなる」と言えるのであれば、電車に飛び込む人よりはよっぽど幸せだ。
比での気付きは映画にものすごく反映されると思う。日本映画の中では陽気な、ファンキーな映画になるんじゃないか。
◇
白羽弥仁(しらはみつひと) 映画監督。1964年生、兵庫県出身。代表作は「能登の花ヨメ」(2008年)、「ママ、ごはんまだ?」(2017年)、「あしやのきゅうしょく」(2022年)など。