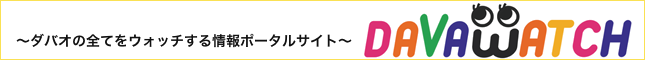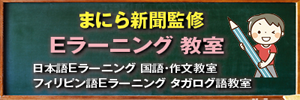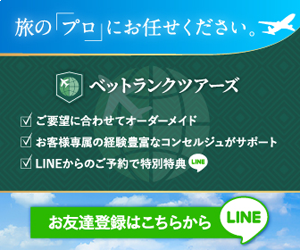台風ヨランダ
台風取材1年体験記「被災者と暮らす」

台風ヨランダが猛威をふるったビサヤ地方レイテ州。被災直後から1年間取材を続け、苦しみの中から立ち上がり、奮闘する多くの被災者に出会った。全てを失った人たちに、逆に優しく迎えられることが何度もあった。被災者と一緒に時間を過ごすことで、マニラでの取材では経験できない「葛藤や悩み」、さらに「希望」を知ることができた。グランド・ゼロの取材をしながら、被災者の中で特にお世話になった2家族のことを報告する。
▽緊張の電話取材
「知人の娘が私の目の前で血を吐いて亡くなりました」。レイテ州ドゥラグ町で農業を営む田村忠義さん(40)と初めて電話で会話したのは台風直撃から7日後だった。電話で話した時、田村さんは妻ポルシアさん(32)と息子の千畝(ちうね)君(6つ)の3人でセブ島まで避難する道中だった。自宅からヒッチハイクしてレイテ島西部のヒロンゴス町の港までたどり着いた田村さんの声には、緊張の連続で蓄積した疲労が感じられた。
「しばらくしたらドゥラグ町に戻って農業がしたい」。所持金は1万5千ペソで、下着もわずかしか持っていないという。しかし、田村さんはレイテに戻る気持ちが強かった。当時、現地からの報道は、壊滅的な被害を受けたインフラ設備や、増加し続ける死傷者数を刻々と伝えていた。
果たして本当に田村さんは帰って農業を再開できるのだろうか、と私は思った。「健康にだけは気をつけてください」。そう伝えて電話を切ったが、一抹の不安が残った。
▽復活した農業
農業を再開するには、しばらく時間がかかるのではないか。しかし、私の予想は大きく外れた。田村さんは被災から1カ月もたたないうちに妻と子供をセブに残し、単身ドゥラグ町に戻っていた。被災1カ月後、レイテ州に再度入った時、州都タクロバン市から車で約1時間ほどの田村さん宅を訪ねた。
短く切った髪型に白いTシャツ姿の田村さんが笑顔で出迎えてくれた。しかし、暴風雨で吹き飛ばされた自宅の屋根は壊れたまま。田村さんは雨よけのビニールシートをつるした部屋で一人暮らしをしていた。電気と水道は来ておらず、夜は灯油を入れた空き瓶をランプ代わりにしていた。「ごく普通の生活のありがたさが分かりました」。田村さんのこの言葉を今でもよく覚えている。
▽バー開店と刺身
被災から1年が経過し、レイテに入った。田村さんに「朝までゆっくり語りたい。自宅に泊まらせてくれないだろうか」と持ちかけると、快く受け入れてくれた。追悼式典などが街中で行われていた11月8日、日暮れ近くまでにすべての取材を済ませ、トライシクル(サイドカー付きオートバイ)で田村さん宅に向かった。
コメ収穫以外の現金収入を生み出すために、田村さんは一念発起し、今年6月までに自宅近くにバーを開店した。奥さんが接客を担当、田村さんもお客に出すつまみ作りで厨房(ちゅうぼう)に立つ。いつもは多くの客でにぎわうバーを午後7時の開店から2時間だけ、「貸し切り」にしてくれた。
田村さんがこの日、用意してくれたメニューは、クエ、タイの刺身。冷えたビールで乾杯し、田村さんが農業を再開したことを祝った。2リットル入りのビール瓶を2人で3〜4本ほど開けた後、ココナツの果汁で作った地酒「トゥバ」を飲んだ。
田村さんによると、台風の被害を受けたため、長く寝かせた質の良いトゥバは見つけるのが難しくなっているという。「台風でココナツがたくさん倒れたので、この酒もなかなか飲めなくなるかもしれませんね」。田村さんが近所住民から手に入れてくれた2年モノのトゥバには、苦みがなく、まるでワインのような深い味わいがあった。
▽掘っ立て小屋
トライシクルドライバーのリベリト・バナドラ(42)さん一家にも、お世話になった。出会ったのは、台風上陸から1カ月が過ぎた2度目の現地入りの時だった。
被災地を移動するためにドライバーとしての仕事を依頼すると同時に、仲良くなったバナドラさんの自宅に宿泊させてくれるよう、無理な願いをしてみた。今となれば、被災者の生活ぶりをもっと身近で知りたいという気持ちがあったのかもしれない。奥さんのエドナさん(34)は、家計が苦しいにもかかわらず、新鮮な鶏肉で作ったフィリピン料理をいつも振る舞ってくれた。
暴風雨でバナドラさんの家は吹き飛ばされ、家の前に止めていた商売道具のトライシクルも失っていた。被災1カ月たって記者が見た家は、屋根だけでなく、柱もすべてなぎ倒され、原型をとどめていなかった。
バナドラさん夫婦と長男サンチャゴ君(14)、次男キム君(7つ)、三男マークアグスティン君(3つ)の5人は、畳2畳もないほどの小さな掘っ立て小屋に丸まりながら寝ていた。がれきの中からトタン板と木材を見つけ出し作ったという。電気などなく、水も井戸水だけ。バナドラさん宅に泊まるときは、日の出とともに起床、取材前に水牛を眺めながら水浴びするのが日課だった。
被災から1年たった11月、バナドラさんを訪ねた。自宅は台所、居間に加えて寝室2室が完備された立派な家になっていた。宿泊させてもらった。電気も通り、長男サンチャゴ君がテレビを見ていた。こちらもうれしくなった。
バナドラさんによると、被災後激減した仕事も、街に活気が戻るにつれて、少しずつだが客足も戻っているという。今は1日250ペソでトライシクルを借りて仕事をしている。多いときは1日600ペソ以上の収入がある。「お金をためてトライシクルを買いたい」と、はにかんだ。
▽被災者と暮らす
復興が進むにつれ、街のホテルは営業を再開し始めたが、1年間の取材を通じて、私はバナドラさん宅に宿泊することにこだわり続けた。訪問する度に変わっていく被災者の生活を目の当たりにし、「夜も一緒に時間を過ごすことで、被災者の気持ちが少しでも分かるのでは」と思ったからだった。
「被災者宅に宿泊している」とメディア仲間に話すとけげんそうな顔で見つめられることもあった。しかし、彼らと過ごした時間があったからこそ、被災者目線の取材に徹することができたと思っている。彼らの生活が本当に元通りになる日まで、取材を続けていきたい。(鈴木貫太郎)