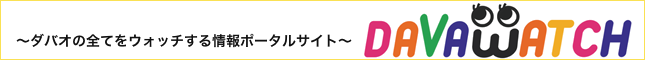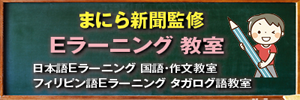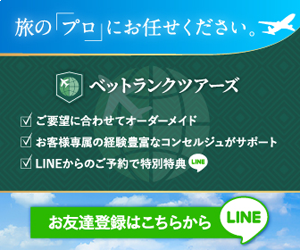バタンガス港
「開発と生活」の狭間で

一九九三年から九四年にかけ、頻繁に港を利用した。週末午前三時すぎ、パサイ市からバタンガス市行きの始発バスに飛び乗り、夜明け前に港着。すぐさま乗客を詰め込んだ木造船の人いきれの中へ紛れ込む。対岸ではジプニーやトライシクルの天井に頭を打ち付けながら島内をはい回る。「旧日本兵生存」の情報を追い求めてこんな生活を続けていた。
寝ぼけ眼をこすりながら、わさわさした港を通るのがとても好きだった。乗客めがけて未舗装の停車場を突進する荷物運びの男たち。「カイン・ナ」(食べませんか)と大声を上げる飯屋の女たち。乗船前には必ず地元産の豆を丸ごと煮立てただけの「バラコ・コーヒー」で塩パンを腹に押し込み、気持ちを整えた。
九四年六月二十七日未明。やはり港にいた。取材目的は旧日本兵ではなく、日本政府の援助事業、港拡張工事に伴う住民の強制立ち退き。前日深夜に「軍・警察に囲まれた」という住民の通報を受け、車を飛ばして駆け付けた。
住居取り壊しが始まったのは午前八時ごろだっただろうか。「取り壊し部隊」を満載した船が海岸沿いの住居を急襲、背後からは兵士や警官が催涙弾や威嚇射撃で上陸部隊を援護した。港の男たちは石やビン類を投げつけて抵抗したが、一時間もたたないうちに総崩れとなった。家財道具を担いで逃げ出す住民、破壊された家の傍らで泣き叫ぶ子供たち。港の生活が壊されていく光景を催涙弾でかすむ目に焼き付けた。
今年一月十六日早朝、第二期工事(借款供与限度額百四十六億円)の起工式取材で約八年ぶりに港内へ入った。あのけん騒、家屋の残がいに代わって、第一期工事(同五十八億円)で整備された「物流基地」の乾いた空間が広がっていた。
起工式の会場はコンテナヤードの一角だった。「首都圏に集中した物流の分散とカラバルソン地域の開発推進。第二期工事は発展への入口だ」。港拡張工事の意義をうたった政府広報が三段積みコンテナの一角に張られ、工事用ヘルメットをかぶったアロヨ大統領の大写真が出席者を見下ろしていた。
日本政府関係者らのあいさつを聞きながら、会場横のブロック塀が気になった。巨額を投じた港に不相応な粗雑な作り。コンクリートが乾ききらず黒ずんだ部分もある。そして、所々に開いた窓様の穴には白い布が張られていた。
「何のための塀だろう」。布をめくると、そこには海沿いに続くヤシ並木と家々、小型バンカの群れがあった。強制立ち退き前に目にした懐かしい風景。ヤシの木陰から住民ににらみを利かす警官隊の姿を見て「塀」の意味が分かった。この家々、港の生活も第二期工事で取り壊される運命にあったのだ。(酒井善彦)