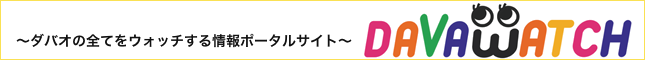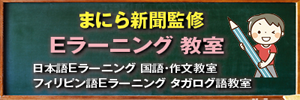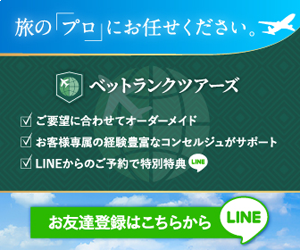移民1世紀 第3部・新2世の闇と未来
第9回 ・ 父の死と息子の岐路

5歳の誕生日を祝ってもらうショウ君(右)=写真上。火葬場に安置された日本人男性のひつぎ=写真下
そのあばら屋は、リサール州アンティポロ市の山中、幹線道路から枝分かれした未舗装路を車で四十分ほど走ったところにあった。
竹を編んだ戸を開けると、根本まで吸いきった一本五十センタボのフィリピン製タバコの吸い殻が五つとカップ酒の容器を流用した「ランプ」二つが目に入った。残されていた食料はわずかな生米と生卵二つ、バゴーン(エビの塩辛)。電化製品は古ぼけた四〇ワットの蛍光灯一本だけ。食卓では、食べかけの目玉焼きとご飯に無数のウジがわき、足元では日本から持ち込んだとみられる、バッテリーのない携帯電話が泥にまみれていた。
住人だった父と子は約三年をこのあばら屋で過ごした。父は東京都出身の日本人男性(57)。子は内縁の妻の比人女性(34)との間に生まれたショウ君(5)。隣人の話では、女性は二〇〇二年九月ごろ夫と子を置いて家を出た。比人男性と一緒になるためだったらしい。
父は二〇〇三年六月十五日夜に心臓発作を起こし、あばら屋前のコンクリートの上で亡くなった。隣人がうなり声に気付いて駆け付けたが、意味不明の日本語を一言、二言つぶやいた後、息を引き取った。子は異変に気付くことなく翌朝まで眠り続けたという。
残された旅券三冊の記録によると、男性が日本を最後に出国したのは九年以上前の一九九四年五月。以後、ビザは一度も更新されておらず、九六年八月に在比日本大使館で取得した三冊目の旅券はスタンプ一つ押されないまま〇一年に失効していた。
男性に職はなく、生活は困窮を極めていたようだ。近所の雑貨屋に残る男性への掛け売り表には「タバコ一箱十ペソ、パン六ペソ、石けん五ペソ、砂糖十ペソ、即席めん十ペソ、生米三十四ペソ・・」と寂しい数字が並ぶ。百ペソ単位で現金も借りていたようで、掛け売り分を合わせた借金総額は一万ペソを超えていた。
男性が比の山中へ移り住んだのはなぜか。ショウ君の将来をどのように考えていたのか。隣人らには「息子を置いて日本へは帰れない。連れて帰りたいが、旅券を取る金がない」と漏らしていたようだが、日記などは残されておらず本心を知る手だてはない。息子の名を漢字で書き留めた紙もなく、ショウ君が「日本名」を知る機会も永遠に失われてしまった。
男性の遺体は、死から二週間以上が経過した七月三日午後、マニラ市にある中国人墓地でだびに付された。立ち会ったのは在比日本大使館の領事部職員二人と葬儀会社の従業員だけ。男性は「マシーン5」と看板の掛かった火葬設備に入れられ、十年近く過ごしたマニラの空へ上がっていった。
父の死は実は、残された息子の人生を左右する岐路になる可能性を秘めていた。日系比人として比で生きていくのか。それとも比系日本人として日本で生きていくのか。
地元バランガイ(最小行政区)関係者も「母親の消息が分からない以上、日本の親類に引き取ってもらうのが一番いい」と日本の親類を待ち続けたが、後者の選択肢が用意される機会はついに訪れなかった。
引き取り手がなく孤児施設送りも検討される中、ラスピニャス市在住の比人女性(33)が養子にしたいと現れた。首都圏在住の複数の日本人からも同様の申し出があった。結局、バランガイ側は「どうしてもと言われたので」と女性を引き取り人に決め、ショウ君は父と三年間を過ごしたあばら屋を去って行った。
それから約一カ月半後。ショウ君が五回目の誕生日を迎えた八月十七日、ビレッジ内にある女性宅では大きなケーキや心づくしの比料理が並んだ。「境遇に同情して引き取った。養子にした以上、比人として育て上げる」と話す養母に「ママ、ママ」と寄っていく息子。アンティポロ市の山中から遠く離れた風景の中には、岐路を既に通り過ぎた新二世の姿があった。(つづく)
(2003.9.16)